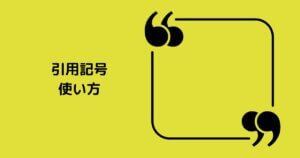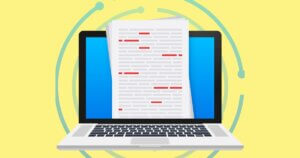文章チェックは自分が書いた文章に間違いや不適切な表現がないかを確認することです。文章チェックをすることで、文章の品質と信頼性を高める事ができます。
文章チェックをしなかったことでトラブルや失敗事例は数多くあります。ビジネス文書では、相手からの信頼を失ってしまい取引を失ってしまったという事例もあります。
そこで当記事では文章チェックの必要性と効果的方法について紹介します。
文章チェックの必要性
文章を書く際に重要なことは、相手に伝えたいメッセージや主張をわかりやすくすることです。自分で書いた文章は、実は自分で読み返しても気づかない間違いや不自然さがある可能性があります。そこで文章チェックが必要になるのです。
相手の元に届いた文章の中に、誤字脱字や不適切な表現があると困ったことになってしまいます。せっかく築いてきた信頼関係が壊れてしまう可能性もあるのです。文章チェックの方法は大きく分けると2つあります。第三者にチェックしてもらう方法と自分自身でチェックする方法です。当記事では自分でチェックする方法について特化し紹介してまいります。
文章チェックはなぜ必要なのか
「文は人なり」という言葉があるように、私たちは無意識のうちに文章から書き手の人柄や価値観などを想像しています。
誤字脱字が多い文章を受け取った時にどう感じるでしょう。具体的な印象は人によるかもしれませんが、一般的には次のように思われてしまうのです。
・相手に対する敬意や配慮がない人が書いている
・書いている人は文章力がないし、知識や情報についても信じていいか疑わしいと感じる
・言葉の意味を考えると何を言おうとしているのか分からなくなる
誤字脱字だけに注目しても、このように相手からの印象はとても悪くなってしまいます。しかし文章チェックするのは誤字脱字だけではありません。表記ゆれ(単語の表示がそろっていない)や文法の間違いもありますし、そもそも伝えたい内容が明確になっているかどうかなどについての文章チェックもあります。
対面して言葉で伝える場合には、身振りや手振りや表情に声の強弱などの要素があって、メッセージが相手に明確に理解されます。しかし文章には、文字以外の要素はありません。相手にわかりやすく伝わるように文章を書くには、文章チェックは重要なのです。
文章チェックの言い方・言い換え
一口に文章をチェックすると言いましても実は複数のチェックがあります。主な文章チェックの言い方・言い換えは以下の4つです。
・校正
・推敲(すいこう)
・添削
・校閲
例えば、誤字脱字や表記ゆれなどを修正する「校正」というチェックがあります。また「推敲(すいこう)」というチェックでは、伝えたい事が明確でわかりやすくなっているのかをチェックします。
また第三者として文章チェックをする場合は、他人の文章を読んで校正や推敲をします。そのことを「添削」すると言います。そして書き手に対してアドバイスをするのです。
そして書かれている知識や情報について、間違いがないのかのチェックをすることも重要です。事実やデータに間違いがないのか、法令などに反していないのかのチェックをするのです。これは「校閲(こうえつ)」と言います。
文章チェックは仕事で必須
現代のビジネス環境において、文章チェックは仕事で必須のスキルです。なぜなら、正確で分かりやすいコミュニケーションが成功に欠かせないからです。文章チェックは次のように重要です:
プロフェッショナリズムの向上: 誤字や文法ミスがある文章は、専門性や信頼性を損なう可能性があります。文章チェックを通じて、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
クリアなコミュニケーション: 複雑なアイディアや情報を効果的に伝えるためには、文章の明瞭さが不可欠です。文章チェックを通じて、読み手がスムーズに理解できる文章を作成できます。
ミスの軽減: 仕事においては、誤った情報や指示を伝えることが大きな問題となります。文章チェックによって、ミスを軽減し、業務効率を向上させることができます。
リーダーシップの向上: リーダーやマネージャーとして、他の人々に対してクリアで影響力のあるコミュニケーションを行う必要があります。文章チェックは、リーダーシップスキルを高める一環として重要です。
専門知識の共有: 専門的な知識を持つ人が、その知識を他の人に伝える場合も、文章チェックが重要です。専門用語を分かりやすく説明し、読み手に適切な情報を提供するための手段として活用できます。
要するに、文章チェックは仕事で成功するために不可欠なスキルです。正確で分かりやすい文章を作成することで、効果的なコミュニケーションを実現し、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
メールの文章チェックは日常的に必須
メールの文章チェックは、日常的に必須なスキルです。なぜなら、メールはビジネスや個人間のコミュニケーションにおいて重要な役割を果たすからです。
- プロフェッショナリズムの維持: メールはプロフェッショナルな印象を与える手段として利用されます。正確なスペルと文法、適切な語彙を使うことで、信頼性と専門性を高めることができます。
- 誤解の回避: 誤った情報や不適切な表現が含まれるメールは、誤解や混乱を引き起こす可能性があります。文章チェックを通じて、メッセージが明確で誤解が生じないようにします。
- 効果的なコミュニケーション: 正確で分かりやすいメールは、受信者にメッセージを迅速かつ効果的に伝える手助けとなります。読み手が素早く理解できるように文章を整えることが重要です。
- プライバシーとセキュリティ: 誤った宛先や内容のメールが送信されることは、プライバシーやセキュリティの問題を引き起こす可能性があります。文章チェックを通じて、誤送信や不適切な情報漏洩を防ぐことができます。
- 印象の向上: 良い文章は、受信者に良い印象を与える一方で、不適切な表現や誤りがあるメールは逆効果です。文章チェックによって、良い印象を残すことができます。
- メールの効果測定: メールの反応や返信率を向上させるためにも、文章の内容や表現方法を適切にチェックすることが重要です。
要するに、メールの文章チェックは、正確な情報伝達と良好なコミュニケーションを維持するために不可欠です。プロフェッショナルな印象を持ち、相手に適切なメッセージを届けるために、日常的に文章のチェックを行いましょう。
文章チェックポイントリストでチェックすること
文章チェックを効果的に行うためには、以下の文章チェックポイントリストが役立ちます。
1)スペルと文法
- 誤字やタイプミスがないかを確認する。
- 文法の誤りや不適切な表現を修正する。
2)表現と語彙
- 適切な語彙を使用しているかを確認する。
- 冗長な表現や不必要な繰り返しを排除する。
3)論理と組織
- 文章全体の論理的な流れと組織を確認する。
- 段落ごとのトピック文や遷移句を使ってつながりを強化する。
4)読みやすさ
- シンプルで明確な表現を心がけ、読み手にストレスをかけないようにする。
- 長文を適宜分割し、適切な箇所で改行を入れる。
5)一貫性と統一性
- 表記や用語の一貫性を保つ。
- 形式やスタイルが統一されているかを確認する。
6)情報の正確さ
- 提供された情報が正確であるかを確認する。
- 数値やデータが正確に表現されているかを確認する。
7)読み手の視点
- 読み手の立場になって文章を読み直し、誤解や疑問が生じる箇所を特定する。
- 読み手にとって重要な情報が欠落していないかを確認する。
8)目的達成
- 文章の目的や伝えたいメッセージが達成されているかを確認する。
- 読み手に対して望む影響や行動を促すことができるかを考える。
この文章チェックポイントリストを使用することで、文章のクオリティを向上させることができます。スペルや文法の誤りをチェックするだけでなく、表現や組織、読みやすさなど、文章のさまざまな側面を確認し、読み手にとって価値のある内容を提供することができます。
日本語文章チェックの効果的な方法
日本語文章の効果的なチェック方法は、文法や誤字の修正だけでなく、表現の見直しや論理的な流れの確認が重要です。文章を一時的に離れてから見直すことで、客観的な視点を持ちやすくなります。
読み手の立場に立ち、分かりやすさを意識して表現を整え、論理的なつながりを確認しましょう。他人の意見やフィードバックも取り入れることで、より洗練された文章を完成させることができます。
文章チェックツール
文章を書いた後でチェックを行い、修正をします。しかし評価者や上司から修正した後の文章が戻ってきたのに、修正箇所を原文から探し出して確認することは、なかなか大変な作業となります。
そこで役立つのが文章チェックツールやサイトです。校正に提出する直前の文章と修正後の文章をテキストのままでフォームに貼り付けて、変更された部分を確認することです。
文章の差分チェックとは
文章の差分チェックとは、一般的に校正前と校正後のテキストを比較して、差異を把握し確認するためのチェック作業です。文章の差分チェックをするには、アプリで行う方法や、サイトにアクセスしてWebアプリを使って行う方法があります。またwordやエクセルを使う方法、あるいはpdfで文章比較する方法もあります。
状況に合わせて利用してみてください。下記のリンクから文章比較ツールについて紹介しています。

文章チェックサイトで文章一致・パクリ・コピペをチェックする
読書感想文コンクールに応募する場合や、ネット上に掲載される記事など、公に公開される可能性がある文章である場合は、著作権侵害にならないように注意する必要があります。
自分が書いた文章が他の文章と似ていないかについて、文章の重複チェックをする必要があります。文章のパクリやコピペと言われないように、配慮するのです。もしも著作権侵害となれば盗作として訴えられる可能性もあるからです。
またもしもネット記事として書く場合には、他人の文章を無断でコピペをしている可能性が高いと判断されると検索エンジンからのサイト評価は低くなってしまう結果につながります。
また読書感想文が苦手でコピペで誤魔化しているというケースがあると聞きます。単に学校の課題として提出しているのであれば、大きな問題になることはありません。しかし時に教師が優れた読書感想文であると判断し、コンクールに応募したりするケースがあります。もしそうなれば盗作騒動へと発展してしまう可能性もあるのです。
ネット上に公開されている文章と自分が書いた文章との文章重複チェックができるツールには以下のようなものがあります。
・こぴらん(無料。一度にチェックできる文字数は4000文字の制限がある)
・copiperin(年間税込6600円。テキストファイルの他に、CSVやWordファイルも読み込み可能)
・Copy Content Detector(無料で4000文字まで利用可能。有料プランでは8000文字に対応)
文章のチェックサイトのおすすめ:無料
文章チェックができるサイトはかなり多く存在します。無料プランや有料プランの選択ができるサイトや保存ができるサイトもあります。注意が必要なのは、サイトの文章チェックはあくまで参考レベルとすべきということです。特に無料プランで利用する場合です。無料には無料のリスクがあるということです。
またチェックする文章の中には個人情報や機密情報を含めないことです。リスク対策が万全とは言えないからです。あくまで参考という使い方がおすすめです。
おすすめサイトを以下に紹介しますが、実際に試してみて使えそうかどうかを自己責任で選びましょう。
1)PRUV(無料で使える日本語文章校正支援サービス。300文字までなら登録なしで文章チェック可能です。会員登録すると2万文字までチェック可能。月額500円の有料プランは文字制限は5万文字までアップし、表記ゆれなどの文章チェックが細かく設定可能)
2)Enno(無料で登録なしに利用可能のツール。誤字脱字やタイポなどを検出してくれます)
3)日本語文章校正チェックサービス(無料で登録なしで利用可能。最大で1万文字に対応しています)

文章チェックAIは補助ツール
文章チェックには、AI(人工知能)を活用する方法があります。AIは文法やスペルのミスを検出するための自動校正ツールや文法チェックソフトウェアとして利用されることがあります。AIベースの文章チェックツールは、高度な自然言語処理技術を使用して、文章の文法的なエラーやスペルミスを検出し、修正の提案を行います。
AIベースの文章チェックツールは、次のような特徴があります:
- 自動校正: 文法ミスやスペルミスを自動的に検出し、修正の提案を行います。一般的な文法ルールやスペル辞書に基づいてエラーを検出するため、基本的なミスを見逃すことがありません。
- 文脈を考慮した修正: AIは文脈を理解し、修正の提案を行います。文の意味やつながりを考慮して修正案を提示するため、より適切な修正案を提供できることがあります。
- 表現の改善: AIは語彙や表現のバリエーションを持っており、より適切な表現やフレーズを提案することがあります。文章をより鮮やかにし、読み手に伝えたい意図を的確に表現するための支援をします。
ただし、AIベースの文章チェックツールはあくまで補助ツールであり、完璧ではありません。文脈や意図を正確に理解することは難しいため、提案された修正を常に受け入れる必要はありません。人間の目で文章を確認し、論理的な整合性や読みやすさ、読み手の視点を考慮することも重要です。
AIベースの文章チェックツールは、効率的な方法で文章の品質を向上させることができますが、最終的な判断は人間が行う必要があります。人とAIの組み合わせによって、より優れた文章を作成することができるでしょう。
文章チェックアプリも活用
文章チェックのために利用できるいくつかの便利なアプリがあります。以下にいくつかの人気のある文章チェックアプリを紹介します。
Grammarly:
Grammarlyは、文法、スペル、句読法のエラーを検出し、修正の提案を行う高度な自動校正ツールです。ウェブブラウザ拡張機能として利用できる他、デスクトップアプリやモバイルアプリとしても提供されています。
Hemingway Editor:
Hemingway Editorは、文章の読みやすさを向上させるためのツールです。長い文や複雑なフレーズ、冗長な表現などを検出し、修正の提案を行います。また、文の強調や品詞の表示などもサポートしています。
ProWritingAid:
ProWritingAidは、文法、スペル、句読法のエラーを検出するだけでなく、文章のスタイル、表現、一貫性なども評価し、改善の提案を行うツールです。プラグインやオンラインエディタとして利用できます。
これらのアプリは、自動校正や修正の提案を行うことで、文法やスペルミスを見つけるのに役立ちます。しかし、完璧なチェックを行うためには、文脈や意図を考慮し、読みやすさや論理的な整合性を確認する必要があります。
wordで文章チェックすることも可能
マイクロソフトのwordで文章作成をする人は多いと思います。実はwordにも文章チェックの機能があります。
一つは、スペルチェックと文章校正を一緒に行う方法です。メニューで「校閲」をクリック>「スペルチェックと文章校正」を選ぶことで、誤字脱字や文法の間違いをしてくれるのです。
またwordの自動文章校正を使うこともできます。「校閲」から「オプション」クリック>「オートコレクトのオプション」>「文字列の置き換え」をオンにしておきます。入力ミスや文法の間違いがあれば自動で検出して修正するかを聞いてきます。
エクセルでの文章チェック方法
エクセルを使った文章チェック方法は、データの整理や分析においても重要です。以下にエクセルでの文章チェック方法を簡単に説明します。
- スペルチェックの活用: エクセルにはスペルチェック機能が備わっており、誤字を検出するのに役立ちます。セル内のテキストを選択し、右クリックして「スペルチェック」を実行しましょう。
- テキスト整形: テキストを整形して読みやすくするために、セル内のテキストを適切なフォント、サイズ、色に変更できます。また、改行やインデントを使って段落を整理しましょう。
- 関数や数式の確認: もしエクセル内に数式や関数が含まれている場合、それらが正しく動作しているか確認します。数式の演算子やセルの参照が正しいかどうかをチェックします。
- 列の幅調整: テキストがセルに収まりきらない場合、列の幅を調整してテキストが適切に表示されるようにします。これにより、情報が欠落することなく確認できます。
- フィルタやソートの利用: データが多い場合、フィルタやソートを使って特定の条件に合致するデータを絞り込み、必要な情報を効率的にチェックできます。
- コメントの追加: エクセルのコメント機能を使用して、テキストに対する補足情報やメモを追加することができます。これによって、他の人と共有する際に説明が不足しないようにします。
- プレビューモードの活用: エクセルのプレビューモードを使って、印刷時のレイアウトやテキストの配置を確認します。これによって、印刷物としても適切な文章かどうかを確認できます。
エクセルはデータ処理のツールとして広く利用されていますが、文章のチェックにも有用です。スペルチェックや整形、関数の確認などを通じて、正確で分かりやすい文章を作成しましょう。
文章チェックを英語で行う場合の手順
英語の文章チェックを行う際には、コミュニケーションの質を向上させるために以下の手順が役立ちます。
- スペルと文法の確認: 英語の文章では、正しいスペルと文法が重要です。自動修正機能や文法チェックツールを使用して誤りを検出し、修正しましょう。
- 表現の見直し: 英語には多様な表現方法があります。シンプルかつ適切な言葉を選び、冗長さを減らすことで文章をクリアにします。
- 論理的な構造の確認: アイディアが順序立てられ、論理的なフローを持つことが重要です。段落ごとのトピック文や遷移句を使用して、論理的なつながりを確保します。
- 適切な語彙の選択: 同じ意味を持つ単語やフレーズを試してみて、適切な語彙を選択します。読み手にとってわかりやすく、的確な表現を目指しましょう。
- 自然なフローの確保: 文章が読み手にとってスムーズに読めるように、文と文、段落と段落のつながりを意識して調整します。
- 読み手の視点で確認: 文章を読む立場になって、読み手がどのように受け取るかを考えます。説明不足や疑問が生じる箇所を特定して改善します。
- フレーズの多様性: 同じフレーズや単語の繰り返しを避け、多様性を持たせることで文章を魅力的にします。
- 簡潔さと明確さ: 冗長さを避けて、簡潔な表現を心がけます。冗長な表現や不要な修飾語を省くことで、文章がより明確になります。
英語の文章チェックは、正確なコミュニケーションを実現するための重要なプロセスです。スペルや文法の誤りを修正し、表現を整え、読み手の視点を考慮して文章を洗練させましょう。
まとめ
文章のチェックをすることは、自分が書いた文章の品質を高めて、相手からの信頼性を高めるために必要なことです。誤字脱字や文法の間違いなどのミスに気づかずに、相手に文章が届いてしまうとせっかく構築してきた信頼関係は壊れてしまう可能性があります。
文章チェックをして読みやすい文章を相手に届けなければ、仕事においても人生においても大きな損失になる可能性があります。文章チェックの方法はたくさんあります。自分が使いやすく、リスクが少ないと思う方法を選択して実行しましょう。
関連記事一覧はこちら
文章チェックの必要性と効果的な方法*当記事