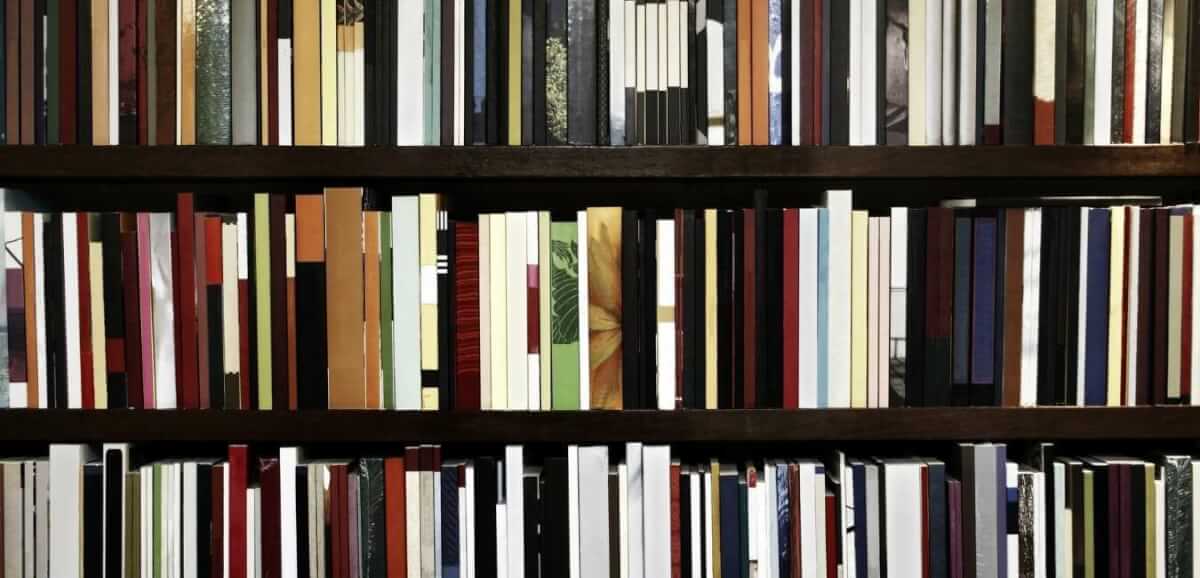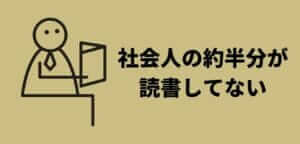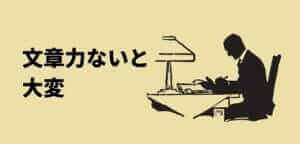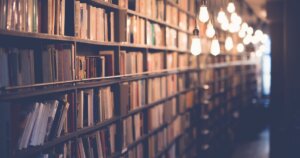本のサイズの種類には、たくさんのサイズの種類があります。
書店では、単行本・文庫本に大きく面積が分けられていますが、ついで新書というサイズの本の種類があります。
少し縦長のスリな感じの本が新書です。
では、サイズ以外の違いについてはご存じでしょうか。
新書とは何か?その歴史と魅力を解説
新書とは、新しい本という意味ではありません。
新しく出版された本は、新刊と言われます。そして新刊と言われるのは期間が限定されています。発行日から3ヶ月半までの間の本を新刊と呼びます。
これは本来、出版社と書店との間の取り決めで、新刊の間は書店から出版社に本を返せる期間として定められている期間のことを呼ぶものです。
新書とは何か?簡単に説明すると
新書とは、本来は新書版というサイズについて指し示すものでした。
新書版のサイズは高さが173mmで幅が105mm(世界大百科事典によれば173mm✖️106mm)というサイズです。文庫本よりは背が高く、単行本よりは一回り小さい本というサイズです。
新書とは|見分け方の一つはサイズ・大きさ
元々は、サイズの違いにの他に、新書・文庫本・単行本には、それぞれジャンルの違いがありました。しかし、今や本のサイズを変更して文庫化されることも少なくなく、サイズとジャンルの関連性は無くなってきていると思われます。
写真集などはA4判(297mm✖️210mm)が多く、文字が中心である文庫本や単行本は、それぞれ文庫本がA6判(148mm✖️105mm)と単行本がB6判(182mm✖️128mm )のサイズで作られています。新書サイズは173mm×105mmですので小型というサイズ感がわかります。
新書の意味
新書(しんしょ)とは、新書版の本・叢書(そうしょ)と定義されています。
叢書とは、同じ種類・分野の事柄を、一定の形式でまとめたもの・編集したものとされます。
新書は、専門的な知識や複雑な概念を、一般の読者にもわかりやすい言葉で解説することを重視しています。このため、専門家や学者によって執筆された内容が、専門用語や専門的なアプローチを避けつつも、具体的な事例や比喩を交えて解説されています。
新書のジャンル
新書は、そのコンパクトなサイズと分かりやすい解説の特徴から、幅広いジャンルにわたって出版されています。以下に、一般的な新書のジャンルのいくつかをご紹介します。
- 学問・教養: 初期の新書は、学術的な知識を一般の読者に提供することを目的としていました。歴史、哲学、文学、芸術、科学など、さまざまな学問分野に関する新書が存在します。これによって、専門的な知識を持たない人々でも基本的な教養を身につけることができます。
- 自己啓発・心理学: 新書は自己啓発や心理学に関するテーマも多く扱っています。人間関係、コミュニケーション、ストレス管理、幸福論など、個人の成長や心の健康に関する内容が取り上げられています。
- ビジネス・経済: ビジネスや経済に関する新書も人気です。経営戦略、マーケティング、リーダーシップ、投資など、ビジネスパーソンや起業家に役立つ情報が提供されています。
- 社会問題・政治: 新書は時事問題や社会的なテーマにも焦点を当てることがあります。政治、社会制度、環境問題、人権、ジェンダーなど、社会の動向や課題についての情報が提供されています。
- 科学・技術: 科学や技術に関する新書もあります。宇宙、生物学、テクノロジーの進化など、最新の科学的な知識や技術動向を分かりやすく解説したものがあります。
- 健康・医学: 健康や医学に関する新書も人気です。食事、運動、メンタルヘルス、疾患の予防といった健康に関する情報が提供されています。
- 趣味・娯楽: 趣味や娯楽に関する新書も存在します。料理、旅行、趣味の深掘り、エンターテインメント業界の裏側など、楽しみながら学べるコンテンツが含まれています。
総じて言えば、新書は多様なジャンルを網羅し、幅広い読者に対応しています。初心者から専門家まで、様々な興味や関心に応じて選べるため、知識を楽しみながら広げる手段として魅力的です。

新書のページ数
新書のページ数は通常、100~300ページ程度と比較的短い範囲で構成されています。これは、新書の特徴であるコンパクトなサイズと手軽さに合わせています。以下に、新書のページに関するポイントをいくつか説明いたします。
- 簡潔な内容: 新書は限られたページ数内で情報を提供することを重視しています。そのため、本質的な内容に絞り込まれ、冗長な説明や繰り返しは避けられています。読者にとって、効率的に知識を得る手段となります。
- 専門的な内容の要約: 専門家や学者によって執筆された内容を、一般の読者が理解しやすい形にまとめています。専門用語や複雑な理論を避け、具体的な事例や比喩を用いてわかりやすく説明することが一般的です。
- テーマの絞り込み: 新書は一つのテーマやトピックに焦点を当てることが多いです。そのため、特定の分野に関する基本的な知識や洞察を提供することができます。幅広いトピックをカバーしながら、各新書が一つのテーマに深く掘り下げています。
- 読みやすさ: 短いページ数で構成されているため、新書は比較的短時間で読み終えることができます。通勤時間やちょっとした隙間時間にも手軽に読書を楽しむことができるので、忙しい日常にも適しています。
- 幅広い読者層へのアプローチ: 専門的な知識を持つ人から初心者まで、幅広い読者層に向けてアプローチしています。専門家向けの高度な議論から、一般の人々が興味を持つようなトピックまで幅広いバリエーションが存在します。
総じて言えば、新書のページ数は、効率的な情報提供と読みやすさを両立させるために工夫されています。限られたページ数内で、専門的な知識や興味深い情報を凝縮して提供することで、幅広い読者に有益な読書体験を提供しているのです。
新書の発売日
新書の発売日は、出版社や書籍ごとに異なることがありますが、一般的には以下のポイントが考慮されます。
- 定期的な刊行: 多くの出版社は、新書を定期的に刊行しています。これにより、読者は一定のペースで新しい本を楽しむことができます。週刊、月刊、季刊などの刊行スケジュールが設定されていることがあります。
- テーマや内容による変動: 新書の発売日は、そのテーマや内容によっても変動することがあります。特定の時事問題やイベントに関連する内容の新書は、そのトピックの注目度や重要性に合わせて、短期間で刊行されることがあります。
- 広告やプロモーションの影響: 新書の発売日は、広告やプロモーション活動によっても影響を受けることがあります。発売前から新刊の情報が公になり、読者の関心を引きつけるための準備期間が設けられることがあります。
- オンライン販売の影響: 近年では、オンライン書店が増えてきたため、新書の発売日に関する情報がネット上で広まることもあります。オンライン予約やプレオーダーのシステムを活用して、発売前から注文を受け付けることも行われています。
- 限定版や特別版の場合: 一部の新書は限定版や特別版として発売されることがあります。これらの場合、通常の発売日とは異なるスケジュールで刊行されることがあります。
総じて言えば、新書の発売日は出版社や書籍の性質によって異なりますが、定期的な刊行スケジュールやテーマに応じたスケジュール、広告やオンライン販売の影響などが重要な要素となっています。読者は、出版社の公式情報や書店の情報を通じて、新書の発売日や情報を確認することができます。

新書とは|その歴史の始まりは岩波新書
そのほかに、世界百科事典やウイキペディアによれば、「1938年(昭和13年)に岩波書店が古典中心に収録する岩波文庫に対して、書き下ろしを中心として、岩波新書として創刊」が新書の始まりと記録されています。(書き下ろしとは、新聞や雑誌への掲載を経ずに、直接発表されるもの)
当時の文庫の判型は決まっておらず、岩波新書のサイズは172mm✖️112mmでした。その後、1940年に用紙規格規則が告示されて、1941年に施行されています。
現在の新書サイズの173mm✖️105mmへと変更されたのは、戦後の1946年〜1949年ごろと思われます。
新書を出版している出版社と特徴
| 岩波新書 | 日本で初の新書を出版。年代ごとに想定が変わるのが特徴。ジャンルが幅広く、専門性も高い。 |
| 新潮新書 | 2003年に創刊。ページ数が少なめで実用系が中心。 |
| PHP新書 | ビジネスマン向けのテーマが多い。自己啓発やビジネス関連が中心。 |
| NHK新書 | 2001年に創刊。新しい。NHKブックスとの棲み分けがされており、生活や趣味関連のテーマに特化。 |
| 幻冬舎新書 | 2006年に創刊。テーマは幅広い。読みやすさを重視している感があります。 |
| 中公新書 | 歴史系が中心。学術的な信頼度が高い。 |
| ちくま新書 | 教養系が中心。専門的な印象が強いですが読みやすい印象もあります。 |
| 講談社現代新書 | テーマは幅広いです。従来型の歴史系などの教養系の新書も多いが、ビジネスマン向けのテーマも多い。最近は新書の定義の一つとも言える手軽に持ち歩きができるサイズ感を超えて、ページ数が多い新書が増えている。講談社はブルーバックスと講談社+α新書という別の新書レーベルも出版しています。ブルーバックスは理数系専門の新書です。講談社+α新書は実用系が中心です。 |
| 文春新書 | 政治家の新書の印象があります。実用系が多いのも特徴。 |
| 集英新書 | 社会問題や政治にフォーカスしている印象があります。またマンガ関連の新書も目立ちます。 |
| 光文社新書 | ターゲットユーザーは中高年ではなく、30代ビジネスマン。 |
| 小学館新書 | 2013年に創刊(2008年に小学館101新書を創刊)。政治・スポーツ・医学・歴史など広いジャンルをカバーしている。偶数月に出版。 |
新書の魅力|特徴と利点
新書の魅力は多岐にわたります。以下に新書の魅力の代表的なものを紹介いたします。
1)新書の魅力は手頃な価格
新書は比較的低価格で提供されることが多く、手に取りやすい価格帯であることが魅力です。高額な書籍に比べて手軽に入手できるため、多くの人々が気軽に新書を購入し、読書の習慣を身近なものにすることができます。
2)新書の魅力はコンパクトなサイズ
新書は一般的にコンパクトなサイズであり、持ち運びや収納に便利です。大きな書籍や電子書籍と比べて軽量であり、バッグやポケットに簡単に収納することができます。これにより、外出先や移動中などの空いた時間に気軽に読書ができる利点があります。
3)新書は幅広いジャンルをカバー
新書は多様なジャンルの書籍が出版されています。学術書、小説、ビジネス書、自己啓発書、歴史書、料理本など、さまざまなテーマや分野の書籍が新書として提供されています。これにより、様々な興味や関心を持つ読者が自分の好みやニーズに合わせて新書を選ぶことができます。
4)新書は情報が短くまとめられている
新書は一冊にまとまった情報を短く・要点を押さえて解説していることが特徴です。膨大な情報を凝縮しているため、読者は比較的短時間であるトピックについて理解を深めることができます。また、専門分野の知識や入門書としても活用され、初学者や学生にも有益な教材となります。
5)新書は学びとエンターテイメントの融合
新書は専門的な知識や情報の入門書的な位置付けにあります。しかし、それだけではなく、読みやすさやエンターテイメント性も兼ね備えています。分かりやすい表現やストーリーテリングの要素を取り入れながら、知識やアイデアを楽しく伝えることができます。これにより、読書は新書を読みながら学びを得るだけではなく、楽しむこともできます。専門的なトピックや複雑な概念を分かりやすく解説する手法や、興味を引くエピソードや事例の紹介などが新書の魅力となっています。
6)新書は最新の情報とトレンドを追跡
最新の情報とトレンドの追跡: 新書は時事問題や最新のトレンドに関する情報を取り上げることがあります。特定のテーマや分野に関する最新の研究成果やトピックを反映した新書が発売されることがあり、読者は迅速に最新情報にアクセスすることができます。
7)新書では著名な著者や専門が執筆
新書には著名な著者や専門家が執筆することが多いです。そのため、信頼性や専門性が高く、読者は確かな情報や洞察を得ることができます。著名な著者の新書は注目を集め、読者の関心を引く要素となります。
これらの要素が新書の魅力となっています。新書は手軽に入手でき、コンパクトで持ち運びやすいため、多くの人々が日常的に読書の習慣を持つことができます。幅広いジャンルやトピックに対応しており、知識の幅を広げるだけでなく、エンターテイメントとしても楽しむことができます。さらに、最新の情報や著名な著者の執筆によって、読者は信頼性の高い情報にアクセスすることができます。
新書はおもしろい
新書の面白さは、そのコンパクトなサイズとわかりやすい解説に加えて、さまざまな魅力的な要素が組み合わさっている点にあります。以下に、新書の面白さを詳しく解説してみましょう。
- 専門知識のアクセス可能性: 新書は、専門家や学者が執筆した内容を一般の読者にも理解しやすい形で提供しています。難解な専門用語や複雑な理論も、具体的な例や比喩を通じて分かりやすく解説されているため、初めてその分野に触れる人でも知識を得やすくなっています。
- バラエティ豊かなテーマ: 新書はさまざまなジャンルやテーマを網羅しています。歴史、科学、哲学、心理学、社会問題など幅広いトピックが取り上げられており、自分の興味や関心に合った本を見つける楽しみがあります。これによって、幅広い分野について基本的な知識を得ることができます。
- 手軽な情報収集: 新書は通常100~300ページ程度の短い本であるため、比較的短時間で読み終えることができます。これは、忙しい日常の合間や通勤時間などにも気軽に読書を楽しむことができる利点です。また、複数の新書を読むことで、幅広い知識を効率的に吸収することができます。
- 最新情報の提供: 新書は時事問題や最新のトピックにも焦点を当てることが多いです。これによって、現代の社会や技術の動向について最新の情報を手に入れることができます。自分の知識をアップデートし、社会的な議論にも参加できるようになるでしょう。
- 深い洞察と気づき: 新書は一般的な知識だけでなく、深い洞察や新たな視点を提供することがあります。専門家の視点からの分析や論考を通じて、従来の考え方とは異なる視座から世界を見つめることができるでしょう。
- 学びの喜び: 新書を読むことは、新しいことを学びながら自己成長する喜びを味わうことでもあります。新たな知識を手に入れることで、自信がついたり、自分の視野が広がったりすることがあります。
総じて言えば、新書は手軽さと専門的な知識の提供、多彩なテーマの取り扱いなどが組み合わさって、知識を楽しみながら広げる手段として魅力を持っています。初心者から上級者まで、幅広い読者にとって新書は知識の宝庫であり、学びの楽しさを提供してくれることでしょう。
新書は読みやすい
新書は、そのコンパクトなサイズや分かりやすい解説のスタイルから、一般的に読みやすいとされています。以下に、その要因をいくつかご紹介いたします。
- 簡潔な内容: 新書は限られたページ数で情報を提供することを目指しており、本質的な内容に絞られています。冗長な表現や詳細すぎる情報を避け、必要な情報を要点を押さえて提供することで、読者にとっての読みやすさが確保されています。
- わかりやすい言葉遣い: 専門用語や難解な表現を極力避け、一般の読者にも理解しやすい言葉遣いが採用されています。具体的な事例や比喩を使って説明することで、複雑な概念も理解しやすくなっています。
- 章立てや構成: 新書は、わかりやすい章立てや構成を持つことが多いです。分かりやすい見出しや小節、箇条書きなどが活用され、情報を整理しやすくなっています。これによって、読者は必要な情報を迷うことなく探しやすくなっています。
- 専門家の視点からの解説: 新書は、専門家や学者によって執筆された内容を、一般の人々に向けて解説しています。専門的な知識を持つ人々が、自分の専門分野に関する深い洞察を提供する一方で、その内容を分かりやすくまとめて説明します。
- 図表やイラストの活用: 新書では、図表やイラストが活用されることがあります。これによって、複雑な概念やプロセスを視覚的に理解しやすくなります。視覚的な情報は、文章だけでは伝えにくい内容も効果的に補完しています。
総じて言えば、新書は専門的な知識や情報を分かりやすく解説するために、多くの工夫がされています。簡潔な内容、わかりやすい言葉遣い、章立てや構成、専門家の視点、図表の活用などが組み合わさって、読者にとっての読みやすさが確保されているのです。初心者から専門家まで、幅広い層の読者にとって、新書は知識の入り口としての魅力を持っています。
新書とは高校生になったら読んでおくべき本
前述の通り、新書には実用書や専門書という印象が強くあると思います。ですので本が好きで小説などたくさん読んでいるという人でも新書を読んでいない人も少なくありません。確かに新書には小説もありますが、数は多くないために、楽しめないのではないかという先入観を持っている方もいます。
しかし高校生になったら、新書は読むべき本としておすすめします。確かに新書は、実用書や専門書の入門書という位置付けにあるものです。しかし著者は様々な分野の専門家であり、入門書的なわかりやすさを持って書かれています。高校生の時期は、未来に向けて各分野について知見を広げ、様々な世界について広く知るチャンスの時でもあるのです。
例えば新書大賞に選ばれた本を読み尽くしてみると、自分の本の選び方では出会わない新書から新しい世界を知るきっかけになるでしょう。

単行本と新書の違い
単行本は、単独で出版される本です。
小説やエッセイ、経済関連など幅広いジャンルが網羅されています。新聞や雑誌の中で連載されていた記事が、まとめられて単行本として出版されることもありますし、書き下ろしとして出版されることも少なくありません。
幅広いジャンルの中には、知識や情報をまとめたものもあり、新書と似ています。
サイズは新書よりも大きく、本自体の作り方(製本や装丁など)がしっかりしています。特に表紙が固い材質が使われているものがハードカバーと呼ばれ、従来単行本の主流でしたが、最近は表紙が硬い材質ではない紙も使われるようになり、ソフトカバーと呼ばれる単行本も増えています。
新書とは、内容が似ている部分もありますが、何よりサイズ感と製本に違いが明確です。
文庫本と新書の違い
文庫本は、より小型に作られ価格が低く設定されています。多くの方に読まれることを目的として作られているものです。
製本や装丁、紙質など、持ち運びがしやすいように軽量になるよう考えられており、サイズ感は新書よりもさらに小さくなっています。
ジャンルは幅広いですが、古典文学や単行本として人気が出た作品が文庫本として出版されるケースは非常に多いです。読書ユーザーなら書店で見て知っているように、売り場面積が一番多い傾向にあります。
実際にカバンに本を1冊入れている方のほとんどが文庫本か新書です。そういう意味では文庫本の目的は見事に達せられています。ですので、近年では文学作品だけではなく、ビジネス書が文庫本化されることが珍しくなくなりました。
新書との違いは、サイズの違いとジャンルの違いにあります。新書は専門分野の入門書的な位置付けがあります。文庫本は文学を中心に網羅されていて、単行本が文庫本としてサイズダウンして出版されているケースもあります。
まとめ
昔の新書は、タイトルを見ても専門性が高く、手に取るのはハードルが高いと感じさせる新書が多かった気がします。
2000年代以降は、新書が雑誌化しているという説が増えたように思いますが、出版社として存続をかけた工夫が裏目に出ているのかもしれません。
しかし単行本や文庫本にはない興味深い本を時々出版されているのもまた事実です。
関連記事一覧
新書とは何か?その歴史と魅力を解説*当記事