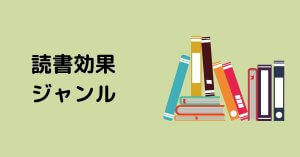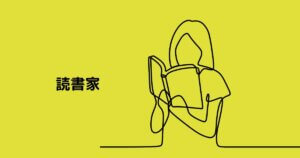読書感想文の書き出しは、「書くキッカケとなった」「読む前に感じていたこと」などから書き出していくと良いです。
しかし読書レポートの場合、一般的にテーマが指定されているなど、感想文とは少し違う書き方をした方が書きやすくなります。見た目の書き出しは「序文」からですが、作業の書き順は序文は後の方が書きやすいです。
読書レポートの書き出しの序文は最後に書く
読書レポートの書き出しは序文(・本文・結論へと続く)です。序文から書き出していこうとして、手が止まってしまった経験はありませんか。
実際には本文から書き始めた方がスムーズにかけます。結論までを書いてしまってから、序文を書く方が、書き出しの序文は書きやすく感じるはずです。
読書レポートの書き出しは後で書く
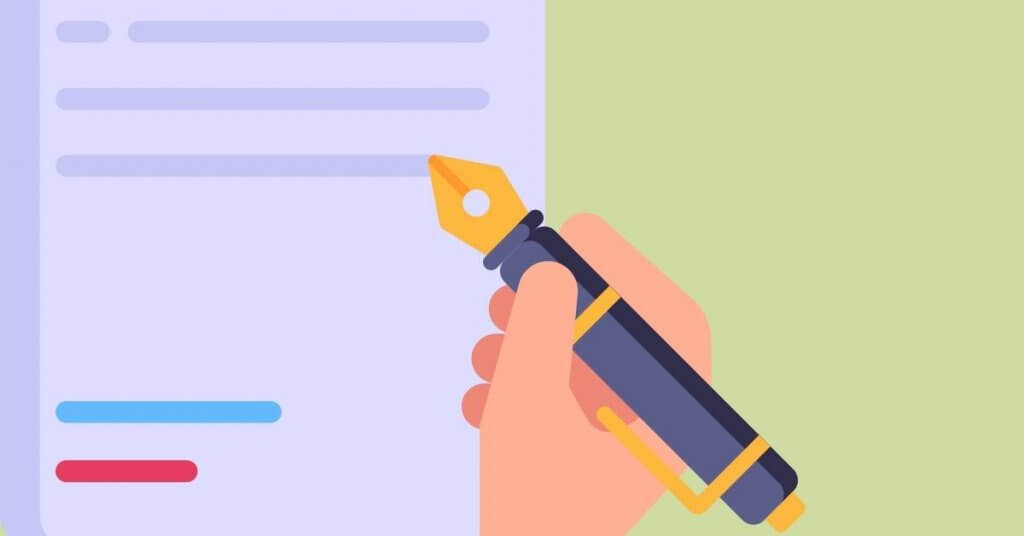
読書レポートの基本形は「序文・本文・結論」です。
書き出しは「序文」ということになりますが、現実には「本文」から書き始めていきます。最後に、序文を書く方が書きやすいからです。
本文は、「結論・理由(根拠)・事例」という構成か、「問題提起・状況説明・付帯説明」という構成で書くのがおすすめです。
読書レポートは、感想文と違い、自分の意見が中心となるものではありません。基本的には要約を書くものです。但し、出題内容によっては、要約文の他にレポート作成者の意見や感想を求められる場合もあります。

読書レポートの書き出しの序文は最後に書く
読書レポートの書き出しである序文を最後に書くのは、さきに「書きやすいから」と説明しました。
何故最後に書く方が書きやすいのかといいますと、序文に書くべきことは、題材となる書籍と当読書レポート からのエッセンスをまとめたことだからです。
ですので、序文を書くときには、本文・結論を書きまとめた内容を十分に理解している必要があるのです。
序文から書き出していくと、本文・結論との不一致が起きてしまう場合もあり、その結果、本文・結論に合わせて、修正をする必要があるかも知れません。また、序文から書き出していく場合、全体像がボンヤリしている状態ですので、書き出しがスムーズに進まない可能性も大きいです。

読書レポートの書き出し|大学生の場合
大学生や社会人でも読書感想文の提出を求められることもあります。
しかし、題材となる書籍が指定され、さらに「□□□を読んで、〇〇〇について作者に意図によってまとめ、更に自分の意見を加えたものを提出するように」等となれば、これはレポートであり、テーマに沿って作者の意見を要約し、更に自分の意見を追加してレポートを提出することになります。
どちらを求められているのかに、提出する内容は違いますので、ご注意下さい。
読書感想文であれば、感じ取ったテーマで比較的自由に感じたことを書いて問題ありませんが、レポートであれば、基本的にテーマが指定されているはずですし、書くべき内容は限定されているはずです。指定の書籍以外からも、エビデンスとなる文献等を見つけ、まとめていくことで、評価は高くなるでしょう。
読書レポートの書き出しとなる序文では、大学生の場合も基本は同じです。本文への関心を高められるように、意識を持って、書くべきです。

読書レポートの書き出しの例文
テーマを決めずに読書レポートを書く事例としてご参照下さい。
その為、やや読書感想文寄りの書き出しになっていることをお許し下さい。

書き出し例|著者名と著書そして感想から始める
書き出し例|「〇〇〇の「□□□」はとても・・・・な感動を与えてくれる小説です。〜〜〜(自分の感想)」
最もありがちなパターンです。大きなマイナスはないです。評価を高めるには、・・・・や〜〜〜への言葉の工夫が必要です。
書き出し例|登場人物への印象から始める
書き出し例|「主人公の〇〇〇はとても△△△な性格の持ち主です。〜〜〜」
登場人物の個性が強い場合には有効です。
書き出し例|中心人物のエピソードから始める
書き出し例|登場人物の〇〇〇は何故□□□をしてしまったのか。〜〜〜」
強いエピソードがあるなら有効です。
出題の内容が、読書感想文としてのレポートを求めている場合もあります。
その場合は、読書感想文の書き出しも参照して頂くと良いです。また、要約文としてのレポートを求められる場合もあります。


まとめ
読書レポートを一般的な方法でまとめる時、よく使われる構成が、「序文・本文・結論」という構成です。
書き出し部分は「序文」にあたる部分になります。但し、実際の作業手順としては、「序文」は最後に書いた方が書きやすいです。
書き出しの序文は、本文を読ませるために読み手を引きつけたい部分でもあります。ですので、作成手順としては、本文と結論を書いた後で、究極的に一言程度でアピールする文章や題材書籍の中の人物やエピソードを絡めて、書き出していく方法も有効です。
関連記事一覧
- 読書
- 読書レポートを書く大学生・社会人そして高校生|まとめ
- 読書レポート2000字の書き方を具体的に|高評価になるように
- 読書レポートの要約の割合はどの程度の配分にすべきか
- 読書レポートはテンプレートで書くと読み手が分かりやすくなる
- 大学生の読書レポート作成はテンプレートで効果的に
- 読書レポートの書き方|社会人になって差がでる
- 大学生のための読書レポートの書き方ガイド
- 読書レポートの例文から学ぶ|大学生から初心者まで
- 読書レポートの要約:例文の活用と書き出し・書き方のコツ
- 読書レポートとは何を書く|読書感想文との違いは
- 読書レポートの書き出しはどこから?例文付き*当記事
- 読書レポートは高校生にも出題|書き方の基本は同じ
- 課題図書のあるレポートを楽に書く|重要なのは準備
- 読書レポートは「考察」の書き方が肝になる
- 社会人のための読書レポートの書き方ガイド
- 読書レポート要約書き出しの方法