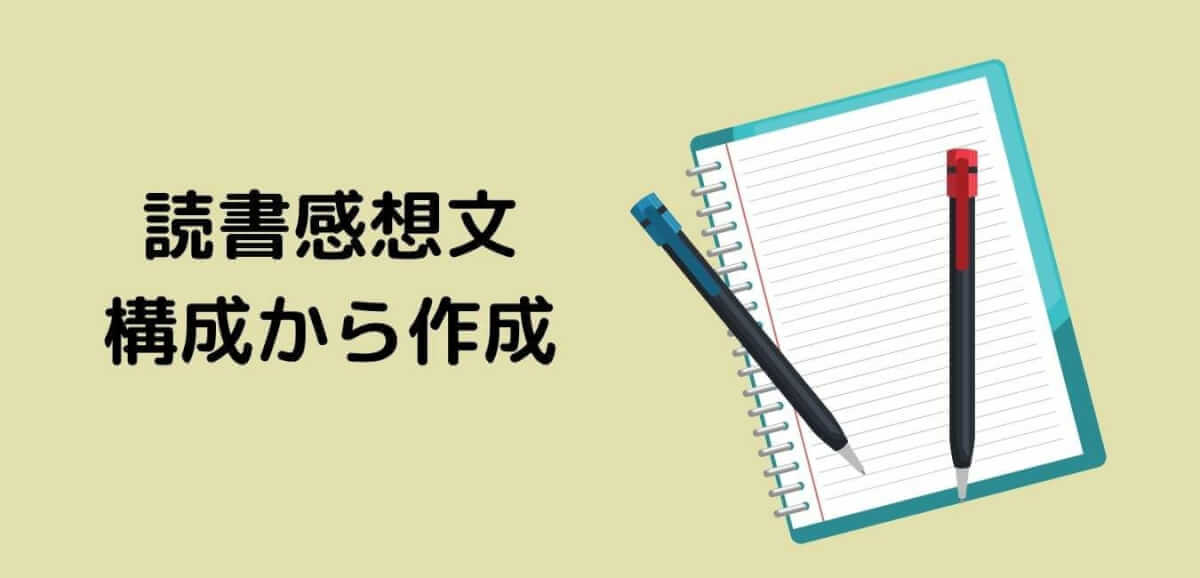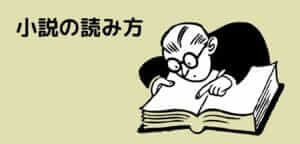読書感想文とは、読書後の個人の主観(感想)を書くものですから唯一の解答はありません。ですから、書きやすいはずですが、読書感想文の文章作成を苦手とする人が多いです。
読書感想文の作成は、小学校5年から授業として始まり、終わりは社会人まであります。社会人と聞くと、苦手な人は、がっくりときてしまうかも知れません。
企業によりますが、新卒か転職で入社し、数ヶ月経過したあたりで、読書感想文の作成を指示される企業は多いです。
社会人の読書感想文の意味は、学生の頃に比べて遥かに意味が深いし、その後の評価や昇進昇格に関係しますので、後悔しないようにきちんと書いたほうがいいです。
読書感想文は構成術:構成から始めると効果的な書き方ができる理由
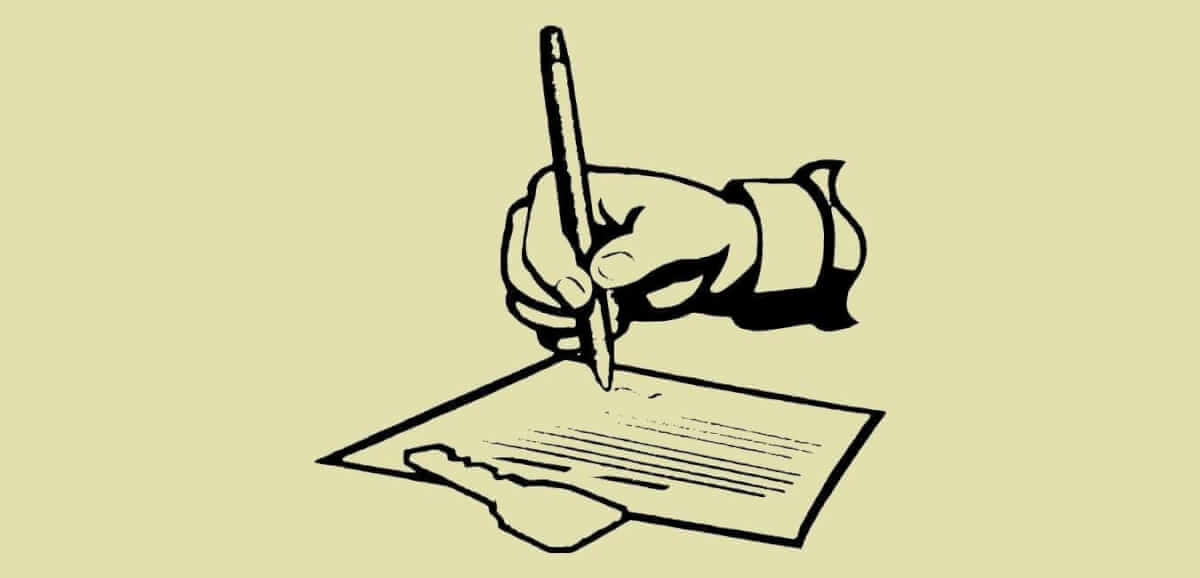
読書感想文を書くときに、白紙状態からスラスラと書ける人には、この記事は無用のものになります。
読書感想文を書くのが苦手で、いつも苦労しているという人に、ぜひお伝えしたいです。
読書感想文に限りませんが、文章や絵を書くにしても、白紙状態に一気に書き始めるのは過去に相当な練習量がなければ、早々できることではありません。
しかし、絵で言えば下書き、文章なら構成が決まっていたらどうでしょう。
構成とは、何をどういう順番で、それぞれどれくらい分量で、先に決めてしまうことです。
この下書きがしっかりと決まっていると、文章はかなり簡単に書いていけます。絵で言えば、下書きの上を、絵の具をつけた筆なぞっていくような感覚に似ています。

読書感想文の基本構成
下書きなしに絵を書いていくと、難しいのは、全体バランスが崩れてしまいやすいことです。各部分から白紙で書き始めると、想定よりも大きくなったり小さくなったりして、全体バランスがちぐはぐなおかしな絵ができてしまいます。
読書感想文も同じです。
書き上がったときに、読みやすいように、「何について、どのくらいの分量で、どういう順番で書くのか」の大枠を先に作ってしまいます。
そのことを、文章構成と言ったり、骨組みや骨子などと言ったりします。
先に骨組みから考えるということは、読書感想文に限らず、論文や小説、あるいは当記事のようなWeb記事など、文章から作られているものは、そうして作られています。(内容の順番等はそれぞれで違います)

読書感想文の基本的なパーツの紹介
読書感想文とは、読んだ本の内容や感想を文章にまとめたものです。読書感想文には、基本的に以下のパーツが必要です。
1)タイトル:読んだ本の題名と作者名を書きます。また、自分の感想文にもタイトルをつけます。
2)序論:読んだ本の概要やテーマ、自分が選んだ理由などを書きます。
3)本論:読んだ本の内容や登場人物、自分の感想や考えなどを書きます。具体的なエピソードや引用を用いて、自分の考えを裏付けます。
4)結論:読んだ本から得た教訓やメッセージ、自分の変化や学びなどを書きます。
以上が、読書感想文の基本的なパーツです。読書感想文を書くときは、これらのパーツをしっかりと組み立てて、自分の思いや考えを伝えるようにしましょう。
また相手に分かりやすい文章構成として、よく使われる方法にはプレップ法という形式があります。
プレップ法は、PREP(point(結論)・reason(理由)・example(具体例)・point(結論))という構成で、できています。
ただ、プレップ法の結論は強い主張のあることですので、読書感想文の場合は、タイトルで示したような「序文・本文・まとめ」の方が、馴染みやすいと考えます。
1)序文は、読書する前に書籍に対して持っていたイメージや知っていたこと、です。
2)本文は、読書していく中で、知ったことや感じたことを書いていきます。「あらすじ」を部分的に抽出し、関連付けるようにして、記載すると読み手は分かりやすいです。
3)まとめは、読み終わって、印象が変わったことや、感じたこと、知ったことをまとめます。
もしも、あなたが社会人で、感想文の題材がビジネス書の場合なら、プレップ法で示した構成のほうが合うかもしれません。
読書感想文のタイトルの選び方と重要性の解説
読書感想文のタイトルの選び方と重要性の解説
読書感想文は、読んだ本の内容や感想を文章にまとめるものです。読書感想文を書くときには、タイトルをどうつけるかがとても重要です。なぜなら、タイトルは読書感想文の内容やテーマを表すものであり、読者の興味を引くものだからです。タイトルを選ぶときには、以下の点に注意しましょう。
- タイトルは短くてわかりやすいものにする
- タイトルは本の内容や感想に関係があるものにする
- タイトルは自分の考えや感じたことを表現するものにする
- タイトルは他の人とかぶらないように工夫する
タイトルを選ぶことは、読書感想文を書く前の大切なステップです。タイトルを決めることで、自分が何を伝えたいかが明確になります。また、タイトルが良いと、読者も読みたくなります。読書感想文のタイトルは、自分の思いや感性を表現するチャンスです。ぜひ、工夫してみましょう。
読書の背景や簡単なストーリー紹介の方法
読書の背景や簡単なストーリー紹介の方法について、以下のポイントを参考にしてください。
- 読書の背景は、本のジャンルやテーマ、作者や出版年など、読者に興味を持ってもらえるような情報を含めると良いです。
- ストーリー紹介は、本のあらすじや登場人物、主要な出来事などを簡潔にまとめると良いです。ネタバレに注意してください。
- 背景やストーリー紹介の順番は、本の内容や目的に応じて変えることができます。例えば、ストーリーが非常にユニークで魅力的な場合は、先にストーリー紹介をしてから背景を説明することで、読者の興味を引くことができます。
- 背景やストーリー紹介の文章は、明確で分かりやすく、かつプロフェッショナルなトーンで書くことが重要です。読者に対して敬意を持ち、感情的にならずに客観的に本の内容を伝えるように心がけましょう。
読書感想文の構成|中学生の場合
読書感想文は、読んだ本について自分の考えや感想をまとめた文章です。学校の授業で課されることが多く、小学生から中学生、高校生まで幅広い学年で書く機会があります。
読書感想文を書く際には、まず本の要約をすることが大切です。要約をすることで、本の全体像を把握し、自分の意見や感想をまとめやすくなります。次に、本の中から印象に残った場面やセリフをピックアップします。印象に残った場面やセリフは、自分の意見や感想を深める材料になります。最後に、自分の意見や感想をまとめます。自分の意見や感想をまとめる際には、理由や根拠を挙げるようにしましょう。
読書感想文の構成は、大きく分けて3つです。
- 本の紹介
- 感想
- まとめ
本の紹介では、本のタイトル、著者、あらすじを簡単に紹介します。感想では、本の中から印象に残った場面やセリフ、自分の意見や感想をまとめます。まとめでは、感想をまとめ、読書感想文を締めくくります。
ここでは、それぞれの構成について詳しく説明します。
本の紹介では、本のタイトル、著者、あらすじを簡単に紹介します。本のタイトルは、本の最も重要な部分なので、必ず正しく書くようにしましょう。著者は、本を書かれた人の名前です。著者の名前も、必ず正しく書くようにしましょう。あらすじは、本の全体の流れを簡潔に説明します。あらすじを書く際には、本の要点を押さえるようにしましょう。
感想では、本の中から印象に残った場面やセリフ、自分の意見や感想をまとめます。印象に残った場面やセリフは、自分の意見や感想を深める材料になります。自分の意見や感想を書く際には、理由や根拠を挙げるようにしましょう。また、自分の言葉で書くようにしましょう。他人の文章を丸写しすると、盗作とみなされてしまいます。
まとめでは、感想をまとめ、読書感想文を締めくくります。まとめでは、本のタイトル、著者、あらすじをもう一度紹介し、自分の意見や感想をまとめます。また、読書感想文を書くきっかけや、読書感想文から得たものなどを書くこともできます。
読書感想文の書き方|中学生5枚(2000字)構成の場合
中学生では、原稿用紙5枚(2000字程度)で書くことが多いかもしれません。読書感想文を書く際の構成は、次のとおりです。
- はじめ(1枚程度・400字)
- 本の紹介(タイトル、著者、あらすじ)
- なぜこの本を選んだのか
- 本を読んだ目的
- 中(3枚程度・1200字)
- 本の感想(心に残った場面、登場人物について思ったこと、自分と比較して考えたことなど)
- 本から得たこと
- おわり(1枚程度・400字)
- 読書感想文を書いた感想
- これから自分がしたいこと
読書感想文を書く際のポイントは、次のとおりです。
- 自分の言葉で書く
- 具体的に書く
- 自分の意見を書く
- 読み手を意識して書く

読書感想文の構成|高校生が書くなら
読書感想文の書き方は、中学生と高校生、あるいは小学生についても書き方の基本には大きな違いはありません。しかし、それぞれに応じて求められる内容のレベルが違います。
中学生では、本の内容を理解し、自分の感想を簡潔に書くことが求められます。一方、高校生では、本の内容を深く理解し、自分の考えを論理的に展開することが求められます。また、高校生は、本と自分の経験を関連付けて、自分の考えを深めていくことも求められます。
具体的には、中学生が読書感想文を書く際には、次の点に注意する必要があります。
- 本の内容を理解する。
- 自分の感想を書く。
- 感想を簡潔に書く。
高校生が読書感想文を書く際には、次の点に注意する必要があります。
- 本の内容を深く理解する。
- 自分の考えを論理的に展開する。
- 本と自分の経験を関連付けて、自分の考えを深める。
「カラフル」についての読書感想文の構成
人気小説である「カラフル」を参考例として読書感想文の構成を考えてみましょう。
「カラフル」の概要やテーマの紹介
「カラフル」は、死んだ少年が「自分の罪を見つける」という条件で生まれ変わるという物語です。彼は、自殺した中学生・小野田真彦の体に入り、その家族や友人と関わりながら、自分の過去と向き合っていきます。
この作品のテーマは、人生の価値や意味、赦しや再生などです。作者は、読者に自分の人生を大切にすることや、他人の苦しみに気づくことを伝えたいと思っています。
作品の特徴や魅力の解説
小説「カラフル」は、死んだ少年が別の少年の体に生まれ変わるというファンタジーの物語です。この小説の特徴は、生まれ変わった少年が自分の過去の罪を探す過程で、人間の喜怒哀楽や葛藤を描いていることです。
また、この小説の魅力は、読者に自分自身を見つめ直すきっかけを与えるとともに、人生の色々な側面を感じさせることです。小説「カラフル」は、人間の心の奥深さや複雑さを表現した作品と言えます。
読書感想文の構成において注目すべきポイントの提案
小説「カラフル」は、死んだ魂が自殺した少年の体に入って生き直すという物語です。この小説の読書感想文を書く際に、構成において注目すべきポイントは以下のようになると考えられます。
まず、物語のテーマである「生きることの意味」や「自分探し」について、自分の考えや感想を述べることが重要です。この小説では、主人公が自分の過去や家族、友人、恋人との関係を見直しながら、自分の本当の姿や幸せを探していく過程が描かれています。
その中で、自分にとって何が大切で、何をすべきか、どう生きたいかという問いに向き合うことが求められています。読者も同じように、自分の人生について考えるきっかけになるはずです。そこで、自分はどのように感じたか、どのように考えたかを具体的なエピソードや引用を交えて書くことが望ましいです。
次に、物語の展開や登場人物の描写について、工夫や特徴を指摘することが有効です。この小説では、主人公が死んだ魂であることを隠して生活するという状況が作り出す緊張感や葛藤が見どころです。また、主人公以外の登場人物もそれぞれに個性的で魅力的であり、主人公の成長に影響を与える役割を果たしています。例えば、主人公の父親は不倫をしていたことが発覚しますが、その後の和解や反省の姿が感動的です。また、主人公の友人である佐々木は、主人公に対して厳しい言葉を投げかけるが、それは本当は心配しているからであり、最後には励ましや助言をしてくれます。このように、物語の中で起こる出来事や登場人物の言動に注目し、作者の意図やメッセージを探ってみることがおもしろいと考えられます。
「ハリー・ポッターと賢者の石」についての読書感想文の構成
もう一つ参考例として「ハリー・ポッターと賢者の石」を題材に、読書感想文の構成について考えてみましょう。
「ハリー・ポッターと賢者の石」のあらすじと舞台の紹介
「ハリー・ポッターと賢者の石」は、J.K.ローリングのファンタジー小説の第一巻です。主人公のハリー・ポッターは、11歳の誕生日に魔法使いであることを知り、ホグワーツ魔法魔術学校に入学します。そこで、友人のロン・ウィーズリーとハーマイオニー・グレンジャーと出会い、魔法の世界を探検します。しかし、ハリーは、邪悪な魔法使いヴォルデモート卿が、不死の秘密を持つ賢者の石を狙っていることを知ります。ハリーは、先生や仲間たちの助けを借りて、賢者の石を守るために奮闘します。この物語は、イギリスの現代社会と架空の魔法の世界が交錯する舞台で展開されます。
主要キャラクターの分析と個人的な感想の述べ方のアドバイス
「ハリー・ポッターと賢者の石」は、魔法の世界に住む少年ハリー・ポッターの冒険を描いたファンタジー小説です。この小説には、ハリーの友人や敵、先生や家族など、様々な個性的なキャラクターが登場します。ここでは、主要なキャラクターの分析と個人的な感想の述べ方のアドバイスを紹介します。
まず、ハリー・ポッターは、主人公であり、勇敢で正義感が強い少年です。彼は、両親を亡くして叔父夫婦に育てられましたが、魔法学校ホグワーツに入学してからは、自分の本当の家族や仲間を見つけました。彼は、自分の運命に立ち向かい、邪悪な魔法使いヴォルデモートと戦います。彼の分析では、彼の過去や性格、成長や変化などを考えることができます。彼の感想では、彼に共感したり尊敬したりする点や、彼がどうすればもっと幸せになれるかなどを述べることができます。
次に、ロン・ウィーズリーは、ハリーの親友であり、忠実で面白い少年です。彼は、魔法使いの家族に生まれましたが、貧しくて多くの兄弟がいるためにコンプレックスを抱いています。彼は、ハリーを助けたり励ましたりする一方で、時々彼と衝突したり嫉妬したりもします。彼の分析では、彼の家族や背景、友情や恋愛などを考えることができます。彼の感想では、彼が面白かったり可愛かったりする場面や、彼がどうすればもっと自信を持てるかなどを述べることができます。
最後に、ハーマイオニー・グレンジャーは、ハリーとロンの親友であり、賢くて勤勉な少女です。彼女は、魔法使いではない家族に生まれましたが、魔法学校ではトップの成績を取っています。彼女は、知識や理性を重視する一方で、友情や正義にも強くこだわります。彼女の分析では、彼女の才能や努力、信念や行動などを考えることができます。彼女の感想では、彼女に感心したり尊敬したりする点や、彼女がどうすればもっと楽しめるかなどを述べることができます。
ファンタジー要素やユーモアの活用方法の提案
「ハリー・ポッターと賢者の石」は、魔法の世界に住む少年ハリー・ポッターの冒険を描いたファンタジー小説です。この作品では、ファンタジー要素やユーモアの活用方法が巧みに使われています。例えば、魔法学校ホグワーツでは、さまざまな魔法の授業や生き物が登場し、読者の想像力を刺激します。
また、ハリーの友人ロンやハーマイオニーとのやりとりや、先生や敵との対決では、ユーモアが効果的に使われています。ユーモアは、緊張感や恐怖感を和らげたり、キャラクターの個性を際立たせたりする役割を果たしています。ファンタジー要素やユーモアの活用方法は、物語の魅力を高める重要な要素です。
読書感想文の構成作成のためのメモの取り方
構成を作成するためのメモの活用方法について解説します。
重要なポイントや感じたことをメモする方法の提案
読書感想文の構成作成のために重要なポイントや感じたことをメモする方法の提案
読書感想文を書くときには、本の内容や登場人物、テーマなどについて自分の考えや感想を述べることが求められます。しかし、どのように文章を組み立てるか、どのように感想を表現するかに悩むことも多いでしょう。そこで、読書感想文の構成作成のために重要なポイントや感じたことをメモする方法を提案します。
まず、読書感想文の構成は、一般的には以下のようになります。
1.はじめに:本のタイトルや著者、ジャンルなどを紹介し、読んだきっかけや目的を述べる。
2.本文:本のあらすじや登場人物、テーマなどを簡潔に紹介し、自分の考えや感想を具体的に述べる。引用や例示などを用いて根拠を示すことも大切。
3.おわりに:本文で述べた考えや感想をまとめ、読んでよかった点や学んだこと、感じたことなどを総括する。
次に、読書感想文の構成作成のために重要なポイントや感じたことをメモする方法ですが、以下のようなステップを踏むと良いでしょう。
1.読む前:本のタイトルや著者、ジャンルなどから興味や期待を持った点や疑問に思った点をメモする。
2.読みながら:本の内容や登場人物、テーマなどに関して気になった点や共感した点、賛成したり反対したりした点などをメモする。ページ数や章番号なども記録しておくと引用や例示がしやすくなる。
3.読み終わった後:本全体に対して感じたことや考えたことをメモする。自分の意見や感想が変わった点や深まった点も振り返る。読んだきっかけや目的が達成されたかどうかも確認する。
以上のように、読書感想文の構成作成のために重要なポイントや感じたことをメモする方法を提案しました。この方法を参考にして、自分なりの読書感想文を書いてみましょう。
メモを整理して論理的な文章にまとめる手法の解説
読書感想文を書くときには、まず本の内容や自分の感想をメモに書き出すことが大切です。しかし、メモだけでは読書感想文の構成ができません。メモを整理して論理的な文章にまとめる手法を紹介します。
メモをテーマごとに分類する。
本の内容や自分の感想に関連するテーマをいくつか決めて、メモをそれぞれのテーマに分けます。例えば、「登場人物の性格」「物語の展開」「作者のメッセージ」などがテーマになります。
テーマごとにメインの意見や感想を決める。
各テーマに対して、自分が伝えたいメインの意見や感想を一言で表します。例えば、「登場人物の性格はリアルで魅力的だった」「物語の展開は予想外でスリリングだった」「作者のメッセージは深く考えさせられた」などがメインの意見や感想になります。
メインの意見や感想を裏付ける根拠や例を挙げる。
メインの意見や感想だけでは読者に納得させることができません。メインの意見や感想を裏付ける根拠や例をメモから探して挙げます。例えば、「登場人物の性格はリアルで魅力的だった」という意見や感想を裏付ける根拠や例として、「主人公は自分の夢を追いかける勇気があった」「脇役は主人公を支える友情があった」などが挙げられます。
テーマごとに文章にまとめる。
メインの意見や感想、根拠や例を使って、テーマごとに文章にまとめます。文章は簡潔でわかりやすく、論理的につながるように書きます。例えば、「登場人物の性格はリアルで魅力的だった」というテーマに対して、「この本では、自分の夢を追いかける勇気がある主人公や、主人公を支える友情がある脇役など、リアルで魅力的な登場人物が描かれています。私は、登場人物たちの感情や行動に共感したり驚いたりしながら読みました」という文章が作れます。
まとめを書く。
最後に、全体のまとめを書きます。まとめでは、自分が読んだ本のタイトルや作者名を明記し、本全体に対する自分の評価や感想を述べます。また、読んでよかった点や学んだこと、読んだ後にしたいことなども書くとより良いです。
以上が、読書感想文の構成作成のためにメモを整理して論理的な文章にまとめる手法です。この手法を使えば、読書感想文を書くのが楽になると思います。ぜひ試してみてください。
大学生向け読書感想文の構成
大学生に適した読書感想文のアプローチの紹介
読書感想文とは、読んだ本の内容や感想を文章にまとめるものです。大学生になると、読書感想文の書き方も高校生や中学生とは異なります。大学生の読書感想文では、以下の点に注意する必要があります。
- 本の内容を要約するだけではなく、自分の考えや感想をしっかりと述べること。
- 本のテーマやメッセージを理解し、それに対する自分の見解や評価を示すこと。
- 本の著者や背景について調べ、その知識を読書感想文に反映させること。
- 他の本や文献と比較し、本の特徴や価値を分析すること。
- 読書感想文自体にも構成や論理性があること。序論・本論・結論の三部構成に従い、自分の主張を明確に伝えること。
以上の点を踏まえて、大学生に適した読書感想文のアプローチを紹介します。
文学理論や批評の手法の活用方法の提案
読書感想文は、読んだ本に対する自分の感想や考えを述べる文章です。しかし、感想だけではなく、文学理論や批評の手法を活用することで、より深く本の内容やテーマを分析したり、自分の主張を根拠付けたりすることができます。文学理論や批評の手法は、さまざまなものがありますが、ここでは代表的なものをいくつか紹介します。
まず、文学理論とは、文学作品を理解するための視点や方法論です。例えば、古典文学を読むときには、その時代や社会の背景や文化を知ることが重要です。また、現代文学を読むときには、作者の生い立ちや思想、作品に影響した他の作家や作品などを調べることが有効です。さらに、作品のジャンルや形式によっても、適切な文学理論が異なります。例えば、小説を読むときには、登場人物や設定、プロット、視点などの要素を分析することができます。詩を読むときには、韻律や比喩、象徴などの言語表現を注目することができます。戯曲を読むときには、台詞や演出、舞台装置などの劇的要素を考慮することができます。
次に、批評の手法とは、文学作品に対する評価や解釈を行うためのアプローチです。例えば、主観的な批評とは、自分の感情や印象に基づいて作品を評価することです。客観的な批評とは、作品の内容や形式に基づいて作品を評価することです。比較的な批評とは、他の作品や作者と比較して作品を評価することです。社会的な批評とは、作品が社会に与えた影響や反映した問題などを考察することです。
以上のように、文学理論や批評の手法は多様であり、それぞれに特徴や利点があります。読書感想文の構成においては、自分が読んだ本に合った文学理論や批評の手法を選択し、それらを適切に活用することで、より高度な文章を書くことができます。
読書感想文の構成|社会人
先にいいますと、読書感想文の構成は、社会人と学生で大きく違うものではありません。
また、当記事で紹介した構成で書かねば評価されないということでもありません。
ただ一つの点について、注意して読書感想文を書くことをおすすめします。それは、読み手が読みやすく分かりやすい感想文であることです。
当記事のタイトルは、読書感想文を書きやすくする文章構成としていますが、実は、整理された文章構成でまとめられている文章は、読み手にとっても読みやすいものです。
感想文の内容が分かりやすいかどうかは、書き手の言葉選びにかかってきます。あまりに稚拙な表現は、評価を落とす原因になりますが、言葉の意味を理解せずに、背伸びをして間違えた使い方をするよりも、平易な表現のほうが、読み手にはわかり易い文章と思われるはずです。

まとめ
読書感想文は、学生の場合は、教育の一環として行われると思いますが、社会人の場合はシビアです。はっきりいえば、能力判定の1つであり、その後の評価・昇進昇格にも影響します。(重要度合いは企業によります)
企業にとっても社員にとっても忙しい時間の中で行うには、それなりの理由があります。その後の評価や昇進昇格のときに、後悔することになります。もし、あなたが社会人でしたら、本気で取り組んで提出しておいたほうが、将来の「得」に繋がります。
また学生にとっては、読書感想文を書くことは面倒な課題だと認識する人が多いかもしれません。しかし他の課題のように唯一の答えを見つけるものではないことに注目してください。書き方によって、必ずプラスの評価になるということです。
関連記事一覧
読書感想文は構成術:構成から始めると効果的な書き方ができる理由*本記事