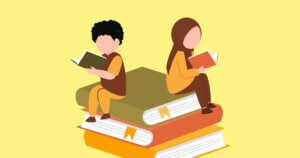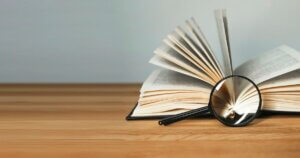本や文章を読む方法には、さまざまな方法があります。本を読む方法の大きな違いには、声に出さずに読むか声に出して読むかがあります。
当記事では、声に出して読む「朗読」について解説しています。朗読は音読と同様に声に出して読む方法です。
声に出して読む方法という点においては、朗読と音読の他に、素読という方法もあります。どの読み方が良い方法なのかと考えてしまう方もいるかも知れません。しかし、どの読み方が優れているということではなく、本や文章を読む上で、何を目的にするのかによって、どの読み方が最適であるという考え方ができます。朗読との違いは何か、関心がある方に、当記事はおすすめです。
朗読は単純に、本や文章の読み方が上手くなるだけではなく、読み聞かせるのが上手になります。
その違いがどこにあるのか、また朗読と音読の効果の違いには何があるのかについて、紹介いたします。
朗読とは何か?感動を伝える10のコツと練習方法
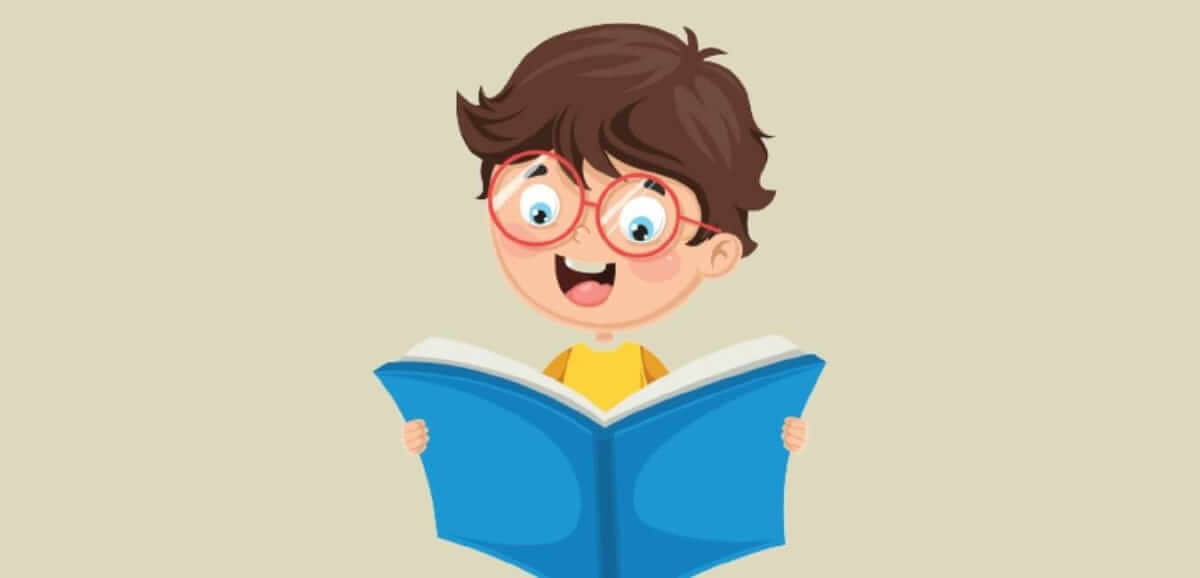
「朗読」を辞書で引くと、概ね次のように説明されています。
朗読と何か?朗読の意味と目的
朗読とは、声を出して文章を読む読み方のことです。
朗読の意味
言葉や文章を音声として表現することによって、聞く人に情景や感情を伝えたり、作品や文章の意図を理解しやすくする役割を果たします。
朗読は、文学作品や詩、物語、演劇の台本、スピーチなど、さまざまなテキストを対象として行われます。朗読を行う人は、声のトーン、リズム、テンポ、表情などを使って、聞く人に作品の世界やメッセージを鮮やかに伝えることを目指します。
発声する他の読み方とは違い、朗読は誰かに聞かせるために、声高く感情をくみ取り、趣があるように感情を込めて読み上げることでもあります。
朗読の目的
朗読の目的は、文学作品や詩、スピーチなどの文章を音声で表現し、聞く人に感動や共感を与えることです。以下に朗読の目的をいくつか挙げます。
1)文学作品や詩の鑑賞と理解を深める
朗読は、テキストを音声で表現することで、聞く人により深い鑑賞体験を提供します。声のトーンや表情を通じて、作品の感情やニュアンスを伝えることができます。
2)感情や思いを共有する
朗読は、作者が込めた感情や思いを聞く人に直接伝える手段です。声の表現やリズムを使って、作品のメッセージやテーマをより深く理解し、共感することができます。
3)聴衆に感動や喜びを与える
朗読は、聞く人の心に感動や喜びを引き起こす力があります。声のトーンや表現を使って情景やキャラクターを生き生きと描写することで、聴衆の感情を揺さぶり、深い印象を与えることができます。
4)コミュニケーションや伝達手段として活用する
朗読は、スピーチやプレゼンテーションなどの場で効果的なコミュニケーションツールとしても利用されます。声の使い方や表情を工夫することで、聞く相手に自分の意図やメッセージを明確に伝えることができます。
朗読の目的は、文学や言葉の力を最大限に引き出し、聴衆に感動や共感を与えることです。それによって、作品やメッセージがより深く理解され、心に響く体験が生まれるのです。
朗読と音読の違い|相手がいるかどうかにある
朗読と同じように、声に出して読む読み方に、「音読」「素読」があります。
「音読」は、声に出して読むことで、自分の脳が刺激され、脳への定着率が一時的に高まるなどの効果があります。個人的な学習の場面でも使われる方法です。子供の頃には音読をしていて、次第に黙読するようになります。しかし大人になっても音読には脳を刺激する効果が認められますので、日常的に音読をすることは脳に良い刺激を与える方法と言えます。
また「素読」とは、言葉や文章の意味にとらわれずに声に出して読む方法です。音読に似ていますが、素読のポイントは意味がわからない言葉があったとしても読み進めることに集中することにあります。文章の内容の理解は後回しであり、脳が活性化されることが目的です。江戸時代の寺子屋で論語の素読が行われていたことは、よく知られています。
そして「朗読」もまた、声に出して文章を読む方法の一つです。違いがあるのは、人に聞かせるために感情をくみ取り、感情を込めて読み上げる方法です。必ずしも、読み聞かせる相手が目の前にいるとは限りませんが、相手がいることが朗読の絶対条件です。当然文章の内容を理解していることが必要になります。内容に応じて感情を表現するなどして、説得力を持って読み上げていくものです。
つまり朗読と音読の違いは、読み聞かせる相手がいるのかどうかが大きな違いとなります。表面的には、音読は単に文字を読み発生する方法となります。朗読は誰かに伝えるように読む方法ですので、表現する技術や演出的な表現をする要素が強くなります。
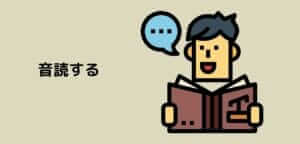

朗読で感動を伝える10のコツ
朗読は、音読に感情をプラスして読むことと考えると、日頃から本を読んでいる方なら、方法として簡単にできそうです。
しかし、試しに朗読してみるとわかりますが、自分が正しく発音ができているのか、イントネーションはおかしくないか、などと注意し始めると、どんどん朗読の難しさを実感することになります。自分自身の理解ではなく、相手に伝えることを目的とする読み方だからです。
事実、番組のナレーションをプロの方が話しているのを聞いてみると、やはりプロはまるで違うことを思い知らされます。感動を伝えるためのコツとテクニックには次10のポイントがあります。
1)テキストの理解と感情の把握
朗読をする前に、読み上げるテキストをよく理解し、その中に込められた感情や意図を把握することが重要です。文学作品や詩の場合は、作者の意図や背景を調べることで理解が深まります。
2)声のトーンとリズムの変化
声のトーンやリズムの変化を使って、テキストの感情や情景を表現します。喜びや悲しみ、緊張など、テキストの要素に合わせて声の抑揚や速度を変化させることで、聴く人に感情を伝えることができます。
3)ポーズと間の使い方
朗読中にポーズや間をうまく使うことで、効果的な表現が可能です。重要な言葉やフレーズの前後で一瞬の静寂を作ることで、効果的な強調や緊張感を演出することができます。
4)表情の活用
朗読は声だけでなく、表情も重要な要素です。顔の表情や目の動きを使って、テキストの情景やキャラクターを表現します。表情によって感情や意図を補完し、聴く人により深い印象を与えることができます。
5)ダイナミックな演技
朗読は、モノトーンにならないように注意が必要です。声の音量や強弱を使ってダイナミックな演技を行うことで、聴く人の興味を引きつけます。状況や感情の変化に応じて、声のパフォーマンスを調整しましょう。
6)練習とフィードバックの活用
朗読は練習が重要です。テキストを何度も読み、声のトーンや表現方法を試してみましょう。また、録音して自己評価を行ったり、他の人からフィードバックをもらったりすることで、自身の朗読スキルを向上させることができます。
7)聴衆とのコミュニケーション
朗読は聴衆とのコミュニケーションの場でもあります。聴衆の反応や反応を感じ取りながら、声の表現やペースを調整することが重要です。聴衆の関心を引きつけるために、適切なタイミングで目線を使ったり、微笑んだり、聞く人に寄り添うような姿勢を持つことも大切です。
8)イマジネーションの活用
朗読は、テキストを聞く人に鮮明にイメージさせる力があります。自身がテキストの世界に没入し、イマジネーションを駆使して情景やキャラクターを描き出すことで、聴く人にもその世界を共有させることができます。
9)積極的な感情の表現
感動を伝えるためには、自身が感情を込めて朗読することが重要です。自然で本物の感情を表現することで、聴く人の心に共鳴し、感動を引き起こすことができます。
10)緊張をコントロールする
朗読はパフォーマンスの一つであり、緊張がつきものです。練習やリラックスのテクニックを使いながら、緊張をコントロールしましょう。自信を持って朗読に臨むことで、自然な表現ができます。
朗読で声のトーンや表情の使い方と効果
朗読を行う効果には、話し方が上手になるということがあります。朗読を行うことで身についた使い方は仕事に活かせるようになります。
営業や販売の人は、普段から商談や商品説明などで、話す機会は非常に多いです。しかし、自分自身の話し方チェックをしている業種や企業は実際には限られており、自分自身の滑舌が悪いことに気づいていないままに、一生懸命に話している方は、意外に少なくありません。
決められたシナリオの中だけで、ロープレという練習をしている企業もありますが、自分自身を客観的に評価できる仕組みで、練習することをお勧めします。
朗読による声のトーンや表情の使い方
朗読をする際に文章に合わせて声のトーンや表情を変えることは、聞く人に内容や感情を伝えるためにとても重要です。声のトーンとは、高さや強さ、速さで変えることができます。
文章によって、明るさや悲しみや切なさを伝わるようの声の表情を変えることも効果的です。テンポを早く話したりゆっくり話すことでも感情の重みや深さも表現することができます。
文章の内容に応じて、単に声に出して読だけではなく、朗読では声のトーンや表情に意識を置いて、相手に感情を伝えることができます。
朗読の効果を仕事に活かす
話をすることが仕事に必須である人は、一人で朗読する方法を毎日少しずつでも繰り返していることで、自分の滑舌の良さ悪さがわかったり、聞きやすい声が発見できることがあります。
決められたシナリオの中で、うまく話せるようになっている気がしていても、実際の場面では想定外の商品説明や顧客とのコミュニケーションが発生することがあります。ですので、普段から、朗読による話し方のトレーニングをしていることが、生かされます。
・滑舌が悪く相手に聞き返されるという経験がなくなる
・発音が明瞭になることで、人柄の見られかたが変わる
・話すことに自信が持てるようになり、人前で話すことに過剰に緊張しなくなる
・顧客や上司に伝えたいことが伝わりやすくなり評価や成果があがりやすくなる
朗読の練習方法
お勧めする朗読の練習方法は、一人朗読です。スマホのボイスレコーダーアプリを利用して録音する方法です。ただし朗読は前述したとおり、単に声に出して読むだけの方法ではありません。内容を理解した上で相手に伝えるための演出や表現が必要になります。
まずは次に紹介する朗読のコツに意識を置いて練習してみてください。
1)抑揚のつけ過ぎに注意する。感情を込めようと意識しすぎると、やり過ぎてしまい、聴きにくい朗読になります。
2)一音一音を丁寧に発音する。特に、語尾が流れたり、声が小さくなる癖がある人は注意しましょう。
3)音読との違いの意識が薄くなると、早口になる可能性がありますので、注意です。
4)句読点(、。)は、原則はあけて発生するが、やりすぎると、間伸びして聞こえるので、文章の流れに沿って、調整して読む。
5)呼吸は腹式呼吸を意識する。胸式だと、呼吸が浅くなって、長文が続かなくなる可能性があります。
6)そばに水を置くことを忘れずに。喉が乾いてしまうと、良い音声が発生できなくなってしまいます。
朗読の練習には文章内容を深く理解する必要がある
朗読の練習は、文章内容を深く理解することが欠かせません。なぜなら、深い理解がなければ、適切な抑揚や感情を込めて文章を表現することが難しくなるからです。
まず、文章を理解するためには、単語やフレーズの意味を把握することが必要です。辞書を頼りに知らない言葉の意味を調べ、文脈を考慮してどのように使われているのかを理解しましょう。
次に、文章全体の構造を把握します。文章は導入、展開、結論といった要素から構成されています。それぞれの部分がどのようにつながり、物語や議論が進行しているのかを把握しましょう。
さらに、文章の背後にある感情や意図を読み取ることも大切です。著者が何を伝えたいのか、どのような情熱やメッセージを持っているのかを考えることで、朗読がより生き生きとしたものになります。
最後に、声の抑揚やリズムを文章に合わせて調整しましょう。文章の内容や感情に応じて声のトーンを変えることで、聴衆に伝えたいメッセージがより魅力的に届きます。
要するに、朗読は単なる文章の音読ではなく、文章の奥深い意味や感情を表現する芸術です。そのためには、文章内容を深く理解し、その理解を声で表現できるようにすることが不可欠です。
朗読練習には台本やテキストが重要
朗読練習において、適切な台本の選択は非常に重要です。良い台本を選ぶことで、朗読技術の向上が効果的に進むでしょう。
まず、初心者の場合は簡単な台本から始めることをおすすめします。難解な文章や複雑なストーリーではなく、理解しやすく、自分に合った内容のものを選びましょう。
また、興味を持てるテーマやジャンルの台本を選ぶことで、練習へのモチベーションが高まります。自分が興味を持っている内容なら、練習が楽しみに感じられるでしょう。
台本選びの際には、文章のリズムや抑揚が魅力的なものを選ぶことも大切です。これにより、声の表現力を向上させるのに役立ちます。
さらに、台本に感情やキャラクターの多様性があると、様々な朗読スタイルを試す機会が増えます。これは成長に繋がる要素です。
最後に、台本の長さにも注意しましょう。初めは短い台本から始め、徐々に長いものに挑戦すると、コツコツとスキルが向上します。
練習台本の選択は、朗読の上達に直結する要因です。自分に合った台本を選び、楽しみながら練習を進めましょう。
朗読の練習にはボイスレコーダーやアプリを使う
朗読の練習を効果的に行うために、ボイスレコーダーや専用アプリを活用することは非常に役立ちます。
ボイスレコーダーを使う場合、自分の声を録音し、再生することで、自己評価が可能です。声の抑揚やリズム、発音に注意を払い、自己改善の手がかりを見つけましょう。また、録音した声を後から聞くことで、客観的な評価を得ることができ、進歩が実感できます。
専用アプリも多く存在し、朗読の練習をサポートしてくれます。これらのアプリは、テキストを読み上げてくれたり、発音の正確さを評価してくれたりする機能を備えています。アプリを通じて繰り返し練習することで、自分の朗読スキルを向上させることができます。
さらに、アプリは様々なテキストやジャンルの朗読練習用のコンテンツを提供しており、幅広い経験を積む機会を提供してくれます。興味のあるテーマや難易度に合わせてコンテンツを選び、効果的な練習が可能です。
ボイスレコーダーやアプリを活用することで、朗読のスキル向上が加速します。自己評価やフィードバックを得ながら、自信を持って美しい朗読を楽しむことができるでしょう。
朗読練習におすすめなのは発声練習と滑舌練習で文章を読むこと
朗読練習において、発声練習と滑舌練習は非常に効果的です。これらの要素を組み合わせて文章を読むことで、朗読スキルの向上が期待できます。
まず、発声練習は声をクリアで魅力的にするために欠かせません。発声練習では、口の形や舌の位置に注意を払い、音を正確に出すことが求められます。発音の改善には、単語や音の練習から始め、次第に文や段落を読むように進めましょう。
滑舌練習は、言葉を滑らかに、正確に発音するための重要な要素です。舌の運動や口の動きをトレーニングし、言葉が混ざらずにクリアに聞こえるようにしましょう。早口言葉を使ったり、特定の音の練習を行ったりすることで、滑舌を向上させます。
そして、これらの練習を文章を読む中で組み込むことが大切です。適切なテキストを選び、発声と滑舌のポイントに注意しながら読み上げましょう。定期的な練習を通じて、朗読におけるスムーズな音声表現を身につけ、聴衆に響く朗読力を向上させることができます。
要するに、発声練習と滑舌練習は、朗読の基盤を築くための不可欠なステップです。文章を読みながらこれらのスキルを養い、自信を持って美しい朗読を楽しむことができるでしょう。
朗読練習では短文でもむしろ有益
朗読練習において、短文は非常に有用です。短文は以下の点で朗読練習に適しています:
- 手軽なスタート: 短文は長文に比べて読むのが簡単で、初心者にとって手軽なスタート地点です。長文を一気に読むよりも、短文から始めて徐々にスキルを積み重ねることができます。
- 集中力の向上: 短文は短時間で読むことができるため、短い時間でも効果的な練習が可能です。これにより、集中力を高め、文章全体を注意深く読む習慣を養うことができます。
- 発音と滑舌のトレーニング: 短文は発音や滑舌のトレーニングに適しています。単語やフレーズの正確な発音や滑舌を短い文で練習することで、基本的なスキルを向上させることができます。
- 即時のフィードバック: 短文を読み終えた後、すぐに録音を再生して自己評価ができます。この即時のフィードバックを通じて、改善点を素早く見つけ、修正できます。
- 表現力の向上: 短文を読むことで、感情や抑揚を効果的に表現する練習ができます。短い文の中で、感情を込めて読むことで、表現力が向上します。
練習には、新聞記事、短編小説、格言、名言など、さまざまな短文を利用できます。短文を選んで、定期的に朗読練習を行うことで、朗読スキルの向上を実感できるでしょう。
朗読検定を目指してみる
今の時代は、仕事やコミュニケーションにおいてテキストによる伝達する場面が増加し、従前よりもはるかに文章力が重視されるようになりました。
しかし実際の声によるコミュニケーション力は、テキストだけでは伝わりにくい雰囲気や感覚を伝えることができます。朗読をする練習を重ねることで、前述のように様々なシーンで、好転するようになります。
朗読の練習をし朗読検定を目指していくことで、さらに自信が高まるようになります。一般社団法人 日本朗読検定協会では朗読検定1級のハイレベルな表現力の認定から、初級レベルの4級までの6段階(1級・準1級・2級・準2級・3級・4級)のレベルを目指すことができます。
必ずしも上級レベルに合格せずとも、話すことへの自信や仕事や生活への好影響が期待できるようになります。
まとめ
本や文章を読むときに、声に出して読む音読と当記事で紹介した朗読は同じように声に出して読む方法です。
音読はあくまでも読むことに目的がありますが、朗読は話し方に重点があります。ですので、朗読を何度も繰り返していくうちに、滑舌が良くなり、話し方が聞きやすくなり、話すことを仕事とする方によっては、スキルアップになる読み方です。


関連記事一覧
朗読とは何か?感動を伝える10のコツと練習方法*本記事