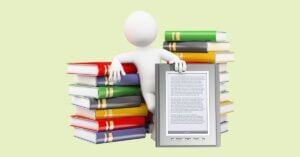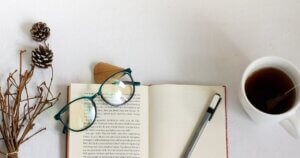本は、一般的に知識や情報を得たり、物語を楽しむために読まれます。しかし一方では、本の読み方がわからないという人は意外に多くいます。
本を手に取った時に、どのように読めばいいのか迷ったり、文章が難しく感じたり、集中力を保つことが難しかったりするのかもしれません。
本記事では、本の読み方を解説し、本を読むことが苦手な人でも、効果的に読むための方法を紹介します。本を読むことは、知識や洞察力を向上させ、自己アップグレードにつながります。また、読書はストレス軽減や創造性を高めるなど、多くのメリットがあります。
本の読み方がわからない人|これで解決!

本の読み方がわからない・本を読めないという悩みを持つ人は、意外に多いのかもしれません。
日本は外国と比べても本を読まない人の割合が多い国です。一般的に読書の経験が少ない人やない人が多いので、社会人となって本を読む必要性に迫られた時に、「本の読み方がわからない」という状態になるのです。
当記事では、本の読み方がわからない人が感じる悩みや本の読み方を改善するためのコツ、本の読解力を上げるために意識すべきポイントなどを紹介します。
本の読み方がわからない人の原因は何か
本の読み方がわからない人が多いですが、その原因は様々です。以下にいくつかの原因を挙げてみました。
1)読み方が教えられていない
学校教育で本の読み方を教えられなかった人は、本の読み方がわからないことがあります。
2)読み方に自信がない
本の読み方がわからない人の中には、自分が正しい読み方を知らないと思い込んでいる人がいます。そのため、本を読むことができなくなってしまいます。
3)読み方が難しい本を読んでいる
本の種類によっては、読み方が難しいものもあります。例えば、学術書や哲学書などは、読み方が難しく、専門的な単語が多いため、読むのが難しいと感じる人が多いです。
4)日本語が苦手である
日本語が母国語でない人は、読み方がわからないことがあります。日本語の文法や表現方法が違うため、読むのが難しいと感じることがあります。
以上が、本の読み方がわからない人の原因の一部です。本の読み方を身につけるためには、まずは基本的な読み方を学ぶことが大切です。
本の読み方がわからない人は苦手だと感じている
本本の読み方がわからない人は苦手だと感じているというのは、本の中に隠された意味やメッセージを見つけることができないからかもしれません。
本を読むときには、単に文字や文章を追うだけではなく、作者の背景や目的、登場人物の感情や動機、物語の展開や結末などにも注意を払う必要があります。そうすることで、本の深層にあるテーマや考え方を理解することができます。本の読み方がわからない人は、本を読むことに楽しみや興味を感じず、退屈や苦痛になることが多いでしょう。
しかし、本の読み方を学ぶことで、本の魅力や価値に気づくことができるかもしれません。本の読み方を学ぶ方法はいろいろありますが、一つの例としては、本を読んだ後に感想や質問を書いたり、他の人と話したりすることです。
そうすることで、自分の考えや感じ方を整理したり、他の視点や解釈を知ったりすることができます。本の読み方がわからない人は苦手だと感じているかもしれませんが、本の読み方を学ぶことで、本に対する態度や関係が変わる可能性があります。

本の読み方がわからない人は集中力が続かないのかも
本の読み方がわからない人は集中力が続かないのかもしれません。
本を読むときには、目的や興味に合わせて選ぶことが大切です。また、読む環境や時間も工夫する必要があります。読む環境は静かで快適なものにしましょう。
音楽やテレビなどの雑音は集中力を妨げます。読む時間は自分の体調や気分に合わせて決めましょう。朝や昼間は頭がすっきりしているので、難しい本や勉強に向いています。夜はリラックスしたいので、軽い本や趣味に関する本がおすすめです。
本を読むことは知識や想像力を豊かにするだけでなく、ストレス解消や睡眠改善にも効果的です。本の読み方がわからない人は、自分に合った本を探してみましょう。
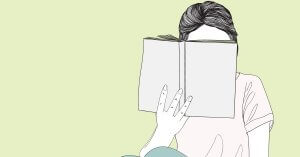
本の読み方がわからない人は言葉の意味や漢字の意味がわからないのかも
本を読むときには単に文字を追うだけではなく、文章の構造や文脈、作者の意図や視点などを理解する必要があります。本を読むということは、言葉を通して他者とコミュニケーションをするということです。
そのためには、言葉の意味だけでなく、言葉が使われている状況や背景、目的や感情などを考えることが大切です。漢字の意味も同様に、単に音や形だけでなく、その由来や構成や関連する言葉などを知ることで、より深く理解することができます。
本の読み方がわからない人は、言葉や漢字に対する興味や好奇心が足りないのかもしれません。本を読むことは、自分の世界を広げることでもあります。本を読むことで、知らなかったことや感じたことがなかったことに出会うことができます。
そのためには、本を読む前に自分が何を知りたいかや何を感じたいかを考えることも有効です。本の読み方がわからない人は、本を読む目的や楽しみ方を見つけることができれば、言葉の意味や漢字の意味も自然に身につくかもしれません。

本の読み方がわからない人は本を読む理由がわからない
本の読み方がわからない人は本を読む理由がわからないというのは、本の価値や魅力を感じられないということです。本は、知識や情報、感動や楽しみ、発想や創造力を与えてくれる素晴らしいものです。
しかし、本を読むには、本の内容や構成、文体や表現に注意を払い、自分の頭で考えたり感じたりしなければなりません。本を読むことは、単に文字を追うだけではなく、本と対話することです。そのためには、本の読み方を学ぶ必要があります。

さらに読書をすること自体が脳を刺激し、たくさん読むことで脳が活性化し頭の回転が速くなることも分かっています。
また社会に出てから評価を受けるのは学歴のある人ではなく、読書量が多い人です。本を読む理由は十分にあります。

本の読み方がわからないのは目的が決まっていないから
本を読むときには、なぜその本を読むのか、どんなことを学びたいのか、どうやって読むのかという目的が必要です。
目的が決まっていないと、本を読んでも内容が頭に入らなかったり、興味が持てなかったり、途中で飽きてしまったりすることがあります。目的がはっきりしていれば、本を選ぶときにも自分に合った本を見つけやすくなりますし、読むときにも重点的に読むべき部分や理解するべきポイントが明確になります。
また、目的に応じて読み方も変えることができます。例えば、本の概要や大事なメッセージを知りたいだけなら、速読やスキャニングという方法で本をざっと読むことができます。一方、本の詳細や論理展開を深く理解したいなら、精読やサマリー作成という方法で本をじっくり読むことができます。このように、目的に合わせて本の読み方を変えることで、効率的に本から知識や情報を得ることができます。
本の読み方がわからない人|解決法の一つは本の選び方
本の読み方に悩む方にとって、本の選び方は重要な一歩です。目的に合わせた本を選ぶことで、読書体験がより充実し、理解を深めることができます。以下に、具体的な本の選び方のポイントをご紹介します。
興味や関心のあるテーマを選ぶ
自分が本当に興味を持つテーマや関心のある分野の本を選びましょう。自分自身がワクワクしたり、学びたいと思えるテーマであれば、読書への意欲も高まります。
レビューや評価を参考にする
他の人の評価やレビューをチェックして、信頼性のある本を選ぶことも大切です。オンライン書店や読書コミュニティなどで、他の読者の意見を参考にしてみましょう。
本の概要や目次を確認する
本の概要や目次をチェックすることで、内容や構成が自分に合っているか判断することができます。本の内容や章立てが自分の学びたいポイントに沿っているかを確認しましょう。
自分の読書レベルに合った本を選ぶ
自分の読書レベルに合った本を選ぶことも重要です。初心者向けの入門書から始めることで、理解しやすくなります。少しずつ難易度を上げていくことで、読書スキルも向上します。
フォーマットや媒体を選ぶ
書籍だけでなく、電子書籍やオーディオブックといった異なるフォーマットや媒体も利用することで、自分に合った読書体験を追求できます。自分のライフスタイルや好みに合わせて選びましょう。
本の読み方がわからない人は概要を把握することから始める
本の読み方に悩む方にとって、本の概要を把握することは非常に重要です。概要を把握することで、本の内容や流れを理解しやすくなり、効率的な読書を実現することができます。以下に、具体的な本の概要の把握方法をご紹介します。
カバーや裏表紙をチェックする
本のカバーや裏表紙には、本の要点や内容の要約が記載されています。タイトルやサブタイトル、キャッチフレーズを読んで、本の大まかな内容を把握しましょう。
目次や章立てを確認する
本の目次や章立てを見ることで、本の構成や章ごとのトピックが分かります。各章のタイトルやサマリーを読んで、本の流れや重要なポイントを把握しましょう。
章の冒頭と結論を読む
各章の冒頭や結論部分を読むことで、その章の主題や結論が分かります。この部分を読むことで、本の要点をつかむことができます。
段落や箇条書きを活用する
本の中の段落や箇条書きを活用することで、重要なポイントや情報を素早く把握することができます。見出しやハイライトされた箇所に注目し、本の主題や要点を把握しましょう。
本の概要を把握するための具体的な手法やツール
本の概要を把握するには要約サイトや書評サイトを利用する方法が有効です。
インターネット上には、本の概要や要約をまとめたサマリーサイトや書評サイトがあります。例えば、「ブクログ」や「読書メーター」などの読書記録サイトや、「flier(フライヤー)」などの本の要約サイトを利用して、他の人の要約や評価を参考にすることができます。


本の読み方がわからない人|本の読み方を改善するためのコツ
本の読み方がわからない人や読書経験が少ない人は、読書することは知識や情報を得るためだけに読むものだと思っています。しかし本を読むことには、知識を得るだけでなく、ストレスを解消したり、脳を活性化するなどの効果があることもわかっています。
本の読み方がわからないからと、読まずにいるリスクを考え、本の読み方を改善するためのコツを紹介します。
本の読み方の改善のコツ|本を読む目的を明確にする
本を読む前に、何を得たいのか、何を学びたいのかを明確にしましょう。
本を読む目的を明確にすることによって、本の内容をより効果的に吸収できます。たとえば、本を読む目的が英語の勉強であれば、その本に出てくる単語や表現を重点的にメモしたり、繰り返し読んで覚えたりすることができます。

読み方の改善のコツ|本を読む前に目次から読みたいところを見つける
仕事に関係する全般的な知識をつけたいということもありますし、具体的な問題や課題があってヒントをつかみたくて読書をする場合もあります。あるいは本のエッセンスだけを読みたいということもあります。
本を目の前にして、この本から「何々についての知識を得る」という明確な目的がある場合は、目次から読むべき部分を見つける方法がおすすめです。目次の中から、今日の自分が読むべきページを特定するのです。
もし選んだページを読んで、関連する別のページを読む必要があると感じれば、そのページも追加して読む方法です。
また本のエッセンスだけを読みたいという場合もおすすめです。目次から探して、読みたいページだけを読むのです。ただし特にビジネス書の場合、「一度読んでお終い」ということはありません。進化成長した数ヶ月後(数年後)の自分が同じ方法で目次を見ると別のページに興味が湧く可能性もあります。
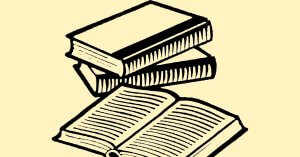
本の読み方の改善のコツ|メモをとる
読書ノートやメモを取りましょう。重要な箇所をメモすることで、後で復習しやすくなります。また、自分が感じたことや意見を書き込むことも有効です。メモをとる際には、簡潔にまとめる意識で行うことです。
本を読むことは、復習することで記憶が脳に定着しやすくなります。ただ単に本を読むだけでは、記憶からどんどん忘れてしまうことがわかっています。復習をしなければ、せっかく読んだ本の内容を忘れてしまいます。
読解力をつけるなら精読を3回繰り返す|文章を読む脳トレ
知識を得るのも大事だが、読書経験がないので読解力がないという人は同じ本を3回読んでください。本の読み方は前述の方法ではなく精読で読みましょう。精読とは全文を意味を考えながら読む方法です。
読書に価値を感じずにあまり読んでこなかった人は、読書が脳トレになることを知らない人も多いでしょう。しかし文章を読むこと、可能なら声を出してなるべく早く読む方法で、精読を3回繰り返す方法がおすすめです。
本の内容の理解も進みますが、前頭前野が刺激されて、記憶力・集中力も高まります。読書が脳を活性化することは実証されています。(東北大学の川島隆太教授)頭の回転が速くなると言います。

先に要約を読んで良い本を選んでから本を読むのは有益|無駄もなくなる
1年間に出版される本は毎年7万冊以上あります。作者や出版社には大変失礼ながら、全ての本が有益とは言い切れません。本を読んでる途中で、すでに知っていることしか書かれていないとわかることもあります。
タイトルは新しめなのに、過去に出版された本の知識情報を寄せ集めて、1冊に編集し直したような本もたくさんあります。そんな時におすすめするのは、先に要約を読む方法です。おすすめするのはFlier(フライヤー)です。
他にも要約のサービスを展開しているサイトやアプリがありますが、月ごとの利用ができるのがフライヤーの特徴です。初めての利用なら7日間無料でお試しすることもできます。
要約を読んで良い本を選んでから、改めて本を購入して読むと、時間とお金の無駄がなくなりますし、事前情報があってから原本を読むことは復習効果もあって理解もしやすいはずです。

改善のコツ|5分10分のわずかの時間でも読書する環境を整える
日本人の読書時間は意外に短く、平均は30分しかありません。毎日30分から1時間の読書をすることができれば、あなたの読書量は平均以上となり、読書の効果も得られやすくなります。
読書は、自分への投資とも言われます。投資が資産に変わるには、投資信託と同様に時間がかかります。毎日5分10分の隙間時間を集めて、1日に30分から1時間読むのでも継続すると、数ヶ月か数年後には資産として効果が得られるようになります。
紙の本を手元に置いてもいいですし、電子書籍アプリをスマホやタブレットにインストールして、いつでも読めるようにすると、楽に読書ができる環境を作ると良いです。
読書する時間がないという人でも通勤途中の10分や、仕事で交通機関で移動している中の10分、寝る前の10分、朝起きての10分をかき集めることは簡単にできると思います。

まとめ
本の読み方がわからないという人は読書経験が少ない人かも知れません。
読書の読み方は目的で少し変わります。例えば、脳トレとして読書をして頭の回転が速くなるようにしたいと思うなら、素読を高速に行うことで、脳が活性化します。

例えば仕事で困ったことがあり、対策を本の中に探す人もいます。その場合は目次から関連することを探し拾い読みをすればいいです。全文を読む必要はありません。
本を読む前に、読み終わったら何を得ていたいと考えるのかによって、本の読み方は変わります。
関連記事一覧
本の読み方がわからない人|これで解決!*当記事