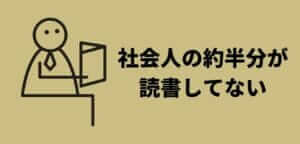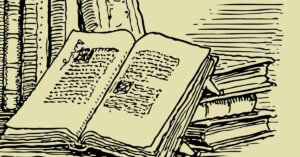素読とは音読のように発声をして本を読む方法です。
同じように声を出して読む方法であっても、音読とは読み方も効果も違いがあります。
素読をしている身近なシーンでは、幼稚園で子供たちが声を揃えて発声しているシーンがあります。子供達は言葉の意味を理解していない文字をみんなで大き声で発声しています。なぜなのか。
2017年脳科学の川島隆太さんと教育学者の齋藤孝さんの対談記事が書籍化された「素読のすすめ」が出版され、素読という言葉が注目されました。
実は素読をすることで、脳が鍛えられる効果があることが分かったのです。
素読とは頭の回転が良くなる本の読み方|基本からやり方まで
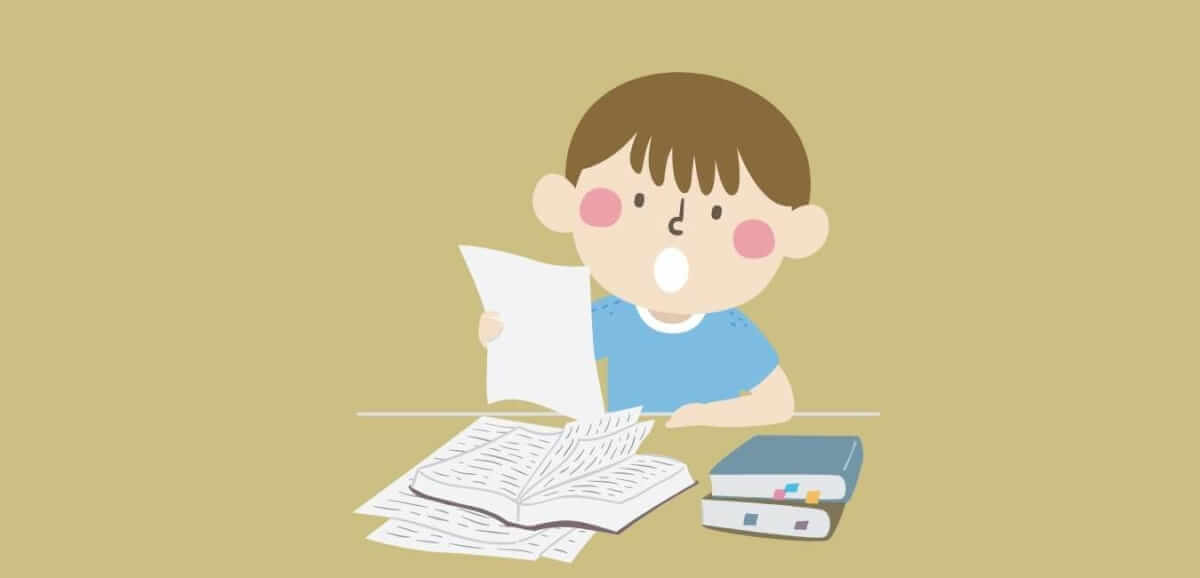
「脳トレ」で知られる川島隆太さんが齋藤孝さんと共著で書籍化された「素読のすすめ」では、素読の重要性が繰り返し解説されています。
素読の意味は
素読の意味は、当記事のタイトルで紹介していますように、本や文章を声に出して読む方法です。では「音読」とは何が違うのか、と気になります。
素読の基本|音読との違い
素読も音読も、「声を出して読む」ところまでは、同じです。
音読している時を思い出してもらうとわかりますが、音読をしている時には、声を出して読みながら、自分から発せられる声を聞きながら、頭の中では文章内容を理解しています。ですので音読で大事なことは、内容を理解することです。
素読では、自分が内容を理解しているかどうかが問題ではないのです。つまり意味を考えずに、立ち止まることなく、読み進めていく方法なのです。
大事なことは、内容理解ではなく言葉のリズムや音を聞くことで脳が刺激されることです。なるべく高速で行うことで、より素読の効果(脳の活性化)は高くなることが確認されています。つまり素読では、内容を理解することではなく、脳を活性化することが目的ということになるのです。

素読の始まりは寺子屋の論語|理解よりも脳を鍛える効果
素読の始まりは、江戸時代の寺子屋に始まります。寺子屋は今の時代なら、小学校の低学年位でしょう。当時は、寺子屋で文字の読み書きやそろばんを学んでいました。
当時は「論語」を使って漢文の勉強していたようですが、その時の勉強が素読でした。
意味の理解は後回しにて、素読によって文字を読み、音を聞くということをしていました。素読は、次に暗唱のステップへと進んでいたようです。
子供たちは、素読と暗誦をして、論語の意味を理解することなく、読んで・発声して・自分の耳で聞くという繰り返しをしていました。論語の意味を理解するのは、後年のことでした。
論語を素読した効果は、文字や文章に対する抵抗がなくなり、音として記憶し感覚が鋭くなっていたものと考えられます。意味の理解は後回しなのですから、始めやすいという効果もあったでしょう。外国の歌を音として覚えているのと同じだったものと思われます。
素読の効果で頭の回転が良くなる
脳科学の川島隆太さんによれば、素読を早くやると脳機能の低下を止めることができるというのです。
仙台市の子供の脳を7万人調べた実証データに基づいた上での言葉ですので、説得力を感じます。さらに、スマホとSNSの使用するほど学力が低下することにも触れています。
音読にも脳の前頭葉が刺激される効果があることは知られています。
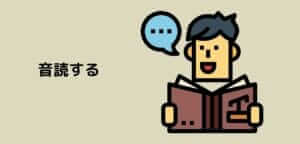
川島氏の実証データによれば、できるだけ速く素読することで、脳に大きな変化が確認されたということです。それは、MRIで調べたところ、脳の前頭前野の両側の体積の増加に現れていたというのです。
そのことにより、頭の回転速度が上がり、記憶力が良くなることに作用しているというのです。

素読が意味ないのは誤解|素読は脳トレ
文章を読むのに、内容を理解しない本の読み方は意味ないと感じる方もいるかもしれません。しかし素読には前述したように音読などの読み方と違う目的があるのです。
素読とは言わば、脳をトレーニングする方法として理解すると良いです。「文字を見ること」「発声すること」「聞くこと」を同時に行うことで、脳を刺激するのが目的なのです。意味を理解しない素読は、意味ない読み方ではないのです。
また本が読めないとか、頭に入らないという人は、改善策として素読をするのがおすすめです。本の内容の理解を、一旦横に置いて「脳の活性化」に特化した素読を進めておくのは、本を読むことに集中できない時でも、トレーニングとしてお勧めできる方法だからです。

素読のやり方
素読が音読と同じように、声に出して読む方法であり、目でみて、声に出して、読むことで脳に良い刺激を与えるところまで、同じであることがわかりました。
繰り返しになりますが、素読では内容の理解は後回しです。いわば脳を活性化するために行うトレーニングのような読み方と言えます。江戸時代の寺子屋の事例でも分かるように、子どもたちは論語を暗唱できるまでに読みこなしたといいますが、論語の内容を理解していなかったと言われています。
後述しますが、江戸時代の寺子屋は現代の幼稚園の教育につながっているように思われます。子どもたちは意味を理解していない言葉を先生の指導によって読んでいきます。その方法が素読のやり方の基本となります。
素読のやり方は、次のとおりです。
「声に出して読む」
「途中意味が分からない部分があっても立ち止まらずに読む」
「できるだけ早く読む」

幼稚園の子供たちは素読をしている
実は私たちの身近なところで、素読はずっと行われてきました。
それは、幼稚園や幼児教室です。この年代の子供に対して、意味がよく分かっていない言葉を、壁に貼って、みんなで声を出して読んでいます。(言葉の意味の理解は後回しです)
ほとんど寺子屋の時代と同じままのことが続けられているのです。意味のわからない言葉を声を出して、読んで覚えるのは、音とリズムです。言語の感覚を磨くだけのことに集中しているのです。
素読の本質は、「文字を見て」「声に出して読む」「自分の発した声を聞く」という言語の感覚を磨くことにだけに注力することであり、音読のように、途中で意味を考えて立ち止まったりせずに、できるだけ早く素読をすることで、脳の機能が高まるのだということの理解になります。
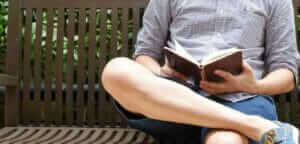
まとめ
素読は、本を読む方法というよりも、文字を読んで発して聞くという動作を同時に淀みなく行うことで脳を鍛える技術ということです。
江戸時代の寺子屋で子供たちが、意味を理解していない論語を素読し暗誦していたのは、脳を鍛えるためだったのだと理解できます。今の時代の幼稚園や幼児教室で、子供たちが大きな声で遊びのように、意味を理解していない言葉や文字を読んでいるのも、そういうことだったのかと、理解できます。
もし子供が元気よく文字を読んでいれば、意味が分からなくても、十分に脳には良い効果があるということです。
関連記事一覧
速読のやり方を効果的に:簡単できる方法から専門テクニックまで
素読とは頭の回転が良くなる本の読み方|基本からやり方まで*当記事