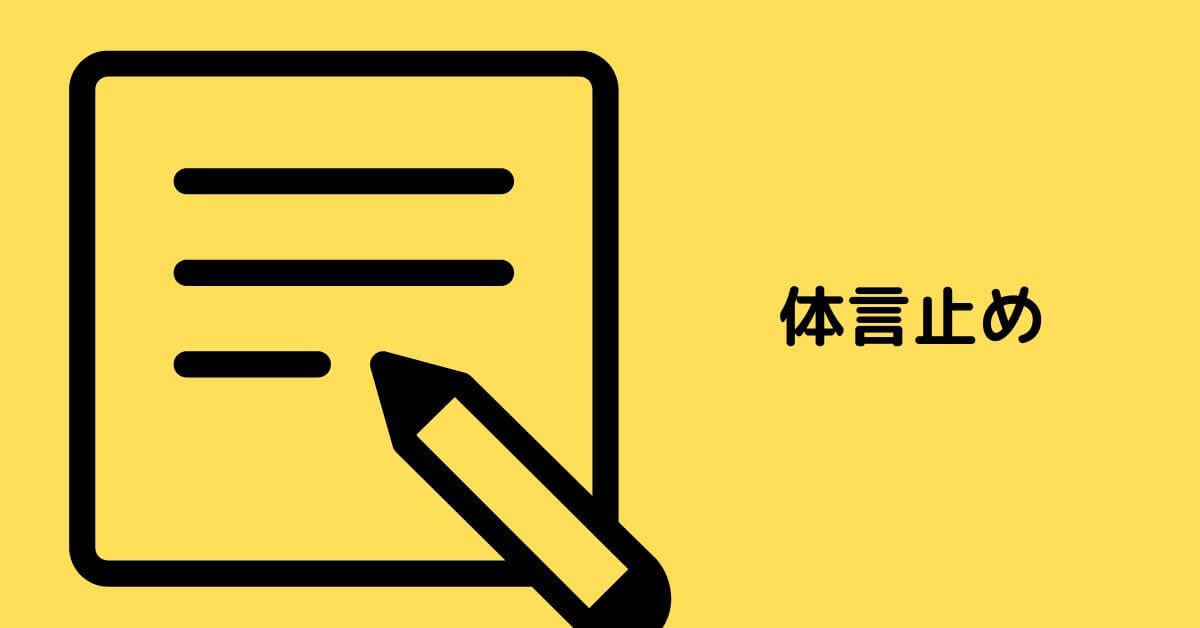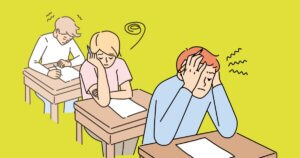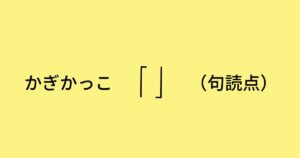文章表現の一つに「体言止め」があります。文章表現に変化が生まれ、印象づけやすくなります。
しかしビジネスシーンでは関係者からの文面に体言止めが使われていると、違和感を感じます。体言止めが有効な場面はビジネスシーンでは特に限定的と考えるべきです。一般的に、ビジネスシーンで文章を書く場合には、社内も社外も含めて、体言止めは使ってはダメな表現と考えておくべきです。
ビジネスコミュニケーションにおいて、文章の効果的な表現方法は重要です。本記事では、「体言止めの意味とビジネスシーンでの問題点」に焦点を当てて解説しています。
うっかり体言止めを使ったことで仕事の大きなミスにつながらないように、注意しましょう。
体言止めの意味とビジネスシーンではダメな理由
語尾に名詞を使うことで文章表現に変化をつける修辞法があります。それが体言止めです。
しかしほとんどのビジネスシーンでは、使ってはダメな表現です。どうしても使う場面には注意が必要です。
体言止めとは?意味|用言止めと例文
体言止めとは、名詞や代名詞などの体言を語尾に使う手法です。ちなみに、体言とは主語になる単語であり名詞や代名詞を指します。
体言止めの定義
俳句や短歌などの短い文章でよく使われます。また、小説やエッセイなどの文章でも、効果的に使われることも多い表現方法です。
体言止めとは文章やフレーズの終わりに体言(名詞や代名詞)を使用して文を終わらせる表現手法です。具体的には、動詞や助詞などの活用を省き、名詞だけで主語や述語を示す形式です。
体言止めに対して用言止めとは
対して用言は述語になる単語で、動詞(形容詞・形容動詞も含む)を指します。
ですので、私たちが普段利用している一般的な文章表現では、「ですます」で文末を終える場合が多いので、語尾には用言を使っているということになります。(用言止めとも言う)
体言止めと用言止めの例文
用言止めの例文は、以下のようになります。
「今日の天気は雨です。」「○○軒では醤油ラーメンが美味しいです。」というように、動詞や形容詞で文末を終えます。
例文を体言止めで表現すると、以下のようになります。
「今日の天気は雨。」「○○軒で美味しいのは醤油ラーメン。」というように、名詞で終えます。名詞で終えることで、「雨」や「醤油ラーメン」が強調され余韻が残ります。
体言止めの効果|俳句や短歌・小説なら効果的だが
語尾を体言止めにすることで、印象や余韻を強める効果があります。その結果、読み手は文章のリズム感を感じます。
また、例文の場合なら「雨」「醤油ラーメン」に惹きつけられる印象を持たされます。俳句や短歌・小説の場合なら、雨のシーンから何かが始まっていくような期待感が生まれ始めます。読み手が持っている経験値によっては、とても世界が広がる瞬間です。
しかし相手の想像力によって、世界が広がるということは解釈が確定していないということになります。相手によって解釈が異なる場合があり得るということです。
体言止めは文学作品や広告などのクリエイティブな表現手法として広く用いられていますが、ビジネスコミュニケーションにおいては注意が必要です。
ビジネスの場面では、具体的でわかりやすい表現が求められます。話し手(書き手)と聞き手(読み手)の間で認識が違うのはトラブルの元だからです。認識のずれがないように数値を用いて伝達し合うのも、認識を一致させるためです。人によって解釈が違うという表現はビジネスシーンではNGなのです。
体言止めはビジネス文ではダメな理由
体言止めを使うことで、文章に変化を与えやすくなり、強調して印象づけたり、余韻をもたせたりなど、文章の印象を変えられ表現豊かになるメリットがあります。
但し場面によってはNGな場合があります。典型的なのは、ビジネス文です。
ビジネスの場合、先の例からしますと「今日の天気は雨になる」のか「今日の天気は雨だった」のか「今日の天気は雨かもしれない」のか、では困るのです。どれか確定してないとビジネスの話が進まないのです。ですので、ビジネスシーで体言止めを使うのはデメリットでしかありません。
ビジネス文で重要なのは情報の正確性
ビジネスでは、口頭で話す場合も、文面で伝える場合も、原則は「伝える情報の正確性」と「敬語」にあります。
ビジネス文で何より優先されるのは、「情報の正確性」です。過大でも過小でも良いことではありません。ですので、修飾や修辞に偏ったビジネス文は軽視される可能性があります。
ビジネス文を書きなれていないと、文章表現を誤解してしまう人がいます。それは、文章に変化や強調を与えることです。ビジネス文は小説ではありません。ビジネス文に必要な文章表現は、情報が正確で、具体的で、分かりやすいことです。
抽象的であったり曖昧に聞こえる表現を続けていると、評価を落としてしまいます。

ビジネス文は原則敬語|体言止めは失礼かつ曖昧
ビジネスでは、相手が目上の場合は当然敬語で表現しますが、相手が年下であっても敬語で接することが原則です。また会社の関係上、相手が下請けであったとしても、やはり敬語で接することで信頼関係につながるものです。
仮に、体言止めをビジネス文に使えば、相手には「失礼な人間」として印象づきます。
例文の「○○軒で美味しいのは醤油ラーメン。」を見れば一目瞭然です。相手が同僚であれば大きな問題ではありません。しかしビジネスシーンでは、年齢や職位・社外社内問わず、一般的には敬語で話すものです。社内の同僚の関係であろうと、丁寧語で話すのが普通です。
最低でも文末は、「です。ます。」で終えるべきです。
体言止めには、上から下への命令的響きを感じるからです。社外の関係ならありえないとなり、即刻取引停止になってもおかしくありません。
それは、社内においても同様です。相手によっては、「偉そうな人」と感じたり、「稚拙な人間」として、印象づけることになります。上司だからといって、部下に対して敬語を使わない人もいます。しかし実際には、部下に対しても敬語(丁寧語)を使うことで、上司は自身に対する信頼感を高めることができます。(上司と部下は業務上の役割でしかありません)
体言止めは失礼に聞こえる上に、動詞がないので何をするのかが曖昧な表現です。ビジネスシーンでは使ってはダメな表現です。

ビジネスシーンで体言止めを使うと誤解を生むリスクがある
体言止めは文脈や背景を省略する傾向があります。しかし、ビジネスシーンでは正確な情報や文脈を共有することが重要です。体言止めだけでは相手が必要な情報を正しく把握できず、誤解や誤解釈が生じる可能性があります。
体言止めは抽象的な言葉や概念を使用することが多いため、相手に対して明確な意図を伝えることが難しい場合があります。具体的な行動や要求を伝える際には、より具体的な表現や文脈を提供する必要があります。体言止めだけでは相手が正確な意図を理解できず、誤解釈や誤解が生じる可能性があります。
用言止めもビジネスでは使わないほうが懸命|曖昧な表現になる
体言止めはビジネス文では「失礼」に聞こえてしまうリスクが有ることをお伝えしました。
では、語尾を動詞で止める用言止めはどうなのかについても解説します。
結論から言えば、用言止めもビジネス文では「有効とは言い難い」です。
例えば「経費を削減」「売上の増加」「労働環境を改善」などという表現を使う人が多いです。しかし、この次に具体策を表現しなければ、相手には曖昧な印象しか残りません。
さらに例の場合なら「経費の削減」を「目指す」のか「現在している」のか「過去にしたのか」という意味についても曖昧です。
もしこれまでにプレゼンや報告などで、これらの用言止めを多用してきているなら、相手の表情を思い出して下さい。相手は曖昧な表情をしていたはずです。

体言止めをビジネス文に使うとデメリットしかない
体言止めや用言止めを使うときの音の余韻などを誤解して覚えていると大人として不適切な使い方をしてしまいます。相手からは「失礼な人」と思われ、恥ずかしい思いをします。
体言止めをビジネス文に使うことには、デメリットしかありません。ビジネスシーンで、体言止めを使っている人に共通しているのは、マンガをよく読み、小説は時々読んでいる人で、ビジネス書はほぼ読まないという人です。(マンガのセリフの中には頻繁に登場します)
問題は新人社員とは言えない年代になっても、その傾向が続く人です。誰からも指摘されずに40代にもなってしまっている人たちも存在します。
おそらくは指摘されても、おかしいことだと気づくことができないのでしょう。企画書や計画書を書く場面でも体言止めがやめられないのです。当然ですが、まともなビジネス文章を書けない人に、昇進昇格はあり得ません。
リーダーや管理職になれば、文章の間違い指摘も含めてチーム員に指導する側になるのです。文章の書き方を間違えていると、指摘されているのに修正できないのですから、未来はとても厳しいです。

まとめ
体言止めは、小説や広告など印象的な表現の変化を必要とする文章には、有効です。
しかしビジネス文のように、敬語をベースとして正確性を求める文章には、使わないほうが懸命です。ビジネス文では、用言止めも同様です。耳障りが良さそうに聞こえる可能性がありますが、具体性がないために、相手には曖昧さしか残りません。
関連記事一覧はこちら
体言止めの基礎から応用:ビジネス文書・レポート・論文での活用法
体言止めの例文: 文章を効果的に書くテクニックと具体的な使い方
体言止めの意味とビジネスシーンではダメな理由 *当記事