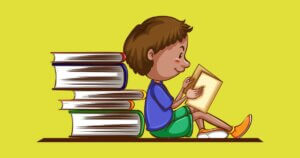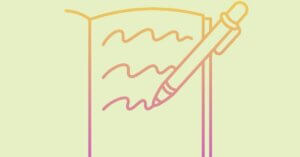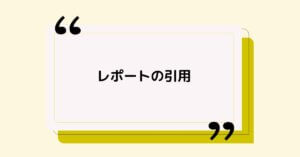ブクログとは読んだ本や読みたい本のレビューを記録するサービスです。
読書メーターと比べて、迷った挙句両方を使っているユーザーもいます。ブクログの方が記録を残す事に重点をおいたサービス内容になっています。
当記事では、ブクログの使い方や特徴について解説します。
ブクログの使い方と特徴
読書の量が増えてくると、過去に読んだ本に対する記憶が曖昧になってしまいます。
その結果、同じ本を2度購入してしまうなどのミスをしてしまいます。最低限の情報だけでも記録しておけば、数年前に読んだことがある本だと思い出すことができます。読書量が増えてきた人には、ブクログなどの記録管理アプリをお勧めします。
ブクログとは何ができるアプリか
ブクログは、名前の通り、本のレビューを記録(ログ)閲覧することに特化されています。本のレビューは2つ書くことができます。一つは公開OKのレビューを書き、もう一つは非公開の記録もできます。
文字数の上限(読書メーターは255文字)は気にしなくて大丈夫です。好きなだけ書いてください。
また読書メーターのように、他のユーザーと積極的に交流を深める仕様にはなっていません。もちろん全くないわけではなりません。読書をしていてわからないことがあれば、談話室に質問を投げかけると、ユーザーの誰かが反応して教えてくれます。(掲示板的機能)
このアプリの主な機能についてご紹介いたします。
- 読書記録の管理: ブクログを使用すると、読んだ本の情報を簡単に記録できます。タイトルや著者、読了日などを入力しておくことで、自分の読書履歴を整理することができます。
- 感想の共有: 読書した本に対する感想やレビューを書いて共有できます。これにより、他のユーザーと読書に関する情報を交換し、新たな本の発見や読書仲間とのつながりを築くことができます。
- 読書の記録と分析: ブクログは、読書の進捗や傾向をグラフや統計で表示してくれます。これにより、自分の読書ペースや好みのジャンルを把握しやすくなります。
- 読書チャレンジの設定: アプリ内で読書チャレンジを設定できます。年間や月間の読書目標を設けることで、自分自身を読書に向かって励ますことができます。
- 読書仲間との交流: ユーザー同士が交流できるコミュニティ機能もあります。他のユーザーをフォローし、感想やおすすめの本を通じてコミュニケーションを楽しむことができます。
- ウィッシュリストの作成: 読みたい本をウィッシュリストに追加できます。これにより、気になる本を見逃すことなく、次に読むべき本を管理することができます。
ブクログの使い方と特徴
ブクログの使い方は簡単です。
ブラウザとアプリからログイン可能です。
ブクログにログインする


新規の会員登録には、メールアドレスとブクログIDとパスワードが必要です。ツイッターやhontoのアカウントで登録することも可能ですが、メールアドレスの入力をすすめられます。その後の管理上の手続きを考慮すると、メールアドレスは登録しておいた方が良いです。
そして最初にすることは、自分専用の本棚を設定し作ります。ブクログは、Web本棚サービスだからです。
本棚の中には、読み終わった本(以前読んだ本)や今読んでいる本、読みたいと思っている本を収めることができます。読もうと思ってまだ読んでいない積読もあります。読みたいと思っている本は、アマゾンのリンクから購入画面へと自動的にアクスして購入もできます。
ブクログと読書メーターの違い
「ブクログ」と「読書メーター」は、両方とも読書愛好家向けのウェブサービスですが、いくつかの違いがあります。以下にその違いを簡単に説明いたします。
ブクログ:
ブクログは、読んだ本の記録を管理し、感想やレビューを共有するためのプラットフォームです。
- 読書記録の管理: ブクログは、読んだ本のタイトルや著者、読了日、評価などを記録することができます。これにより、自分の読書履歴を整理することができます。
- 感想の投稿: 読んだ本に対する感想やレビューを投稿できます。他のユーザーと交流しながら、読書の体験を共有できます。
- 読書の統計情報: ブクログは、読書の傾向や進捗をグラフや統計情報として表示します。自分の読書ペースやジャンルの傾向を把握しやすくなります。
- 読書チャレンジ: 年間や月間の読書チャレンジを設定でき、読書目標を達成する楽しみがあります。
読書メーター:
読書メーターも、読書履歴の管理と感想の共有を中心にしたウェブサービスです。
- 読書記録と分析: 読書メーターは、読んだ本の情報を記録し、統計情報を提供します。ページ数や読了日、ジャンルなどを分析することができます。
- 感想の共有: 読書メーターでも感想や評価を投稿でき、他のユーザーとコミュニケーションを取ることができます。
- 読書の振り返り: 過去の読書履歴を振り返ることで、自分の読書傾向を把握することができます。
違いの要点
- ブクログは感想の共有と交流が強調されており、他のユーザーとのコミュニケーションが重要です。
- 読書メーターは読書履歴の詳細な分析に重点を置いており、自分の読書傾向を知ることができます。
どちらも読書ライフを楽しむためのツールですが、自分の好みやニーズに合ったものを選ぶことが大切です。
ブクログで登録した名前変更する
とりあえず登録した人は、あとで名前を変えたくなるかもしれません。
変えたいという人は、後で変更することができます。ホーム画面>設定>プロフィール設定から、ブクログIDやニックネームの名前も変更可能です。
性別や誕生日は公開・公開しないを選択できます。
ブクログの本棚を追加して複数持つには
アプリから利用する場合、複数のアカウントを作ることができます。
マルチアカウントとして利用できます。本棚の歯車マークから>アカウントの切り替え>既存のアカウントを追加するを行うことで、アカウントを切り替えて使うと、本棚を複数利用することができます。
ただ後述しますが、カテゴリで分類し、タグで関連付けて管理ができますので、マルチアカウントの必要性はそれほど高くはないと感じます。
ちなみに読書メーターでは複数の本棚を所有できる設計になっています。
ブクログににアカウントを登録しない使い方
個人情報の流出騒ぎなどのニュースを見たり聞いたりすることがあります。
様々なサービスを受ける場面で、新規登録をする必要がある箏に不安を感じる人もいるかもしれません。
ブクログではアカウントの登録をしないでも、ある程度のサービスを受けられます。ある程度のサービスとは、「本を探すこと」・「人気になっている本の情報を知ること」「新刊情報を知ること」です。
ブクログではカテゴリとタグを使い分けられる
ブクログの本棚ではカテゴリとタグを使うことができます。
カテゴリもタグも使い分けは個人に任されています。通常はカテゴリーで分類し、特徴にタグをつけて関連する本として管理することができます。カテゴリーは中分類くらいのイメージでつけると使いやすくなります。
あまり小さい分類にカテゴリー分けしてしまうと、カテゴリーだけが増えすぎてしまい1カテゴリーに1〜2冊しか本が存在しないという現象が起きてしまいます。それではカテゴリー分けする意味がなくなります。
またブクログのタグは本につけて管理することで、後でタグで関連本を絞ることができます。ハッシュタグとしての使い方が可能です。カテゴリを飛び越えて、キーワードとしてタグ付けして置くことができます。関連するキーワードで絞り込むこともできます。
ブクログにない本はあるのか
ブクログが便利すぎて、自分の読書記録を一元管理しようと思う人も多いです。
すると、ブクログにない本に出会うことがあります。ブクログではアマゾンのシステムを使っている関係上、アマゾンに登録がない本は、検索しても表示されない本もあります。
その場合は、検索結果画面の本を登録するメニューの中の「オリジナルアイテム登録」から登録することができます。
ブクログのランキング
ブクログのランキングの分類は非常に多彩です。
「デイリーランキング」「週間ランキング」「月間ランキング」「オーディオブックランキング」が集計されています。
本の種別は「本」「文庫」「新書」「マンガ「殿堂」に分類されており、さらに年間では2009年からのランキングを見ることができます。
ブクログには感想を非公開にする機能がある
ブクログのレビューは公開用と非公開用を記録できます。
さらに公開用についてもブクログが提携した外部サービスやブクログが許諾した出版物に、掲載されることを「許可しない」という選択ができます。
ホーム画面>設定>レビュー掲載の設定で選択可能です。
非公開の記録の方には、誰かに忖度する必要もなく、思うまま日本に関する記録を残すことができます。
ブクログ 新刊
ブクログでは、新刊に関する情報を「本・新刊ニュース」からみる方法と、設定したキーワードが含まれる新刊情報をメールで通知を受け取る方法があります。メールアドレスは、入力しておいた方が良いです。
ブクログを退会する方法
ブクログの退会についての方法を確認しておきます。
マイページの設定から、メニューにある「退会」から簡単に手続きができます。
ただ状況によっては、お知らせメールだけ止める方法も選択できますし、本棚を全部クリア(まとめて削除)する方法もあります。
完全に辞めるかどうかはよく考えた方がいいです。無料のサービスだから仕方がありませんが、一度退会した場合、復帰ができません。再開する場合は、一からのスタートになります。
ブクログからエクスポート
ブクログの中に記録してきたデータを引き出したい時は、エクスポートすることができます。
ファイル形式はCSVです。データの項目は、サービスID、アイテムID、ISBN、カテゴリ、評価、読書状況、レビュー、タグ、読書メモ(非公開)、登録日時、読了日、タイトル、作者名、出版社名、発行年、ジャンル、ページ数です。CSVファイルは、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトやアプリで使用できます。

まとめ
読書の記録を残す方法は、多彩です。当記事ではブクログアプリやWebサービスの利用を紹介しています。
純粋に本に関する記録を残すと考えると最善のWebサービスです。しかし読書を介して誰かとコミュニケーションしたいと考える人ならば、読書メーターがいいでしょう。
あまたアナログで記録を残す読書ノートという方法もあります。後日に復習の材料としての勉強のための読書ノートを考える方には、手書きの読書ノートがおすすめです。
関連記事一覧