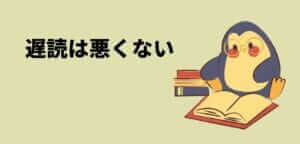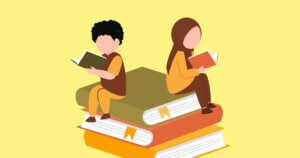本記事では、「読書感想文の書き方」「社会人におすすめのテンプレート」「実際の例文」という3つの要素を取り上げ、読者のみなさんが効果的な読書感想文を書くための手助けをいたします。
まず、読書感想文の書き方については、イントロダクション、本文、結論という基本構造を解説します。さらに、興味を引く方法や要点の整理、具体例の活用など、具体的なアドバイスをご紹介します。
次に、社会人におすすめの読書感想文のテンプレートについて解説します。テンプレートの利用は、効率的に文章をまとめる手法として大変有効です。シンプルなテンプレートから複雑なテンプレートまで、幅広い選択肢をご提案します。
最後に、実際の読書感想文の例文をご紹介します。本記事では文学作品に関する例文について、感想文例を掲載します。これらの例文を参考にすることで、自身の読書体験を豊かな言葉で表現するヒントを得ることができます。
読書感想文の書き方ガイド社会人編
読書感想文を社会人になっても書く意味は、学生の頃とは全然意味が違います。
社会人になると、書類各種・レポート・報告書・顧客や取引先との商談や交渉もメール、などと、文字や文章について触れる機会が増えます。
読解力や文章作成能力・要約力など、文章を読む・書く・まとめるに関する能力が求められるのです。
社内の書類の書き方が下手だとしても、個人の評価は下がりますが、会社にとっては大きな問題ではありません。
しかし、社外関係はそうは行きません。顧客や取引との連絡やコミュニケーションは、今の時代は9割がメールです。メールの文章を書けないことで、ビジネスに大損失を起こすことは、現実に起きています。
読書感想文の書き方の基本は社会人も同じ
読書感想文の書き方の基本は社会人も同じです。本の内容を要約するだけではなく、自分の感想や考えを述べることが大切です。読んだ本がどんなテーマやメッセージを持っているのか、それに対してどう感じたのか、どう共感したのか、どう反論したのかなどを具体的に書きましょう。
読書感想文は自分の言葉で書くことが重要ですが、引用や出典を使って本の内容を補強することもできます。ただし、引用や出典は適切に表記する必要があります。読書感想文は自分の読書体験を伝える文章ですから、文章の構成や表現にも気をつけましょう。
序論で本のタイトルや著者、ジャンルなどを紹介し、本文で本の内容と自分の感想を交えて書き、結論で自分の読書のまとめや感想の結論を書くというのが一般的な流れです。表現については、誤字や脱字がないか、文法や句読点が正しいか、言葉遣いや敬語が適切かなどをチェックしましょう。
読書感想文は社会人にとっても有益な文章です。本を読むことで自分の知識や視野が広がり、文章力や表現力も向上します。読書感想文の書き方の基本を身につけて、楽しく読書をしましょう。
読書感想文の書き方の基本構造
読書感想文の書き方は、以下の基本構造に従って構成されます。基本構造は社会人の場合でも同じです。
1)イントロダクション:
イントロダクションでは、読者の興味を引く導入部として機能します。以下の要素を含めることが有効です。
- 本のタイトルや著者の紹介
- 背景情報や書かれた時代の文脈の説明
- 興味を引く引用やエピソード
2)本文:
本文は、読書体験や感想を詳細に説明するセクションです。以下の要素を含めることが有効です。
- 読んだ本の要約やストーリーの概要
- 自身の感想や思考、物語に対する洞察
- 著者の表現方法や文体、キャラクターの魅力についての考察
- 本書が自身の人生や考え方に与えた影響や学び
3)結論:
結論では、読書体験のまとめと自身の思いを締めくくります。以下の要素を含めることが有効です。
- 読んだ本の評価やおすすめ度
- 読者へのメッセージやアクションの提案
- 本との関連性や他の人にとっての価値についての考察
この基本構造に従いながら、自身の思考や感情を具体的に表現することで、魅力的な読書感想文を書くことができます。また、ストーリーの要約やキャラクターの分析、自身の体験や感じたことへの深い考察を取り入れることで、読者に共感や洞察を与える文章に仕上げることが重要です。

読書感想文の書き方はテンプレートで書けばいい|社会人編
読書感想文を書くことが苦手な社会人は、文章構成のテンプレートを使って書く練習をすればいいです。
文章構成のテンプレートとは、「何を、どのくらいの分量で、どの順番で書くか」をテンプレート化したものです。
白紙から書き始めるより、遥かに書きやすいです。
読書感想文のテンプレートと書き方
学生時代に読書感想文を書いてきた経験がある人なら、お分かりだと思いますが、読書感想文は、書き始める前に、大枠(骨子)を決めてから書き始めると、書きやすいです。
学生の場合の一般的な書き方(文章構成の骨子)は、以下のように書く場合が多いです。
・読む前の印象など|読み始めるきっかけや事前にその本に対して感じていたこと
・本文1|ごく簡単なあらすじ(長くなりすぎないように)
・本文2|内容の要所について、感じたこと
・まとめ|読み終わって、全体を通して感じたこと
しかし、社会人ともなれば、会社は読書感想文を後日の人事考課の参考に見ている場合が多いのですから、社会人としての論理的思考を感じてもらいやすい書き方にするのがおすすめです。
そのための書き方は、以下の通りです。
・序文|まず結論を書くことです。読書を通じて何を感じたのか。今後の業務に何を役立てることができると感じたのか、など。
・本文1|最初に書いた結論に繋がる根拠を書きます。なぜ、そう感じたのか、です。
・本文2|根拠につながる具体例です。関連する本の一部を引用すると良いです。
・まとめ|結論の繰り返し
本文2の具体例を示す引用を用いることについては、一般的に「引用ルール」が決まっています。引用ルールとは、著作権に関連することです。
会社に提出する読書感想文に、著作権の引用ルールは該当しないと思いますが、著作権の引用ルールを知っていて、活用していることは、プラスの評価になるはずです。
引用ルールは次の通りです。
・主従関係が明確であること・・・この場合、引用文は、あくまでも読書感想文を支えるだけの「従」の関係にあるということです。
・引用部分を明記・・・一般的には、「” ”」を使用して明記します。
・出典元を明記・・・今回は感想文ですので、「出典元:(本のタイトル名)何ページ」で良いでしょう。
・改変しないこと・・・これ重要なのですが、引用した文章は、原文そのままで引用することです。

社会人の読書感想文の書き方|テンプレート活用のメリット
社会人の方々が効果的な読書感想文を書くための具体的な手法として、テンプレート活用のメリットについて解説します。テンプレートを活用することで、以下のようなメリットがあります。
1)構成の手間を省力化:
テンプレートに基づく書き方は、一貫性のある構成を作りやすくします。これにより、論理的で読みやすい文章を簡単に作成することができます。
2)時短効果:
テンプレートに基づく書き方は、文章の骨組みが既に用意されているため、アイデアの整理にかかる時間を短縮することができます。これにより、忙しい社会人でも効率的に読書感想文を書くことができます。
3)自己表現の支援:
テンプレートは、論理的な構成や適切なフレームワークを提供するだけでなく、自己表現の手助けもしてくれます。テンプレートの枠組みを活用しながら、自身の考えや感情を豊かに表現することができます。
読書レポートの書き方でもテンプレは応用できる
読書レポートという課題があった方は、読書レポートの趣旨を確認すべきです。
要約文を求められているのか、要約と考察(意見や批評)を求められているのか、です。一般的に、要約だけで良い場合、意見や批評は不要のものだからです。
一般的な要約文の書き方は以下の通りです。意見や批評も求められている場合は、最後に加えると良いです。
・文章全体から、要旨を見つける
・要旨につながるように、文章構成に分解し、骨子を見分ける
・多くの場合、文章全体は、大見出しか章ごとに、分けられる
・要旨につながる要点を、分けた大見出しのブロックごと、あるいは章ごとに見つける
・要約文の場合は、それぞれの要点を、要旨にそうようにつなげて、わかりやすくまとめる
読書レポートを、読書感想文だと早合点して、作成すると、求められているものと、まるで違うものになりますので、注意しましょう。
要約文とあらすじは別のものですが、小説の要約だと、似てしまう可能性があります。
また要約文には、通常文字数制限があります。「100文字に要約しなさい」あるいは「10%に要約しなさい」などと、指定があるはずですので、確認しましょう。最短だと、「1行(〜5行)に要約する」などという場合もあります。

読書感想文を書く社会人はコピペNG
学生時代に、著作権フリーの読書感想文を全写しか部分写しをして、逃れてきた経験があるひとは、社会人になってもコピペをやってしまう可能性があります。
それは絶対にNGです。バレます。ネットから写した感想文は100%バレます。
学生時代は大丈夫だったと思ってる人もバレてます。ただ、学生の頃には読書感想文の評価割合が小さいものだったから影響が少なかっただけです。
社会人の場合、クビにこそなりませんが、昇進昇格はなくなるでしょう。人事部の評価には「コピペをする人」と記録が残ります。

読書感想文の書き方|社会人編の例文
文学作品に対する読書感想文の書き方の例文として紹介します。あくまでも例文としての紹介です。実際の場面では、指定の文字数等を意識して書いてみてください。
タイトル: 「『羊をめぐる冒険』への旅:読後の感動と人生への深い洞察」
イントロダクション: 『羊をめぐる冒険』は、村上春樹氏による文学作品であり、人生の意味や孤独との闘いについて描かれています。この小説を読み終えた私は、そのストーリーとキャラクターの深さに感動し、この読書感想文を通じてその魅力を共有したいと思います。
本文: この小説では、主人公の旅を通じて人生の意味や孤独との向き合い方について考えさせられます。私は主人公の孤独な旅路と彼の内面の葛藤に心を打たれました。物語の進行に合わせて主人公が成長し、自己発見を果たしていく様子は、私たち社会人にとっても共感できるものでした。私自身、この作品を読んで自己探求の重要性を再認識し、自身の人生においても内省の時間を大切にするようになりました。
さらに、本作では作者の独特な表現やメタファーが多用されています。それによって、読者はストーリーに没入し、さまざまな感情を味わうことができます。私はこの作品を通じて、言葉の力や文学の魅力に再び惹かれました。また、読書を通じて他者の物語に共感することで、人間の複雑な感情や人間関係について深い洞察を得ることができました。
結論: 『羊をめぐる冒険』は、人生の意味や孤独との向き合い方について深く考えさせられる文学作品です。この小説を読むことで、主人公の旅に共感し、自己探求や他者への共感の大切さを再認識しました。文学作品は私たち社会人にとって、人間の内面や人間関係に対する洞察を深める貴重なツールです。ぜひ皆さんも、この作品を読んで深い感動と洞察を得てください。
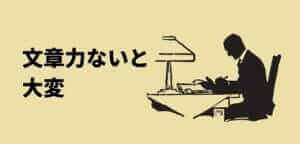
まとめ
社会人にこそ読書は必須です。学生時代の読書は、半分は趣味や楽しみだったと思います。しかし、社会人は、会社として評価を上げて、年収を上げていくのに必要です。
読書をして、読解力・文章力・要約力を高めていくことで、経営者や上司に認められるようになります。性格の良い人が出世するわけではありません。
読書感想文(読書レポート)の書き方を覚えて、必要なジャンルの本を読んでいくことをお勧めします。
関連記事一覧
大学生のための読書感想文の書き方ガイド|テンプレートと具体例
読書感想文の書き方ガイド社会人編*当記事