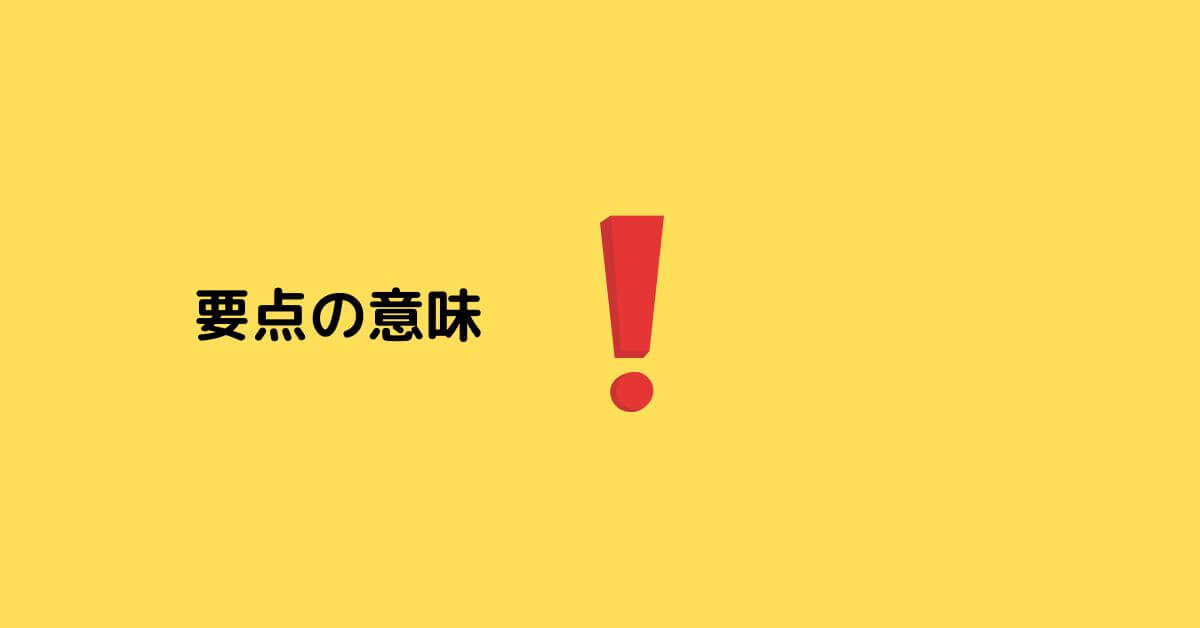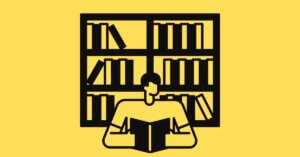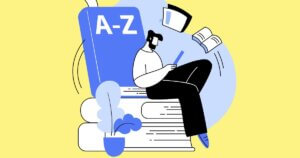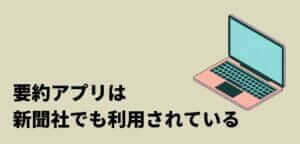社会人の仕事上のコミュニケーションは、要約でできています。
しかし世の中には読書をしないという人が、日本の場合は半分近くいるために、要点がわからないという人も混在しています。原因は読書をしない人が多いからです。(先進国の中で日本の読書率は15位)
小学校3年で要点を学び始め、4年になったら要約、5年になったら要旨の勉強をしているはずですが、大人になる頃には多くの人が忘れてしまいます。
この記事では、要点についての記事をまとめて紹介しています。
要点の意味がわかれば要約もできるようになる
実は要点や要約のことを、社会人になる前に忘れてしまう人が少なくありません。
この記事では、「要点」についてまとめて紹介しています。詳しくは「続きを読む」からご参照ください。
要点とは
要点を絞って要約をすることは、社会人になると、日常になります。上司に対してなんらかの説明(口頭・書面)することは毎日あります。仕事の役割が社外の人と折衝がある人なら、社外の顧客や取引先担当者に説明したり商談(交渉)したりを、ほぼ毎日繰り返します。
そういう場合の説明・交渉などでは、前提として、「要点を絞って要約して話す(文章を書く)」ことが基本となります。
ですから時に気を抜いて、要点を絞らずに話してしまうと、すぐに「君の話は何を言いたいのかわからない」と指摘されてしまいます。ですので、社会人の場合は、仕事に関連する話すをする場合(書く場合)は、すべて、要点を絞り、要約することが基本になります。
要約は要点をまとめたものです。要点は要旨に関連するものです。要旨に関連するキーワードを各段落や章の中に見つけると、そこに要点があるはずです。

要旨とは
要点と要約・要旨と、よく似た漢字が集まります。それぞれに重要な役割があります。本の場合であれば、本のタイトルに関連して本の最初の部分か最後の部分に、著者が最も主張したいことが書かれています。それが要旨です。
要旨が特定できると、関連性のあるキーワードから、各段落(各章)の中に要点を見つけやすくなります。見つけた要点を流れを崩さずに文章化していったものが要約になります。ですので、本の要約を作成することや、要点を絞ることは、比較的やりやすいと感じる部分があります。
社会人の要約では、本の要約のように、元となる文章がありません。要約の課題となる書籍がないことがポイントになります。例えば、「昨日までの過去1週間の業務報告をしてください」「□□プロジェクトの進捗状況を知りたい」などのようケースがあります。
これらの場合、報告するように希望されたことを要旨と考えるが良いです。ただ、現実は「質問の内容を具体的に示されていない場合もあります。「□□プロジェクトはどうなってる」など、曖昧な表現をされる場合もあります。そういう場合は、勇気を持って具体的な報告のゴールを確認することです。
その確認をしなかったために、「知りたかった報告は、そういうことじゃない」と言われてしまい、評価を下げてしまいます。

要点をおさえるコツ
要点をおさえるコツが特に重要なのは、要点を押さえて話す場面です。上司からの質問に対して、数秒後には答えなければなりません。「報告は明朝9時までにレポートで出してくれ」と言われると、報告レポートを作成することになります。面倒だと感じるかもしれません。しかし、口頭でピントがずれた報告をしてしまい評価を落とすよりも余程マシです。
口頭での報告や説明で、要点をおさえるコツは、「続きを読む」に詳しく解説していますので、ご参照ください。上司からの評価が上がる瞬間とは、まさにそのようなことです。
不意の質問なのに、「わかりやすく説明してくれた」ことで、社員の評価は「優秀な人材」として上がるはずです。

要点をおさえるのが苦手
本や文章の要点をおさえるのが苦手という方は、こちらの記事が参考になります。
実は、要点をおさえるのができない(苦手)という方は、原因が明確だからです。それは文章を読んだ経験が少なすぎることです。要点をおさえることができないということは、本や文章を読んでも、何が書いてある文章なのか、理解できていない可能性があります。表面的には理解しているかもしれませんが、著者が何を言いたいのかはわからない可能性が高いです。
本や文章を読んだ経験が少ないのですから、本や文章を読んで要点がわからないとしても、ごく当たり前のことです。
ですから、何歳であっても遅くありませんので、毎日できれば30分以上、少なくとも10分以上、本や文章を読むことです。その後で、自分なりに要約をしてみることです。

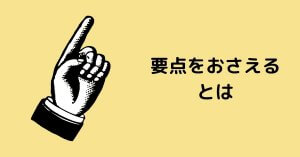
要点を絞る話し方にする
学生時代までは、好きな相手と好きなことを話していても大きな問題はなかったはずです。
しかし社会人になると、年代も違うし育ってきた環境が違う人同士が、互いに協力しあって仕事の成果を出そうとする環境になります。年代も違うし育ってきた環境が違うということは、考え方や話し方が違うということです。
そういう環境の中で、互いにわかりあい、仕事をスムーズにするための共通語として使われるのが、要点を絞った話し方です。論理的(ロジカルに)には話すなどもほぼ同義と考えて良いです。「続きを読む」のページでは、7つのポイントについて要点を絞った話し方を解説しています。
要点を意識しない話し方(学生時代のように)を続けていくと、上司から評価が厳しくなる以前に、職場の中で話し方がNGな人として認定されてしまう可能性があります。人間関係もうまくいかなくなる可能性があります。

要点の書き方はまとめるか・箇条書きにするか
要点を介して示す方法として、まとめる方法と箇条書きにする方法があります。

要点をまとめる書き方にすると、要約になります。要点を絞って要約する段階では、さらに枝葉となるような情報は削ります。要約文として何文字で表すのかにもよります。10万字のビジネス書を、100〜200文字の要約にする場合もありますし、20文字程度で表す場合もあります。文字数が少ないと要約力の難易度は上がります。
もう一つは要点を箇条書きにする方法です。社会人の場合、本を要約するよりも、業務に関する報告や連絡について要約する場面が多数あります。
本のような既存の文章があるわけではありませんので、要点を箇条書きにして書き出すことは、相手にわかりやすく示す方法の一つです。

箇条書きで要点を書くとわかりやすくなる
文章力に不安がある人は、箇条書きを使うと相手に要点を伝えやすくなります。
文章力がない人の特徴に、一文が長いという特徴があります。
度々、接続詞が使われ、文章が長くつながった状態になります。その結果、「何を言いたいのかわからない」「変な日本語」と言われてしまうこともあります。
プレゼン資料などではよく使われています。さらに、メールの中でも使うと、込み入った部分の説明がすっきりします。箇条書きを使った方がわかりやすくなります。

まとめ
要約文を作成する途中段階で、要点を抽出する場合があります。
社会人の場合は、本や文章を読んで要点を抽出する機会は少ないです。しかし日常業務に関するコミュニケーションがすべて要約をしたり、要点を絞ったりすることになります。
上司や取引先から、「□□□□について説明して」と言われれば、それは要点を提示すること、あるいは要約することが求められます。
関連記事一覧
「要点」を英語で言うと? 英語学習の要点をおさえて効率アップ!
要点の意味がわかれば要約もできるようになる*当記事