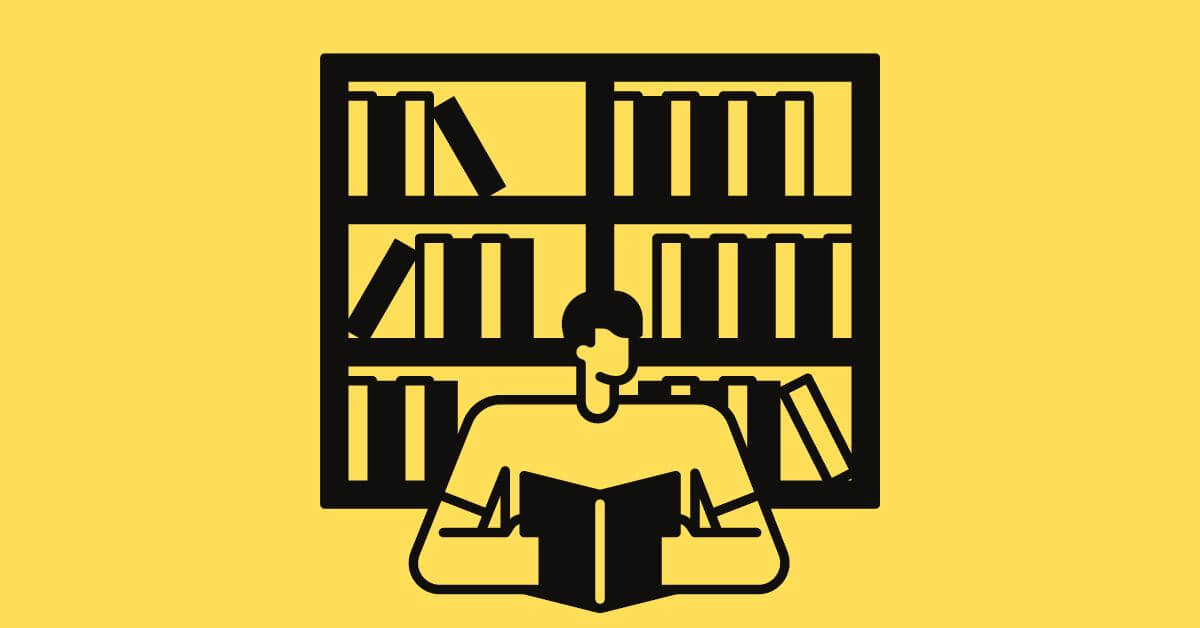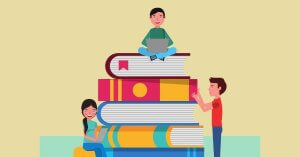本の要約とは、本の要約をすることと、本の要約をしたものです。
基となる本の内容を変えずに、要点をまとめて短く簡潔にしたものと、することを指します。
当記事では、その両方のケースについて関連する記事をまとめて紹介しています。
詳細についてはそれぞれの「続きを読む」から御覧ください。
本の要約のまとめ
本の要約と言えば、学生ならば「要約は書くもの」とイメージしていると思います。
しかし社会人になると、本の要約といえば、本を購入する前に下調べ的に「読むもの」というイメージです。
また要約には、著作権侵害というリスクもありますので、ルールをきちんと守る必要があります。
本の要約チャンネルyoutubeのおすすめを紹介
前述の通り、「要約」という言葉をつけているyoutubeチャンネルはありますが、基本的には要約をしていません。それは著作権侵害という法律に抵触してしまうからです。
ですので当記事で紹介しているのは、運営者の解説と感想が中心となっているチャンネルです。
チャンネルのスタイルは運営者によって様々です。参考になる役立つ解説もありますし、解説とも感想とも言いにくい独特のスタイルのチャンネルまであります。

本の要約を音声で聞く
本を音声で聞くといえば、Amazonのオーディブルのようなオーディオブックのサービスをイメージすると思います。最近では、電子書籍を扱う会社が増えて、どこを選べば良いのか迷ってしまいます。
しかし、本の要約を音声で聞けるというと、選択肢はグンと狭まります。現状は2択です。前述のフライヤーによる音声サービスと、YouTubeの要約チャンネルの音声を聞く方法です。
ただ後述しますが、YouTubeの要約チャンネルは、チャンネル名には「要約」が含まれていますが、実際には要約ではありません。正しくは、本の個人的解説チャンネルという名前が正解なのだと思います。
もしもタイトル通りに、「要約」を著作者との契約なしに行なっているとすれば、それは著作権侵害という犯罪になってしまうので、大問題でもあります。

本の要約の書き方には著作権侵害に注意する必要がある
著作者に無断でコピーを取って配布したり、ネット上で公開すると、著作権侵害という犯罪になります。事前に著作者と公開や掲載に関して条件等について許諾をもらう必要があります。通常は契約書を取り交わすものです。
学年が教育の場という特定の場所だけで要約をするなどの場合、著作権侵害にあたらずに使うことができます。
それでも、読書感想文に関するあらすじや、要約や読書レポートなどで、俗に言われる「ネタバレ的に使う」場合は一定の使い方によって、引用として使うことができます。
大学の読書レポートや要約書の作成に関する注意書きには、詳しく書かれています。引用ルールや著作権侵害については、大学では大きな問題と考えています。
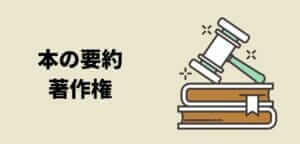
本の要約をブログに書くなら著作権に注意
自分が読んだ良い本を誰かに紹介したくてブログに書く人もいるかもしれません。
本の要約を個人的に書くことは問題ありませんが、ブログ等で公開すると著作権侵害にあたりますので、注意が必要です。ブログでは収益化していないという人もいるかもしれませんが、問題はそこではなく、公開することにあります。
公開する前提でブログに書くのであれば、個人的な感想を超えない範囲で、自分の言葉遣いによって書くのであればセーフなのです。本の中の一節を引用するのであれば、引用ルールに則って書く必要もあります。

本の要約と似ているレポートと読書感想文
似ていると説明しましたが、本来は意味が違います。
本の要約は、本の内容を変えずに短く簡潔にまとめることです。基本的には、自分の意見を含めないものです。ただ、公開する場によっては、著作権侵害に抵触することになります。個人の勉強のためや教育の場であればよいです。ネットに公開したり、コピーを配布すると犯罪の疑いを持たれます。
本のレポートは、出題者によって意図することが違う場合がありますので、確認をすべきですね。一般的な読書レポートでは、要約+考察の形式で書きます。考察では他に参考物件をエビデンスとして引用して、自分の意見を客観的なものとして示します。問題提起や共感によって、意見を示します。
本の読書感想文は、そのままの理解です。自分が何を感じて、何を学んだのか、読む前と読んだあとで何が変わったのかなどについて自分の意見を書きます。レポートの考察のように客観的根拠は必要ありません。

本の要約をアプリで読むならflier(フライヤー)が最強
本の要約を有料で読むことができるサービスを、複数の会社が、それぞれが事業化しています。その中で筆者も愛用し、おすすめできるのがフライヤーです。
他の企業の要約サービスには、価格面で有利なものもあります。しかし、企業が法人として申し込んで利用する印象が強くあります。(年払いが基本)
フライヤーだけが月払いが可能なので、個人ユーザーが使いやすい印象があります。
扱っている本のジャンルは、それぞれが少し違いがあります。「続きを読む」で、各社のサービスの違いや料金設定の違いを紹介していますので、ご参照ください。

本の要約は著作権侵害で違法のはず|YouTubeの要約チャンネルが続いているのは
本の要約は、本当に要約をしていて、それがブログであろうとYouTubeであろうとネットに公開されている時点でNGです。問題なく公開できるためには、著者と契約を締結する必要があります。
著作権侵害は親告罪(近年かなり変更があるので、いずれは親告罪ではなくなるかもしれません)です。ネットに公開されていることを知った被害者(著者)が告訴した時点で、犯罪確定となります。
結論を言えば、YouTubeの要約チャンネルはかなり多くのユーチューバーたちが、「要約」という名前をつけたチャンネルを公開していますが、本当に要約をしている動画はないということです。
原作と同じアイディアや理論などについて、動画が作られていても、表現しているキーワードや表現を全く違う方法や言葉で表現している場合、著作権侵害にはあたらないとされています。
つまり本の内容については、よく似たことが語られていても、原作に書かれている言葉を使わず、表現の仕方は自分独自の表現で表している場合、要約にはあたらないということになります。
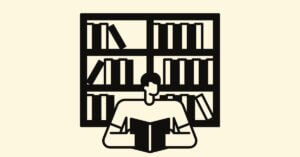
本の要約を書くなら章ごとに書くのがコツ
本の要約を書く場合、苦手に思っている方は、多くの場合、いきなり全体を対象にして要点を見つけたり要約の作業を始めようとします。
一般的な文章の要約と違い、本は1冊平均10万文字ほどある長文です。書籍によっては章立てや見出しが設定されています。全体の要約に取りかかる前に、章ごとに要点を見つけていくほうが書きやすいです。
本の種類によっては、章立てや見出しがなされていない場合もあります。その場合は、段落に分けて考えることです。段落には形式段落と意味段落があります。
すでに本の中で形式段落になっているかもしれません。重要なのは意味段落で、文章の構成をみることです。章ごとに要点を見つけたように、意味段落ごとに要点を見つけると要約しやすくなります。

本の要約サイトの利用ガイドとおすすめ無料サイト
本の要約サイトは、時間を節約しながら多くの本のエッセンスを吸収する手助けとなるツールです。主要なポイントや内容を簡潔にまとめたもので、全ての本を一つ一つじっくり読むことは難しい場合もあります。本記事では、本の要約サイトの中で無料で利用できるサイトに注目して紹介しています。
要約サイトは、本の内容を要点だけに絞って提供するため、複数の本を同時に読む時間を大幅に節約できます。長時間の読書が難しい方や、短時間で多くの情報を吸収したい方には最適な方法です。
無料で利用できるおすすめの本の要約サイトは、「flier(フライヤー)」と「bookvinegar」です。「フライヤー」では全ての要約コンテンツが無料で読み放題というゴールドプランが人気ですが、月に税込2,200円の料金が発生します。「bookvinegar」では約1000冊ほどの要約コンテンツがあり、基本的に全て無料で読むことができます。
しかし、企業向けの要約文作成ツールが開発され販売が始まっています。NTTが運営している「COTOHA Summarize」では、ハイレベルなAI要約機能を完成させており、企業を相手に月額10数万円としたサービスを提供しています。富士通ではシステムZinraiの公開を開始しました。AdobeでもAIによるテキスト自動要約サービスを開始していますが、導入についての企業別見積もりが必要なため、詳細は不明です。

ビジネス本要約のプロセス
ビジネス本の要約は、知識獲得とスキル向上の重要なステップです。ビジネスの世界では常に新たなアイデアや戦略が生まれ、それらを理解し、実行する能力は非常に重要です。しかし、時間が限られている場合や膨大な情報に圧倒されている場合、効果的な学習方法が求められます。
この記事では、ビジネス本を見つける方法から始め、要約スキルを磨く具体的なステップまでを詳細に説明します。ビジネス本要約のプロセスを明確に理解し、自身のビジネス知識を迅速に拡充し、要約スキルを向上させるために必要なステップを紹介します。
ビジネス本を読むことが好きな方も、初めてビジネス本を要約する方も、この記事から有益な情報を得られることでしょう。知識とスキルを高め、ビジネスの成功に一歩近づきましょう。
具体的な手順は以下の通りです:
- ビジネス本を読む目的を明確にする
- オンライン書店を利用
- ビジネス本の書評を確認
- ビジネス本の要約サービスを活用
これらの手順により、ビジネス本の知識を迅速に獲得し、要約スキルを向上させることができます。

まとめ
本の要約に関連する記事を紹介しています。
本の要約には、本の要約を読む場合と、本の要約を書く場合があります。
本の要約を書くことは大変勉強になりますが、著作権侵害のリスクもあります。ただし、ネットに公開しなければ、問題にはなりません。
ただし要約を私的に活用することは、メリットが大きいので、要約で練習したほうが良いです。要約の練習をすれば、同時に読解力と語彙力と文章力のレベルアップにも繋がります。
関連記事一覧