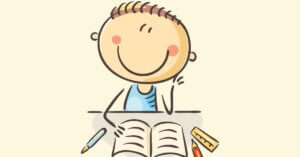読書は、知識を得るための重要な手段ですが、ただ読むだけでは、学びが定着しにくいことがあります。そのため、多くの人が読書ノートを作成することで、読書の効果を最大限に引き出そうとしています。
しかし、読書ノートの作り方は人それぞれ異なり、目的に応じたアウトプット型、インプット型、プロジェクト型といった手法があります。
本記事では、それぞれの目的別に読書ノートの作り方を解説し、あなた自身の学習スタイルに合わせた読書ノートの作り方を身につけることを目的としています。
読書ノートの作り方|アウトプットかインプットかプロジェクト

読書ノートを書く際、目的によって適した作り方が異なります。一般的に、読書ノートの目的は、アウトプット、インプット、プロジェクトの3つに分けることができます。
まず、アウトプット型の読書ノートは、読書した内容を自分自身の言葉でまとめ、要約することが目的です。このタイプの読書ノートは、読書した内容を深く理解し、アウトプットすることで自分自身の知識や理解を確認することができます。アウトプット型の読書ノートを作成する際には、まずは読書した内容の要点をまとめ、その後、自分自身の言葉でまとめるようにしましょう。
次に、インプット型の読書ノートは、読書した内容をそのまま記録することが目的です。このタイプの読書ノートは、将来的に読書した内容を振り返ったり、復習するために役立ちます。インプット型の読書ノートを作成する際には、書籍のタイトル、著者名、ページ数、読書日、そして要約などの内容を記録するようにしましょう。
最後に、プロジェクト型の読書ノートは、読書を通じて特定の目標を達成することが目的です。例えば、論文を書くために必要な情報を集めるために、関連する書籍から情報を収集する場合などがあります。プロジェクト型の読書ノートを作成する際には、プロジェクトの目的や目標、必要な情報や資料のリストなどを記録するようにしましょう。

アウトプット型読書ノート
アウトプット型の読書ノートは、読書した内容を自分自身の言葉でまとめ、要約することが目的です。
アウトプット型読書ノートの特徴
アウトプット型読書ノートは、読んだ本から得た知識や気づきを、自分自身でまとめてアウトプットすることを目的としています。そのため、以下のような特徴があります。
- 要約が主な目的:本の内容を要約することが中心となります。そのため、重要な箇所やポイントを簡潔にまとめることが求められます。
- 考察や感想を記録:要約だけでなく、自分なりの考察や感想を書き残すことも重要です。自分自身の思考を整理し、深く考えることができます。
- 見返しやすい構成:後で見返しやすいように、見出しや箇条書きなど、分かりやすい構成を取ることが大切です。
- 記述に手間がかかる:要約や考察を記述することで、時間や手間がかかる面があります。しかし、その分自分自身の学習効果を高めることができます。
- 整理整頓が必要:アウトプット型読書ノートは、自分自身の学習のためのものであるため、整理整頓が必要です。そのため、書き方や保存方法などを考える必要があります。

アウトプット型読書ノートの作り方
アウトプット型読書ノートを作成するためには、以下のような手順があります。
- 目的を明確にする:アウトプット型読書ノートの目的は、本から得た知識や気づきを自分自身でまとめてアウトプットすることです。そのため、まずは自分がどのようなアウトプットをしたいのかを明確にすることが大切です。
- 読書前に目次や構成を確認する:アウトプット型読書ノートは、後で見返しやすいように、分かりやすい構成を取ることが重要です。そのため、読書前に目次や構成を確認し、自分自身がどのような構成でまとめたいかを考えることが大切です。
- 要約する:読書中に重要な箇所やポイントを見つけたら、要約を書き残すことが大切です。要約は簡潔にまとめることが求められますが、自分自身が後で見返しやすいように、見出しや箇条書きなど分かりやすい構成を取ることが大切です。
- 考察や感想を書き残す:アウトプット型読書ノートは、自分自身の思考を整理し、深く考えることができるため、要約だけでなく、自分なりの考察や感想を書き残すことも重要です。
- 整理整頓する:アウトプット型読書ノートは、自分自身の学習のためのものであるため、整理整頓が必要です。そのため、書き方や保存方法などを考え、見返しやすく整理整頓された読書ノートを作成することが大切です。
インプット型読書ノート
インプット型読書ノートとは、主に知識や情報を得ることに重点を置いた読書ノートです。具体的には、本の内容を正確に理解するために、要点やキーワードを抽出して記録することが目的です。
インプット型読書ノートの特徴
インプット型読書ノートの特徴は、読書内容をまとめることに重点を置いている点です。主に、以下のような特徴があります。
- 見出しやキーワードを中心に整理されている
- 読書内容を要約・整理することに重点を置いている
- 自分なりの考察や意見は書かない場合が多い
- 読書の理解度を深めることを目的としている
インプット型読書ノートでは、本の内容を理解するために必要な情報を整理し、記録することが目的となります。そのため、具体的にどのような情報を記録するか、どのような方法で整理するかについて、考えておく必要があります。

インプット型読書ノートの作り方
インプット型読書ノートの作り方は、以下のような手順で進めることができます。
- 読書する前に目次を確認し、どのような内容が書かれているのかを把握する。
- 読書を進めながら、章ごとにまとめる。見出しをつけて、各章の内容を要約する。
- 本文中のキーワードや重要なフレーズを抜き出し、箇条書きにしてまとめる。
- 重要な図表や表などがある場合には、それらもまとめておく。
- 本文中で疑問に思ったことや理解できなかったことがある場合には、それらも記録する。また、疑問や理解できなかった点について、後で調べるためのキーワードを記録することもできる。
- 読書が終わった後、まとめた内容を見直し、さらに整理する。重要なポイントをまとめた箇条書きにして、自分なりの理解度を確認する。
インプット型読書ノートは、見出しやキーワードを中心に整理することが重要なので、整理した情報を後で見返す際にも見やすくなっています。また、要約やまとめをすることで、読書の理解度を深めることができます。
プロジェクト型読書ノート
プロジェクト型読書ノートは、読書に対してある特定の目的を持って取り組むことを目的としています。例えば、自分でビジネスプランを立てるためにビジネス書を読む場合や、自分の専門分野の知識を深めるために学術書を読む場合などが挙げられます。
プロジェクト型読書ノートの特徴
プロジェクト型読書ノートは、自分が取り組むプロジェクトに関連する情報を集めることが重要であり、そのために以下のような特徴があります。
- 目的に合わせた情報を集めるため、複数の書籍を参考にすることが多い。
- 情報を収集する際には、ノートだけでなく切り抜きやインターネット上の情報も取り入れることがある。
- 取り組むプロジェクトに関連するキーワードや概念などを中心に、情報を整理することが求められる。
- 情報を整理する際には、マインドマップやアウトラインなどの手法を活用することが有効である。
- 自分自身のアイデアや考え方を加えることで、独自の見解を生み出すことができる。
これらの特徴から、プロジェクト型読書ノートは、読書を通じて自分自身の知識やアイデアを深めることができる点が大きな魅力となっています。
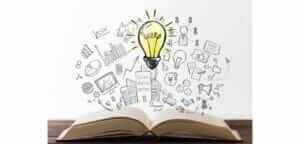
プロジェクト型読書ノートの作り方
プロジェクト型読書ノートは、プロジェクトを進めるように読書ノートを作成する方法です。この方法では、本の内容を理解し、目標を設定し、実際に計画を立て、実行し、評価を行います。
以下は、プロジェクト型読書ノートを作成するための手順です。
- 目的の設定
まずは、読書ノートを作成する目的を明確にしましょう。どのようなプロジェクトを進めるために、この読書ノートを作成するのかを明確にすることが大切です。
- 本の内容を理解する
次に、読書する本の内容を理解します。この段階では、インプット型読書ノートを作成する場合と同様に、本の概要や重要なポイントをまとめることが重要です。
- 目標の設定
プロジェクト型読書ノートでは、プロジェクトに必要な目標を設定します。これにより、プロジェクトを進めるために必要なアクションを決定することができます。
- 計画の立て方
次に、プロジェクトを実行するための計画を立てます。目標に向かって、どのようなアクションを取るか、それらのアクションをどのように実行するかを決定します。この段階では、日程表やToDoリストなどのツールを使用して、計画を明確にします。
- 実行
計画を立てたら、実際にプロジェクトを進めましょう。この段階では、アクションプランに従って行動し、目標を達成するために必要な作業を完了します。
読書ノートの活用方法
読書ノートは、読書を深めるだけでなく、アウトプットの練習やアイデア出しの場としても活用できます。ここでは、読書ノートを活用する方法を紹介します。
- アウトプットの練習
アウトプット型の読書ノートを使って、読んだ本の内容を自分自身でまとめ、要約、感想を書き出すことで、自分自身の思考力や文章力を鍛えることができます。また、自分自身が書いた文章を振り返り、改善点を探ることで、自分自身の成長に繋がります。
- アイデア出しの場として
プロジェクト型の読書ノートを使って、アイデア出しの場として活用することもできます。読んだ本からインスピレーションを受けて、自分自身のプロジェクトやビジネスアイデアを考え出すことができます。また、ノートを振り返りながら、アイデアの具体化や改善点を見つけることができます。
- 読書の復習に活用
インプット型の読書ノートを使って、読書の復習に活用することもできます。読んだ本から得た知識やアイデアを整理し、自分自身の言葉でまとめることで、記憶に定着しやすくなります。また、振り返りを行うことで、自分自身が理解し損ねていた部分を見つけることができます。
- キーワードの抽出
読書ノートからキーワードを抽出し、そのキーワードを使って、関連する本を探したり、情報収集することもできます。また、キーワードを使って、自分自身の問題解決の手がかりを見つけることができます。
- 読書の共有
読書ノートを使って、読書を共有することもできます。自分自身がまとめた内容を、友人や同僚と共有することで、自分自身の理解を深めることができます。また、他の人の読書ノートを見ることで、新しい視点やアイデアを得ることができます。
まとめ
読書ノートの作り方は、役立てたいと思う目的で選ぶと良いです。
いずれの方法も普通に読書をするよりも、一手間かかります。めんどくさいという人もいます。しかし、特にビジネス書のように自分の勉強のために読む読書であれば、一度読むだけでは勉強としては浅いのが現実です。
アウトプットするか、抄録してインプット強化をすることをしないと、数日後には何が書いてあったのか、何が勉強になったのかも薄らいでしまいます。
関連記事一覧
読書ノートの作り方|アウトプットかインプットかプロジェクト*当記事