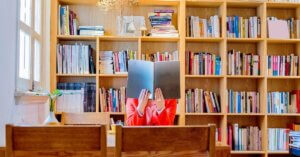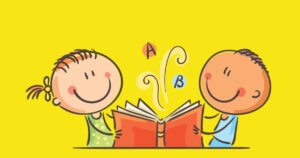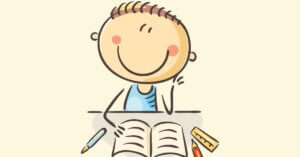読書時間は一般的にどのくらいなのか。平均何時間なのか。また読書すると時間がかかる、など読書の時間に関するポイントについて解説しています。
まず最初に気づくべきことは、読書が単なる趣味ではないことです。もし芸術やスポーツにかけるだけの時間を読書に使うと、社会人になってから読解力や文章力がなくて困ることが少ないということです。
読書に時間を投資することは、社会人として働くことを考えると、非常に有効な方法です。
読書は時間の有効活用|時間を作る方法!驚きの恩恵がある

読書をすることの重要性に気づき始めると、「みんな何時間本を読んでいるのか」「どうやって時間を確保してつくっているのか」「読書はやっぱり時間がかかる」など、読書時間について気になることが、思い浮かんできます。
一つずつ解説をしてまいります。基本的に、読書をすることには数年後の結果から考えると、他の何よりもノーリスクでハイリターンの投資です。社会人になると気づきますが、社会人として成功していくには、学歴よりも社会に出てからどれだけ読書をしたかで決まります。
有名大学の出身者でも、読書をしない人は読解力は低く文章力もありません。社会人として活躍できる能力は、読書によって脳を鍛えることで高まるものです。
読書時間は平均何時間|読書時間の調査(小学生〜大学生・社会人)
読書時間に平均何時間使っているのか?調査機関や対象となる年代によって差異がありますので、あくまでも目安として紹介でします。
学研教育総合研究所では、小学生・中学生・高校生を対象に過去(2018年)に1週間の平均時間について調査を行なっています。学研の調査によれば、小学生の1週間の平均読書時間は2時間14分、中学では2時間1分、高校では1時間54分とされています。1日に換算すると約16分です。
また大学生協の調査によれば、大学生が1日に読書にあてている時間は平均で約28分です。
社会人については、オンラインサイトhontoが行なった20代〜40代の男女アンケート調査では、男性では20代が39分で最も多く、女性では30代が34分で最も多いという結果があります。
それぞれの調査が、同一条件ではなく調査対象も異なりますので、比較することはできませんが、一つの目安として参照することは可能です。大学生から社会人では、大まかな目安として1日あたり30分程度と見ることができます。
ですので、後述するスキマ時間を集めて、毎日1時間程度の読書時間を作って本を読んでいくと、数ヶ月か数年後には本を読まない人との差は明確になります。

読書に最適な時間帯
読書をすることで人が最も影響を受けることは、かなり大きく分けると2つです。1つは知識情報をインプットすることです。もう1つは、脳を活性化することです。
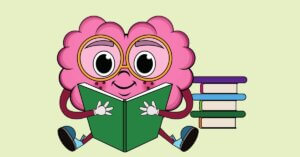
これら2つの点に基づいて考えると、読書に最適な時間帯は、朝〜午前中の時間帯といえます。
人の脳は、睡眠によって昨日の情報は整理されており、朝には新しい情報を受け入れやすくなっています。実は、試験勉強等も、夜遅くまで頑張るよりも、朝1時間でも2時間でも早く起きて勉強する方が、効果的なのです。
おすすめする時間帯は、「朝起きた直後」「通勤時の移動時間中」です。この時間に読書ができる環境を整えるのがおすすめです。
また夜に勉強をしたり、人によっては就寝前の時間帯が有効とする説もあります。しかし特に就寝前に得た情報は、脳に定着しやすいということには個人差があります。
さらに寝る前に読む本によっては、交感神経優位になってしまい、質の良い睡眠が取れなくリスクがあります。面白すぎない本を選ぶほうが、良い睡眠へと進んでいきます。

読書は時間の無駄という誤解|驚きの恩恵がある
読書は時間の無駄と考える人がいます。確かに読書をするには、一定の時間が必要とされます。しかし読書で得られる影響には驚きの恩恵があるのです。
逆に言えば、読書をしないでいるとその恩恵を受けることはできません。
読書をすることで受けられる恩恵にはいくつもありますが、代表的なものは以下の効果が恩恵としてあるとされています。
・読書をすることで脳が活性化し、記憶力や集中力、判断力がアップする
・読書をすることでストレスが軽減し、睡眠の質も向上する
・読書をすることで想像力や創造力が豊かになり、表現力やコミュニケーション力が向上する
・読書によって知識や教養が増えて視野が広がる
さらにもっと現実的な恩恵があります。それは国語力が向上することです。読む力(読解力・語彙力)・書く力(文章力)・考える力(思考力・判断力)といってもよい能力です。
読書以外でも勉強すれば身につけることができる能力ですが、読書をすることで自然と向上していくのです。読書をしないままに社会人になった方は、読解力・語彙力・文章力が身についてないために、仕事で苦労するのです。
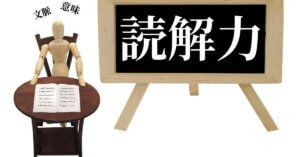
ですので読書は時間の無駄ではありません。ただし時間の無駄にしてしまっている人はいます。それは読書をしても、自分の行動に活かしてみようとしない人です。
読書の時間がないという人は誤解している
読書は時間がかかるという方は、おそらく「読書は趣味でしかない」という間違った認識を持っています。
確かに読書をすると時間を使います。しかし特に社会人になってからの読書は、「勉強という投資」をしているのです。単に時間を消費しているのでありません。数ヶ月後か数年後に成果を出すための勉強という投資をしているのです。
また他にやりたいことがあるから、読書にかける時間がないという方もいますね。一方で、芸術やスポーツに学生時代から一生懸命に取り組む人もいます。しかし実際に、芸術やスポーツで食べていける人は、ほんのひとつまみの狭き門でしかありません。その道のプロになれなかった人たちは、心と体を鍛えられたことが成果かもしれません。
読書の場合は、考えて読書をして、脳を鍛えて、仕事に役立てようとした人を、仕事ができる人間に成長させてくれます。上級管理職や経営側の人になっていく人たちです。芸術やスポーツで成功するよりもはるかに確率が高いです。
そして読書は時間がかかるから・読書する時間はないと言っていた人たちは、数年後に読書をしてきた人たちの部下になります。それが読書という投資の結果です。
読書時間は一冊読むのにどのくらいかかる
一般的に日本語の文章の場合、読書の速度は1分間に400字〜600字とされています。仮に読書速度を1分間に500字とするなら、本を一冊読むのにかかる時間は、どのくらいかかるのでしょう。
本の文字数は一般的に、文庫本で10万字〜12万字、新書で8万字〜12万字とされています。計算すると、文庫本一冊を読み終えるのにかかる読書時間は、200分から240分が目安となります。つまり3時間から4時間というところです。
一つのかたまりの時間として考えるとそれなりの長時間になります。しかし後述するスキマ時間を使っていくと、1日に1時間の読書時間を確保することは、そう難しいことではありません。個人差はあるにしても、1週間に1冊〜2冊の読書をすることはとても現実的であることがわかります。
読書時間を作る方法
「読書する時間がない」「読書時間の確保が難しい」と言っている人は、前述の読書を趣味だと思って勘違いしている人たちです。実際、読書する時間がないと言っている人がSNSをする時間はあるのです。これは優先順位の問題です。
とはいえ、毎日決まった読書時間をまとめて30分〜1時間ほど確保することが、実際難しいという人も少なくありません。
読書時間はスキマ時間から作る
読書時間の確保で最も有効なのは、「スキマ時間」の活用です。
何かのスキマの時間にいつでも読書ができる状態にしておくことがおすすめです。紙の本であれば、カバンの中だけではなく、家のリビングやベッドの脇、トイレの中においても良いです。
家の中でも、何かの作業や合間のスキマの時間があるはずです。社会人や学生であれば、スキマ時間の代表は、通勤通学の移動時間です。スマホでSNSチェックやゲームの時間を半分にするだけで、1日に読書にあてられるスキマ時間はすぐに30分や1時間になるはずです。
読書の時間は時間帯から作る
読書の時間は時間帯に割り当ててみることでも作ることができます。例えば朝起きてすぐの時間や寝る前の時間が有効です。中でも「朝読書」は学校の取り組みでも行われている学校もあり、睡眠をとったことで頭がリセットされていて、読書には最適の時間とも言われています。

読書以外の時間を減らすことで作る
日常の中には必要以上に時間をかけてしまっていることや、何となくテレビを見て過ごしてしまっている時間などが散らばっています。特に楽しみにしていたテレビ番組ではないのに惰性的に見ているテレビ時間をやめてみて下さい。
1日の中に30分〜1時間程度の目的なく過ごしてしまっている時間がないでしょうか。それらの時間を減らすことで読書の時間は作ることができます。
kindleなら読書時間の目安がわかる
スマホにKindleなどの読書アプリをインストールしておき、どこでも読める状態にしておくのも良いです。現在読んでいる本をあと何分で読み終えるのかの目安を表示してくれる機能があります。
また「その他」>「読書の詳細情報」から読書記録を表示してくれます。表示されるのは連続読書時間についてです。(Kindleペーパーホワイトにはこの機能は確認できませんでした)

まとめ
読書時間の平均はかなり少なめに感じたのでないでしょうか。実は日本人は、世界の先進諸国の中でも本を読まないことでトップクラスなのです。
ですので、読書時間を平均的な30分ではなく、毎日1時間以上にするだけで未来は変わります。大学に入るまでは勉強する人が多いです。しかし社会人として順調にやっていけるためには、学歴は残念ながらあまり関係がありません。むしろ社会人になって、どれだけ読書をしているかが、大きく影響しているのが現実です。
関連記事一覧
- 読書
- 読書のやり方に関する注意のまとめ
- 読書の姿勢を理想的にすれば集中力アップし疲れは低下する
- 寝ながら読書の姿勢では集中が続かないし眠くなる
- 目が悪くなる原因は読書ではなく姿勢と環境
- 読書は時間の有効活用・時間を作る方法!驚きの恩恵がある*当記事
- 読書のBGM|聞く音楽はクラシックかジャズが集中できる
- 読書習慣を身につけよう!誰でも始められる読書習慣化のコツ
- 読書には場所が必要|読書場所問題は発想を変えれば解決
- 社会人に読書が必要な理由|本読んでないと出世する人にならない
- 読書の方法が正しければ人生が変わり始めていきます
- 頭に入る読書の仕方はノートしだい
- 読書率の低下|地域(県)別・年代別・世界との比較
- 読書家の世界|有名人の読書事例から個性的な楽しみ方まで
- 読書家あるあるエピソード|いくつ共感できる?
- 東京で読書会を探している人におすすめの記事
- 読書会オンラインの魅力と成功のポイント
- 読書会のやり方:社内および大学での効果的な実施方法と成功の秘訣
- 読書初心者におすすめのジャンルと選び方|自己啓発〜ミステリー
- 読書の仕方完全ガイド:基本から応用まで