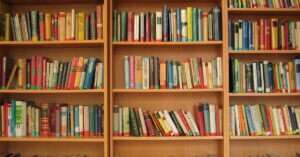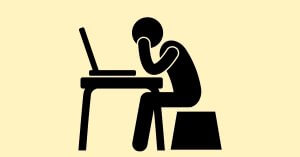言葉の力は大きいですね。私たちは日常でコミュニケーションを取る際に、正確で適切な表現が求められます。語彙力を高めることは、思考を豊かにし、自分の意見や感情を的確に伝える手助けとなります。
年代によって適したアプローチがありますが、読書や会話、書き物を通じて新しい単語や表現を身につけることが大切です。これによって、より多彩なコミュニケーションが可能となり、人生がより充実したものになるでしょう。無理なく楽しんで語彙力を養い、豊かな言葉で世界とつながりましょう。
語彙力をつけるにはどうするのか|年代で対策はどう違う

語彙力向上の方法は年代により異なります。若い世代は読書や英語映画が効果的。
社会人はビジネス関連書籍やコミュニケーションを通じて。中高年は趣味に関連する本や学びの場を活用しましょう。適切な方法で楽しみながら語彙力を伸ばせます。
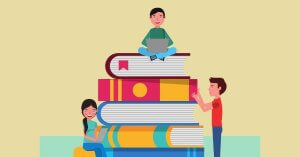
語彙力を向上させる全般的な方法
- 読書を積極的に行う: どんなジャンルでも良いので、興味を持てる本を読むことが重要です。小説、エッセイ、記事、専門書など、様々なテキストを通して新しい単語や表現を学びましょう。
- 単語帳やアプリを活用する: スマートフォンアプリや単語帳を使って新しい単語を学ぶことができます。日常的にチェックしてみましょう。
- 定期的な書き物を行う: メモ、日記、エッセイなどを書くことで、新しい表現を使う練習をしましょう。
- 会話を大切にする: 誰かと話す機会を増やすことで、実際のコミュニケーションで使える語彙を増やすことができます。
- 文脈を理解する: 新しい単語や表現を学ぶ際に、その文脈や使い方も理解することが大切です。一つの単語が複数の意味を持つこともあるため注意が必要です。
若年層の語彙力の現状と課題
若年層の語彙力の現状としては、SNSやメッセージアプリなど、短文でのコミュニケーションが主流となっているため、表現力や正確な単語選びなどが不十分な場合が多いと言えます。また、若年層は学校教育での語彙力向上が重視されている場合が多いため、自己学習に取り組む機会が少なく、自分から語彙力向上に取り組む意欲が低い場合もあります。
課題としては、言葉の表現力が不十分なため、自分の考えや意見を相手に伝えることが難しい場合がある点や、高度な知識や技術を持つ分野でのキャリアアップが難しい点が挙げられます。
若年層におすすめの語彙力向上方法
若年層におすすめの語彙力向上方法について、以下のような方法があります。
- 読書をすること:幅広いジャンルの本を読むことで、新しい言葉に触れ、語彙力が向上します。
- 英語学習をすること:英語の勉強をすることで、日本語とは異なる表現や単語を学ぶことができます。
- クロスワードパズルやクイズなどの脳トレをすること:頭を使うことで、新しい言葉を覚える力が高まります。
- 会話の中で積極的に新しい言葉を使うこと:周りの人に影響されず、積極的に新しい言葉を使うことで、語彙力を向上させることができます。
中年層の語彙力の現状と課題
中年層とは、年齢的には40代から60代の人たちを指します。彼らが抱える語彙力の現状としては、若年層と同様にSNSやテキストメッセージでのコミュニケーションが増え、文字数制限やスマートフォンの自動変換機能によって簡略化された言葉遣いに慣れてしまう傾向があることが挙げられます。また、仕事や家庭の忙しさから、読書や外国語学習といった語彙力を鍛えるための時間が取れないケースも少なくありません。
中年層におすすめの語彙力向上方法
語彙力向上の対策として以下のような方法がオススメです。
- 洋書を読む:英語圏の文学作品やビジネス書など、自分が興味を持てるテーマの洋書を読むことで、新しい単語や表現を学ぶことができます。
- オーディオブックなど聞き流しアプリを利用する:通勤や家事の合間に、英語のニュースやラジオ番組を聞き流すことができるアプリを利用することで、リスニング力とともに語彙力の向上が期待できます。
- 趣味を見つける:自分が興味を持てる趣味を見つけることで、その分野に関連する単語や表現を学ぶことができます。例えば、車に興味がある場合は自動車関連の書籍やブログを読み、新しい単語や表現を覚えることができます。
- 知人との会話を増やす:中年層になると、仕事や家庭の関係で、自分と同じ年代や職種の人との交流が中心になってしまうことが多いですが、異なる世代や職種の人との会話を増やすことで、新しい言葉や表現に触れる機会を増やすことができます。
高齢者の語彙力の現状と課題
高齢者は語彙力の低下によって、表現力の欠如やコミュニケーションの困難、または単純な言葉の忘れがちさを感じています。特に、高齢者は年齢とともに語彙力が低下し、語彙レベルが教育水準に比例して低下することがわかっています。また、高齢者は一般的に、語彙力向上のための新しい言葉や情報に接する機会が少なくなる傾向があるため、語彙力を維持することが難しくなることが指摘されています。認知症といった病気が進行すると、語彙力の低下がより深刻になることがあります。
語彙力については、67歳頃に成長のピークがあることがわかっています。
ただ当然ながら、成長のためには脳に良い刺激が必要です。そして、使うことが必要です。たくさんのインプットがあったとしてもアウトプットが無ければ、語彙力の質は高まりません。
高齢者の語彙力向上のための対策
以下のような対策が考えられます。
- 音読や読書を通じて、新しい単語を覚える。
- 言葉遊びやクイズ、パズルなどを通じて、言葉に触れる機会を増やす。
- 語彙レベルが近い友人や知人とコミュニケーションを取ることで、新しい単語や表現を学ぶ機会を増やす。
- 趣味や興味関心に基づく習い事やイベントに参加し、新しい知識や情報を得ることで、語彙力を維持する。
ただし、高齢者は他の年代以上に個人差が大きい場合があります。状況によっては、専門家のアドバイスを仰ぐことも重要です。
語彙力をつけるには本を読むことはいい影響がある
語彙力をつけることを考えると、本を読むことをイメージすると思います。
そこで、どんな本を読むと語彙力をつけるのにプラスになるのかを、解説します。語彙力をつけるように意識して読む場合は、いつも読んでいないジャンルの本を選ぶとよいです。これは人との出会いにも同じことがいえます。いつもと同じジャンルや同じ著者の本を読んでいるのでは、いつもと同じメンバーと話をしている状況と同じです。
表現される言葉や文章は、すでによく知っている言葉である可能性が高いのです。苦手ジャンルにまで手を伸ばさずとも、普段に積極的には読まないというジャンルの本を読むと語彙力をつけるには効果的です。いつものジャンルや好きな著者の本だと、新しい言葉や表現が登場してくる可能性が低いからです。
語彙力をつけるには小学生の場合どうすればいい
全国学校図書館協会の読書調査によれば、小学生4年〜6年は読書率は約95%、読書量も平均月に11冊と、非常によく本を読んでいることが分かります。実はどんな本を読んでいるのが読解力に影響することも分かっています。
アメリカとイギリスの子どもに対して、本のジャンルと読解力に関する調査が行われています。フィクション・ノンフィクション・新聞・雑誌・コミック(マンガ)の5つのジャンルを用意して、本を読んでもらいました。
その結果、一番読解力が高かったのは、フィクションを読んだグループでした。逆の結果になったのは、コミック(マンガ)を読んだグループだという結果があります。読解力が高いということは、言葉の意味を理解しているのですから語彙力も高いことになります。
これらのことから、小学生に語彙力をつけるには、フィクション(物語・小説)を読ませることが良い方法とかんがえられます。マンガはマイナス作用も確認されていますが、マンガを禁止するのは難しいと思います。マンガを読む分、さらに物語を多く読むようにするのが良い方法になります。
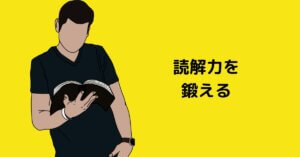
語彙力をつけるには 高校生
高校生の場合、小学生・中学生の頃と比べると、読書率と読書量が大きく減少します。
全国学校図書館協会の調査によれば、小学生の読書率は約95%ほどあります。中学生になると85%程度に落ちます。しかし高校生になると、読書率は50%近くまで大きく落ちます。読書量にも明確な差があります。小学生は一ヶ月の読書量が非常に多いです。平均で11冊前後あります。しかし高校生になると、読書をする人の割合は半減します。読書量も読む人の平均で1.5冊ほどに減少します。読書率と読書量の低下が影響していることは明確です。
OECDのPISA(学習到達度調査)の結果(世界の15歳が対象)、日本人の読解力が低下していることが分かりました。日本の人の読書率が低い(先進国17ヶ国中15位)ことは、GfKの調査でも明白です
高校生の場合、語彙力をつけるには、まず読書率を上げて、読書量を増やすことです。中学生に比べると、急に減少しますので、読書量を増やすだけでも相対的に、語彙力をつけることができます。

語彙力をつけるには 大学生
社会人になるのが目の前に迫っている大学生は、語彙力が無いボキャブラリー不足の状態から、脱出しておいたほうがいいです。
そのまま社会人になってしまうと、上司との会話の中で「ヤバい」「スゴい」などSNSで使い慣れた形容詞の言葉が出てしまいます。万が一顧客との会話の中で、「ヤバい」「スゴい」などの言葉が出てきてしまいます。実際の経験では、社外の人と会う場面に同席をさせると空気が凍りつくことがあります。
語彙力をつける方法は、大学生の場合、できることがいくつもあるのですが、現実的に考えると難しいこともあります。本来は、SNSとマンガの量を減らすのが良いのです。しかし友達との関係性を考慮すると、現実的には難しいです。
読書が単なる趣味だという誤解に早く気づくことです。読書は物語を読むことでさえも、社会人になってからの基礎力となる語彙力をつけるには重要なことなのです。
また「ヤバい」などの形容詞をほかの言葉に言い換える練習もしておくべきです。社会人になって、大事な場面で言わないようにできると考えている方がいるとするとそれは甘い考えです。緊張する場面には、往々にして、体にしみこんでいる習慣的な言葉が出てしまうからです。

語彙力をつけるには 社会人
「語彙力がないまま社会人になってしまった人へ」という本を知っているでしょうか。
小学生と中学生の頃には、かなり読書をしていた子供たちが高校生・大学生になると読書を単なる趣味にしています。そして単なる趣味と考えると、時間がとられるし、めんどくさいと感じてしまい、ほかのことに時間を使いたくなります。。
その結果、約半分の人が読書をしなくなります。そのため、語彙力(言葉の力)は中学生でストップしたまま社会人になってしまいます。本書には社会人としての「知性」と「教養」という言葉が出てきます。しかし語彙力が無いまま社会人になってしまった人は、中学生でストップした状態です。
社会人としての「知性」と「教養」を求められても、厳しいです。企業に入ると語彙力が無いことで厳しい洗礼を受けます。有名大学卒の学歴ある人も同じです。社会人の「知性」と「教養」が無い状態が、数ヶ月か数年続きます。その間は、言葉の意味を知らないことで、仕事の指示内容も理解できずに、仕事ができない人になってしまいます。
ここで気づいて、奮起する人もいます。しかしそのままの状態で中堅社員として落ちこぼれながら進んでいく人も少なくありません。語彙力をつけるには面倒がらずに本を読んで知らない言葉を調べて覚えて、話すこと書くことに使うことです。
まとめ
語彙力は、人間の関係性の中で重要です。語彙力が無ければ、ワンパターンの言葉しか使えないだけでは無く、相手が言っていることが理解できないですし、伝えたいことをちょうどいい言葉で伝えられないと言うことが起きてしまいます。
まるで、言葉が通じない外国にいるような状況です。もしある日から、言葉の通じない世界に目覚めたとすれば、本を読んで知らない言葉を調べて覚え、そして話したり書いたりするはずです。
語彙力が無いとそんな経験をすることになります。早い時点で気がつけば、本を読み始めることくらいでも対策できるモノです。遅くならないうちに、手を打つべきと思います。
関連記事一覧