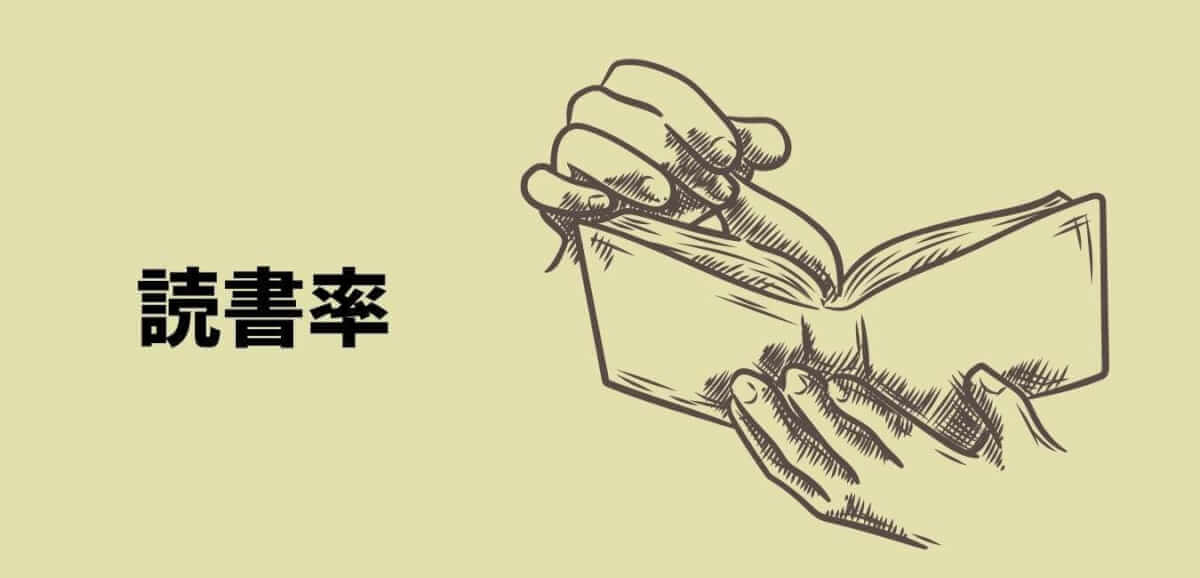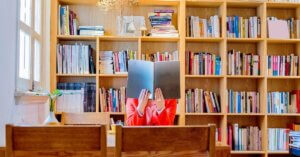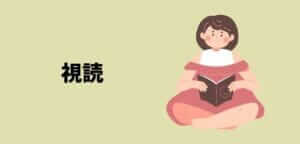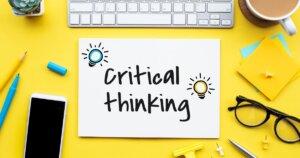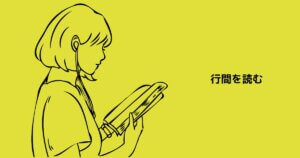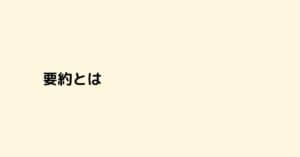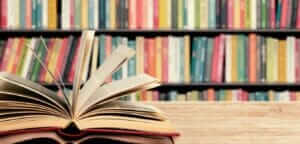日本はかつて、書籍出版大国として知られていましたが、現在ではその読書習慣は大きく変わってしまっています。
最新の調査(日本財団)では、読書が好きな人は6割近くに上りますが、嫌いな人も約1割に留まり、その間にいる人たちは、読書に対してどちらかといえば無関心という傾向があります。
読書率が低下したのはSNSとスマホが原因とされていますが、海外を見ても日本はとても読書率が低いです。
原因は他にありそうな気がしませんか。また中高生の読書率も低下し、子どもたちの読解力が下がっていることが話題になったことがあります。
さらに子ども以上に大人の読書率の低下と読解力の低下の方が、企業では問題になっています。逆に、社会人になって読書量を増やし勉強している人にとってはチャンスの時と言えるかもしれません。
他に関連する情報もまとめた「読書方法のまとめ」も併せて参考にしてみてください。
読書率の低下|都道府県別・年代別・世界と日本
近年、スマートフォンやパソコンなどの普及により、多くの人々がオンライン上で情報収集やコミュニケーションを行うようになりました。しかし、一方で、本を手に取って読む機会が減少しているというデータがあります。
特に日本の若年層において、読書離れが進んでいるとの指摘もあります。読書に関する読書量・読書率などの数値は、すでに何年もの間、低下を続けています。また都道府県別に見ると、読書率が高いとされる都道府県と、低いとされる都道府県があることが分かります。
読書率の低下の原因
読書率とは、ある一定期間内(通常は1か月)において、何らかの書物(雑誌、新聞、小説など)を読んだ人の割合を示す指標です。一般的には、国や地域の教育水準や文化レベル、経済格差などと関連しています。読書率は、読書自体の普及状況を示すだけでなく、その社会的・文化的な背景にも着目することで、社会的課題や政策立案につながるデータとなります。
読書をしない人の割合を指して、不読率という数値データで表されている場合もあります。
読書率の低下にはさまざまな要因がありますが、一般的に原因とされているのは次の4つです。
1)スマートフォンやタブレット端末の普及:これらのデバイスを持っている人は、常にインターネットにアクセスしているため、本を読む時間が減少しています。
2)テレビやインターネットの娯楽の充実:多くの人は、テレビやインターネットで映画やドラマを見たり、音楽を聴いたりして時間を過ごすようになっています。
3)読書への意欲の低下:スマートフォンやテレビなどの娯楽が充実する中、読書に興味を持つ人が減少しているため、読書率が低下していると考えられます。
4)教育環境の変化:教育現場でも、情報通信技術の進化に伴い、教材がデジタル化されるなど、紙媒体から電子媒体への移行が進んでいます。
読書率の低下は中学生に顕著に現れ、高校生となるとさらに低下します。低下の原因は、SNSやスマホの進化だとする説がまことしやかにあります。

学研教育総合研究所の調査(古くは1946年から読者はがきがベース、2010年からインターネット調査)によれば、小学生の読書量が30年前に比べると、半減しているようです。とすると、SNSやスマホの進化だけでもなさそうです。
また、全国学校図書館協会、毎日新聞社、文部科学省、文化庁、民間調査機関など、読書に関する調査は、毎年のように行われており、調査対象者により、多少前後するものの、日本全国の読書に関する読書量の数値・読書率に関する数値は、いずれも年々低下をしています。
未来の日本を考える上では、ピンチでありますから、関係各所では打開策を検討していますが、効果ある策は今のところ、目立ったものはありません。
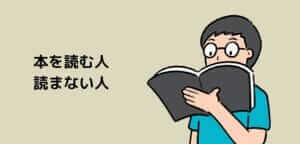
読書率が低下を続けると
読書率がこのまま低下を続けると、様々な問題が引き起こされる可能性があります。
まず、読書は知識を深めることができる貴重な手段の一つであり、読書から得られる知識や情報が減少することによって、個人の学習能力や社会での活躍に影響が出る可能性があります。また、情報化社会において、読解力や批判的思考力がますます重要になっているため、これらの能力の低下も懸念されます。
さらに、読書離れが進むことで、書店や図書館の閉鎖、書籍出版の減少などの経済的影響も懸念されます。このような問題が起こらないためにも、読書率の低下を食い止めるための取り組みが必要であると言えます。
読書率低下の問題で表面的に取り上げられるのは、多くの場合、中学生・高校生・小学生です。しかし、目の前の問題として最も大きいのは大人の方です。読書しない大人の問題を取り上げるメディアは少ないですが、企業内では大きな問題になっています。社会人の読書率が低いことは文化庁のデータからも明らかです。「国語に関する世論調査」の「Ⅳ読書について」を参照ください。
関連する他の情報などをまとめた「読書方法のまとめ記事」もあわせて参考にしてみてください。
多くの社会人は読書を子供に必要なものと考えているのかもしれない
一部の社会人は、読書を人生や仕事に役立てています。しかし多くの社会人は、読書が必要なのは子供だと考えている傾向があります。
前述の文化庁のデータによれば、読書が必要と考える年代の問いに、「年齢に関係なく必要」という回答は約20%しかいません。60%の回答が10歳以下を示しています。また70%近い人が、読書量が減っていると回答していることも気になります。
しかし、読書は子供だけでなく、大人にとっても多くのメリットがあります。例えば、読書はストレス解消になったり、自己啓発に繋がったり、語彙力や知識の増加につながることが研究から明らかにされています。ですので、社会人にとっても読書は非常に重要な習慣であり、読書を促進する取り組みが必要です。
社会人の読書率の低下は非常に深刻
企業の社員教育の現場にいて感じることは、「読書しない人」と感じることが増えています。なぜかといえば、社内のルールや顧客からの連絡内容、取引先とのメールの内容を、自分独自の理解・解釈をして、トラブルを起こす人が増えてるからです。
まずいのは、本人にはその意識(理解不足)がないことです。さらに、会社員は毎日様々な書類を書きますが、中学生レベルの文章しか書けない社会人も増えています。
戦略書や計画書などはとても無理です。報告書すら書くことが難しい人が増えています。
読書をしない人と接していて感じることは、驚くほど、「言葉を知らない」ことです。そのために、例えば業務上の注意やアドバイスをされても、相手が話していることを理解できないのです。相手が顧客や取引先となれば、会社の損失が発生する可能性もあります。
ですので、ごく普通に読解力・文章力があるだけの社員が、優秀にすら見えてきます。
毎月3〜4冊の本を読んでいる人はチャンスです。その状況を維持して、「行動」のギアを少し上げれば、上司から、チャンスを与えられるようになります。本を読んで得た学びを仕事に活かせる場面がないかなという意識を持って行動していれば、チャンスは発生します。
大事なのは、「本から学んだことを、仕事に活かせる場面がないか」と考えながら待つことです。
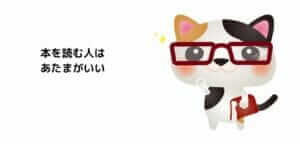
読書率を都道府県別にランキング
文科省の全国学力テストには、子どもの生活習慣全般のアンケートがあります。その結果から中学3年の読書率の都道府県別割合がわかります。ただし、都道府県によって調査の方法が異なるため、他の調査によって結果が異なる場合があります。
読書率の上位都道府県の読書傾向
読書率が高い地域(平均は64.2%)は以下の通りです(2017年)。一般的に、大都市部では読書率が低く、地方部では比較的高い傾向があります。これらの都道府県では、読書に対する関心が高く、図書館の利用率も比較的高いとされています。また、地域によっては図書館の蔵書数が多く、読書に対する環境が整っていることが要因の一つとして挙げられます。
1.秋田県 75.1%
2.鹿児島県 72.8%
3.山梨県 71.5%
4.福井県 70.9%
5.岩手県 70.8%
読書率の下位都道府県の読書傾向
読書率が低い地域は以下の通りです。
下位にランクインした都道府県の多くは、農業や漁業などの第一次産業が盛んな地域が多く、都市部に比べて情報にアクセスする機会が少ないため、読書の機会が少ないことが一因とされています。また、高齢化が進んでいる地域も多く、高齢者の読書離れが影響している可能性があります。
ただし、地域によっては、都市部に比べて自然に囲まれているため、アウトドアな活動が盛んであったり、地域に密着した文化が残っているなど、それぞれの地域の特色を活かした生活が営まれている場合もあります。
1.大阪府 54.4%
2.和歌山県 56.6%
3.石川県 56.8%
4.大分県 57.2%
5.熊本県 57.4%
読書率を年代別の傾向
民間インターネット調査機関マイボイスコムが2019年に行なった1ヶ月の読書量についての調査(20代〜60代、各年代で男性500名、女性500名を対象にインターネット調査)によれば、1ヶ月に1冊以上の本を読んでいる人の割合=読書率は以下の通りとなっています。
読書好きの人は、紙の本と電子書籍を時と場合で使い分ける傾向があります。あくまでも大まかな目安としては、紙の本と電子書籍を合計しても、月1冊も読まない人は、45〜50%程度いるものと考えられます。
紙の本を1ヶ月に1冊以上読んでいる割合 50.2%
20代 47.7%(1冊22.6%、2〜3冊15.6%、4〜5冊3.4%、6冊以上6.1%)
30代 45.6%(1冊19.4%、2〜3冊15.9%、4〜5冊3.7%、6冊以上6.6%)
40代 51.2%(1冊22.4%、2〜3冊16.8%、4〜5冊2.7%、6冊以上6.9%)
50代 53.2%(1冊23.1%、2〜3冊17.5%、4〜5冊5.3%、6冊以上7.3%)
60代 55.9%(1冊22.0%、2〜3冊20.6%、4〜5冊4.9%、6冊以上8.4%)
電子書籍の本を1ヶ月に1冊以上読んでいる割合 19.7%
20代 28.9%(1冊8.8%、2〜3冊9.8%、4〜5冊4.1%、6冊以上6.2%)
30代 26.5%(1冊8.2%、2〜3冊9.5%、4〜5冊3.0%、6冊以上5.8%)
40代 19.8%(1冊6.6%、2〜3冊5.7%、4〜5冊3.0%、6冊以上4.5%)
50代 14.9%(1冊5.2%、2〜3冊4.5%、4〜5冊1.4%、6冊以上3.8%)
60代 8.5%(1冊3.7%、2〜3冊2.3%、4〜5冊1.1%、6冊以上1.4%)
年代別の読書率の推移
年代別の読書率の推移については、以下のような傾向があるとされています。
- 若い世代ほど読書率が低く、特に10代の読書離れが顕著です。
- 一方、40代以上の世代は比較的高い読書率を維持しています。
- また、女性の方が男性よりも読書率が高く、年齢に関係なく一貫して高い傾向にあります。
ただし、これらの傾向は全体的なトレンドであり、個人差や社会的背景によっては異なる場合もあります。
各年代の読書傾向について
各年代によって読書に対する傾向があります。
10代以下の若年層は、スマートフォンやタブレットを使ったインターネット閲覧が主流となっており、書籍よりもオンラインでの情報収集が多い傾向にあります。
20代前半の若者は、仕事や学業での勉強のために書籍を読むことが多く、また自己啓発書や趣味に関する書籍も読む傾向があります。
20代後半から30代にかけては、仕事や家庭の忙しさから書籍を読む時間が減少し、読書離れが進む傾向があります。
40代以降は、仕事や家庭の時間的余裕が生まれ、読書の時間を確保することができるため、再び書籍を読む人が増える傾向があります。ただし、文化庁のデータにもありますように、絶対数は非常に少ない傾向にあります。
読書率の世界と日本の比較
読書率を表す調査は、複数の調査機関が独自に行なっています。本記事では、その中の一つを紹介します。どの程度の割合で読書を行なっているのかという「読書頻度」について調査されたものです。
読書頻度のランキング|GfKジャパン(17カ国22,000人のネットユーザーに2017年調査実施)
| 毎日ほぼ毎日 | 週1回 | 月1回 | 合計 月1回以上読む | ||
| 1 | 中国 | 36% | 34% | 16% | 86% |
| 2 | イギリス | 32% | 24% | 16% | 72% |
| 2 | スペイン | 32% | 25% | 16% | 73% |
| 4 | イタリア | 30% | 26% | 19% | 75% |
| 4 | アメリカ | 30% | 25% | 16% | 71% |
| (中略) | |||||
| 15 | 日本 | 20% | 24% | 19% | 63% |
日本の読書率と世界との比較
日本の読書率と世界との比較については、国際的な調査結果によって異なりますが、一般的には日本の読書率は低いとされています。
例えば、2016年に発表されたOECD(経済協力開発機構)の調査によると、15歳の平均読書量で日本は31カ国中28位、PISA(国際学力調査)でも読解力の平均得点で上位に入る国々に比べて、日本は低い評価を受けています。
ただし、年代や読書対象の違いなどによって、結果は異なる場合があります。

まとめ
読書率の低下のことで若者がターゲットにされますが、現実は中高年の人も本を読んでいる人は、多いと言える状況ではありません。また世界の読書頻度に関する調査では、日本人の読書頻度は平均以下であることも判明しています。
フィンランドのように、国が読書を推進しているケースもあります。また、企業や自治体が読書推進に力を入れることも重要です。しかし、まずは個人レベルの取り組みが重要です。
読書に対する誤解を解いて、仕事や人生が改善するきっかけになるよう読書体験を深めるべきです。
関連記事一覧