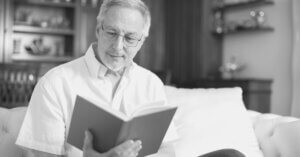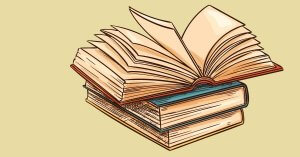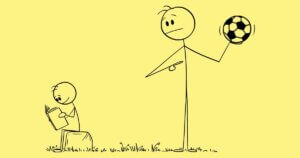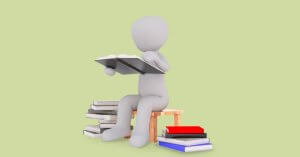日本人の不読率はかなり高いです。
調査によりますが、いずれの調査結果でも、約4割から5割近い人が本を読まない人とカウントされています。調査によっては、月に一冊まで読んでいない人を読まない人にカウントしている場合もあります。文化庁の平成30年の「国語に関する世論調査」では、「読まない」と回答している人が47%です。
この結果を現実において考えると、困ったことになります。つまり、どこの会社にも本を全く読まない人がいるということです。そして、ある日クレームやトラブルに発展するのです。それらの現象は、大企業でも中小企業でも同じです。
なぜかと言いますと、本を読むか読まないかは、学歴とは関係がないからです。実務に影響するのは学歴ではなく、本を読んで身につけた知識や能力によるものです。
本を全く読まない人は話を聞いていても理解はしてない
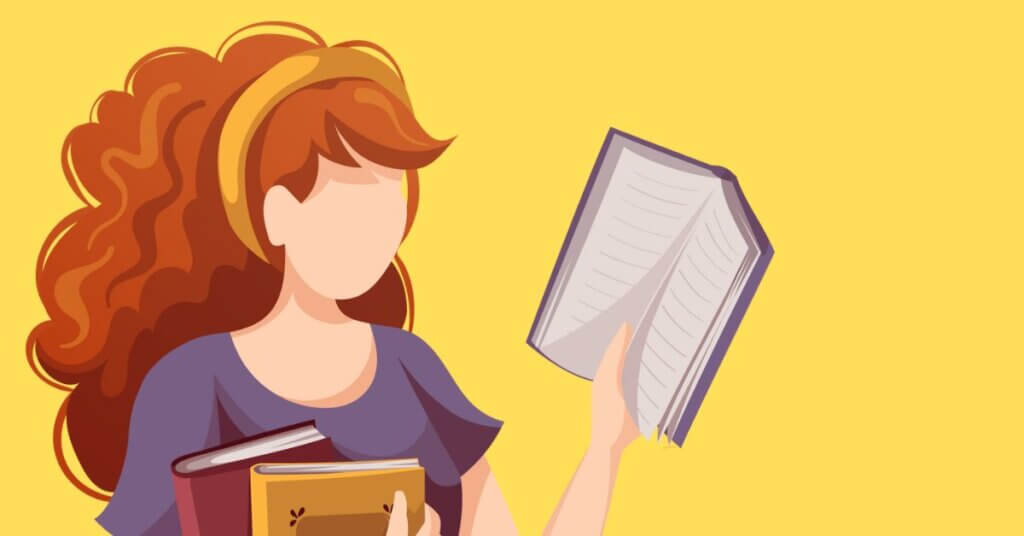
どこの会社にもありがちな会社内の風景に、「上司に注意されている部下」という状況があります。
上司が優秀な人ばかりなら、この風景も違うものになるかもしれませんが、上司の中にも本を読まない人はいます。最初は穏やかに話している上司が、だんだんと熱を帯びていく場面を見た事がないでしょうか。実はこの状況は、上司の話を理解する能力が低い部下と理解力を考慮して話していない上司との間に起こる不幸ともいえます。
本を読まないことが話を理解する能力に与えている影響はとても大きいのです。例えば次のような影響があるのです。「言語能力が制約されている」「文脈理解が欠如している」「読解力が低い」「情報が制限されている」などです。
本を読まないことが話を理解する能力にどんな影響を与えるか
本を読まないことが影響している点についてさらに詳しく解説します。
言語能力が制約されている
本を読むことは、言語能力を向上させる上で重要な役割を果たします。本を読むことによって、語彙力や文法の理解、表現力などが発展し、豊かな言語リソースが身につきます。そのため、本を読まない人は言語的な制約を抱える可能性があり、他人の話を理解する際に困難を感じることがあります。
文脈理解が欠如している
本を読むことによって、異なる文脈や背景を理解する能力が養われます。本は物語や情報の一貫した流れを提供し、読者に新たな視点や経験をもたらします。本を読まない人は、異なる文脈や背景の理解に欠けるため、他人の話の中で重要な要素を見逃したり、意味を誤解したりすることがあります。
読解力が低い
読書は読解力を向上させる効果があります。本を読むことで文章を理解し、情報を整理し、要点を把握するスキルが養われます。本を読まない人は、読解力の訓練を受けていないのと同じ状態です。そのため、他人の話の内容や意図を正確に把握するのに苦労することがあります。
知ってる情報や知識が少ない
本は知識の貴重な源です。本を読むことでさまざまな分野やトピックについての情報を得ることができます。本を読まない人は、情報の入手範囲が限定されるため、新たな知識や視点に触れる機会が減ります。その結果、他人の話において必要な背景知識や情報が不足し、理解が妨げられる可能性があります。
本を全く読まない人は理解力が低い
本を全く読まない人は、新たに漢字や言葉を知る機会が極端に少ないです。また、人とのコミュニケーションやニュースなどで、意味がわからない言葉が登場しても、わからないままスルーする傾向が強くあります。その結果、いつまでたっても理解力が高まることはありません。
本を読むことで言語能力や語彙力が発達する
本を読むことは、語彙力や文法の理解、表現力を向上させるのに役立ちます。本を読まない人は、十分な語彙や文法知識を身につけていないため、他人の話の意味を正確に把握することが難しくなります。
また本を読むことで文章を理解し、情報を整理するスキルが養われます。本を読まない人は、読解力の訓練を受けていないため、他人の話の内容を正確に把握するのに苦労することがあります。
本を全く読まない人は、その人の理解力が低く、人生の中で多くの機会を逃してしまう可能性があります。読書は、知識や経験を得るために素晴らしい方法の1つであり、私たちが成長するために必要不可欠な要素です。本を読むことによって、私たちは新しいアイデアや概念を学ぶことができ、知識や語彙力を増やすことができます。さらに、本を読むことは、論理的思考力を向上させ、ストレスを軽減し、リラックスすることができます。
本を読まないと読解力や思考力は低下する
知識の増加によって、私たちは自分自身の理解を深め、世界をより広く理解することができます。本には、歴史、科学、芸術、文化、哲学などの多様なトピックに関する知識が含まれており、これらの知識を獲得することで、私たちはより多くの視点から物事を見ることができます。また、本を読むことは、語彙力を向上させるための効果があります。新しい単語やフレーズを学ぶことで、より豊かな表現力を身につけることができます。
さらに、本を読むことは、論理的思考力を向上させるために役立ちます。本は、複雑な問題を分析し、問題解決力を高めるためのトレーニングとして役立ちます。また、読書は、ストレスを軽減し、リラックスするためにも役立ちます。読書は、私たちが日常生活でストレスを感じているときに、自分自身を癒すための方法の1つです。
総合的に考えると、本を読むことは、私たちが健康的で充実した生活を送るために必要不可欠な要素の1つです。本を読むことは、私たちが成長し、発展するための重要な手段であり、私たちが自分自身と他者を理解するためのスキルを磨くことができます。したがって、本を読むことを習慣にすることは、私たちが自分自身を成長させ、人生をより充実したものにするために不可欠な要素の1つです。
本を読まない人がコミュニケーションで問題を抱える原因とは
本を読まない人がコミュニケーションで問題を抱える原因として、以下のような理由が挙げられます。
語彙力の不足
まず、本を読まない人は語彙力不足に陥る可能性があります。本を読むことは、新しい単語や表現方法を学ぶことができるため、語彙力を向上させることができます。しかし、本を読まない人は、そのような知識や表現方法を身につけることができず、コミュニケーションにおいて適切な表現をすることができないことがあります。例えば、ビジネスの場でのプレゼンテーションやメールでのやり取りなど、正確な表現が求められる場面で、語彙力の不足は大きな問題となることがあります。
相手からの文章の意図を正確に理解できない
また、本を読まない人は文章理解力不足に陥る可能性があります。本は、様々なジャンルや分野で書かれた文章が存在します。これらの文章は、時には複雑で長いものもあります。しかし、本を読まない人はそのような文章を正しく理解する力を身につけることができず、コミュニケーションにおいて他人の意見を正しく理解することが難しくなることがあります。例えば、ビジネスの場での契約書やリポートの読解など、正確な理解が求められる場面で、文章理解力の不足は大きな問題となることがあります。
相手と共感できることが少ない
さらに、本を読まない人は感性の欠如に陥る可能性があります。本は、様々なストーリーや登場人物、世界観を体験することができるため、感性を磨くことができます。しかし、本を読まない人はそのような感性を養うことができず、コミュニケーションにおいて他人との共感や共通点を見つけることが難しくなることがあります。例えば、趣味や娯楽について話をする場合に、自分が興味を持っていない分野については相手との共感や共通点を見つけることが難しくなります。
適切な返答ができないことにつながる
以上のように、本を読まない人は語彙力不足、文章理解力不足、感性の欠如など、コミュニケーションにおいて問題を抱えることがあります。その結果、相手から発せられたコミュニケーションに対して、適切な返答ができないという状態になってしまいます。
読書を通じて得られる情報や知識、語彙力・読解力・論理的思考能力、コミュニケーションスキルは、相手とのコミュニケーションをより効果的に行うために重要なのです。
本は読まないが他人とのコミュニケーションに問題は起きていないと感じている人は、上記の状況にも気づいていない可能性もあります。
相手とのコミュニケーションで、後で「そういう意味だとは思わなかった」という場面があるのでしたら、それが相手の意図を理解できていない証拠なのです。
本を読まないことは会話で相手にバレてしまいます
本を全く読まない人は、会話をするだけでもその事実が相手にバレる可能性があります。その理由には次のようなことがあります。
本を読まない人は限られた語彙しか持っていないため、会話において言葉の選択や表現の幅が制限されることがあります。相手はそれを察知し、本を読んでいないことに気付く可能性があります。
本を読まない人は多くの場合に知識や情報を持っていません。そのため、会話において特定の話題や知識に関して理解や参加ができないことが相手に伝わるかもしれません。
本を読まない人は、文脈や背景を理解することが苦手です。相手との会話で文脈や重要な要素を把握することが難しくなります。この点でも相手は気づいてしまいます。
以上から、会話をするだけで本を読んでいない人だと相手にバレてしまう可能性は非常に高いのです。それは社会人の場合、仕事の成果や評価に直結する重要な問題となってしまいます。

本を読んで読書レポートを継続的に書くことで、ビジネス力をアップさせることも可能です。現時点で本を読んでいないのであれば、ぜひチャレンジすることをお勧めします。

本を全く読まない人はうなづいていても理解はしてない
もし相手とのコミュニケーションで、相手にうまく伝わらないと感じることが続くようなら、相手は本を読まない人である可能性があります。例え相手が年長者や上司であったとしても、本を読まない人であれば、理解をしていない可能性があります。
本を全く読まない人がうなずいていても、その人が話を理解しているかどうかは保証されません。うなずくことは、相手が話を聞いていることや共感を示していることを示す一般的なコミュニケーションの合図ですが、実際に理解しているかどうかは別の問題です。
本を読まない人は、情報や知識の取得の手段が限られているため、話の内容や文脈を正しく理解するのに困難を抱えることがあります。うなずくことで相手に理解しているように見せようとしても、実際には話のポイントや重要な要素を見逃している可能性があります。
理解力は言語能力や知識の幅と深さに基づいています。本を読むことは、言語能力の向上や幅広い知識の獲得に役立つため、本を全く読まない人は理解力の向上においてハンディキャップを抱えることが多いです。
したがって、本を全く読まない人がうなずいていても、そのうなずきだけでは十分な理解を示しているとは言えません。コミュニケーションにおいて本当に理解したい場合、積極的に質問をしたり、追加の説明を求めたりすることが重要です。また、本を読む習慣を取り入れることで、理解力や知識の幅を広げることができます。
本を全く読まない人は見てる世界が違うので注意が必要
これはコミュニケーションにおいて重要な点です。見えている世界が違えば、コミュニケーションが取れているようであっても、共感もできていませんし、会話の共有もできていない可能性が高いです。
本を全く読まない人は、情報や知識を本から得る機会が制限されているため、彼らが見ている世界や認識している現実は、本を積極的に読む人とは異なる場合があります。この点に注意することは重要です。
本を通じて他人の考えや意見に触れたり、新しい情報を得たりすることで、自身の視野が広がり、多様な観点を理解することができます。しかし、本を全く読まない人はこのような情報や視点に触れる機会が制限されるため、彼らが持つ世界観や認識は限定的な範囲にとどまる可能性があります。「そんなバカな」と思う人がいるかもしれませんが、言葉の意味がわからないということは、そういうことです。
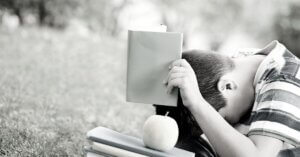
まとめ
本を全く読まない人は、実際にはかなり多くいます。アンケートの結果によれば、4割以上5割未満の人たちが自分が勤めている会社や職場にもいるのです。
普段仕事で話している会話の何割かは理解していないのに、理解している風にいるのです。読解力と語彙力アップのトレーニングをすることと、言葉や漢字を理解していない前提でコミュニケーションをとる必要があります。
ここを対策をを先に行っておけば、トラブルやクレームは少なくなり、成約度合いも高くなる可能性があります
関連記事一覧
本を読まないが頭がいい人は知識力ではなく記憶力か思考力が高い人
本を全く読まない人は話を聞いていても理解はしてない*当記事