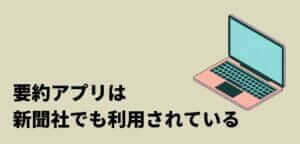読書に集中するために、音楽を聴きながら読書をすることは、多くの人にとって身近な方法の一つかもしれません。しかし、一方で、「音楽が邪魔をする」「音楽を聴きながら読書すると、作業効率が落ちる」という意見もあることも事実です。
そこで、この記事では、読書に音楽を取り入れることがプラス効果になる場合と、マイナス効果になる場合を、科学的な観点から解説します。
音楽が読書に与える影響や、どのようなジャンルの音楽が集中力を高めるのか、逆に邪魔をするのか、などについても触れていきます。
読書に音楽を取り入れることで、より快適に読書を楽しめるようになるためには、正しい知識を持つことが大切です。ぜひ、この記事を読んで、自分に合った音楽の選び方や、音楽と読書のバランスを見つけてみてください。
読書に音楽はプラス効果かマイナスか

読書中の音楽には、プラスとなる効果があるとされています。
音楽には、リラックス効果や集中力を高める効果があり、それが読書に取り入れることで、より快適な読書体験を得られる可能性があります。
一方で、読書中の音楽にはマイナス効果もあることがあります。例えば、音楽が集中力を削ぐ原因となってしまうことがあるため、読書に取り入れる際には注意が必要です。
読書中に音楽を聞くと得られるプラス効果
読書中に音楽を聴くことで、得られるプラス効果はいくつかあります。
まず、音楽がリラックス効果をもたらすことで、読書に集中するための環境作りができます。リラックスした状態で読書をすることで、集中力が高まり、効率的に読書が進められることがあります。
また、音楽が集中力を高める効果もあるため、集中が途切れやすい場合には音楽を聴くことで効率的な読書ができることがあります。
さらに、音楽が読書の理解力を向上させる効果があるとされています。音楽を聴くことで、脳内でDopamine(ドーパミン)が分泌されると言われており、この物質が認知機能や学習能力を高める効果があるとされています。つまり、音楽を聴くことで脳が活性化され、読書の理解力が向上する可能性があります。
また、音楽は感情を呼び起こす効果があります。読書中に感情を表現する場面や登場人物の心情に合わせた音楽を聴くことで、より物語に没頭することができるかもしれません。
これらのように、音楽は読書にプラスの効果をもたらす可能性があります。
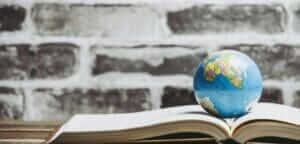
読書中の音楽のおすすめ|聞くと集中力が高まるジャンルは
読書中に聞く音楽で集中力が高まるジャンルは、人によって異なることがありますが、一般的には以下のようなジャンルが挙げられます。
1)クラシック音楽
クラシック音楽には、集中力を高める効果もあります。クラシック音楽には穏やかでリズミカルなメロディーやハーモニーが多く、その音楽に聴き覚えがある人は集中力が高まる傾向があるのです。また、特定の楽器の音色によっては脳の活性化を促し、読書の理解力を向上させる可能性があるとされています。
そして、クラシック音楽は、長時間の演奏や複雑な楽曲構成が多いため、聴くことで脳がトレーニングされ、注意力や集中力が高まるとされています。
2)ジャズ
ジャズは、スムーズなメロディーやリズム、独特な音色が特徴的で、集中力を高める効果があります。特にインストゥルメンタルのジャズは、読書中のBGMとして適しているとされています。また、ジャズ音楽は即興演奏が重要な要素の一つであり、演奏者が楽曲を自由にアレンジすることができます。そのため、ジャズ音楽は読書中にも注意力を高める効果があると考えられています。ただし、ジャズ音楽の中でもテンポの速い曲や複雑なアドリブが多い曲は、読書の邪魔になる可能性があるため注意が必要です。
3)ピアノ曲
ピアノ曲は、落ち着いた雰囲気や穏やかなメロディーが多く、集中力を高める効果があります。また、無言で演奏されることが多いため、読書中の邪魔になりにくいというメリットもあります。ピアノ曲は音楽の中でもメロディーがシンプルで、同じメロディーが繰り返されることが多いため、脳が音楽を処理するのに集中力を使わずに済みます。そのため、読書中にピアノ曲を聴くことで、脳がリラックスして集中力を高めやすくなるとされています。ただし、個人差はあります。
4)自然音楽
自然の音を取り入れた音楽は、リラックス効果が高く、集中力を高める効果があります。たとえば、海の波音や鳥のさえずりなど、自然の音を取り入れた音楽は、リラックス効果が高く、ストレスを軽減することができます。
ただし、人によって好みや集中力に合う音楽のジャンルは異なるため、自分に合った音楽を選ぶことが重要です。また、読書中に聞く音楽は、あくまでBGMの役割を果たすものであるため、音量や選曲にも注意が必要です。
自然音を取り入れた音楽が集中力が高まる理由は、人間が自然の音に長い期間暮らしてきた進化の過程で、自然音に対して感受性を持っているためです。自然音は人間の心理的なストレスを軽減させる効果があることが研究からも示されています。
また、自然音は周波数が安定しているため、聞き続けることで脳波が安定し、リラックス効果も期待できます。したがって、自然音を取り入れた音楽は集中力を高めるだけでなく、ストレス軽減やリラックス効果も期待できます。
読書中に音楽を聴きながらリラックス効果をもたらすクラシックとジャズ
リラックス効果をもたらす音楽には、一般的にはクラシック音楽やジャズ、自然音や白いノイズ、雨音などが挙げられます。これらの音楽は、緊張を和らげたり、心を落ち着かせる効果があるとされています。
これらの音楽は脳波に影響を与える可能性があります。脳波は、睡眠やリラックスの状態で変化します。
例えば、自然音は波の音や鳥のさえずりなど、自然界で聞こえる音を模したものであり、脳波をリラックス状態に導くと言われています。ジャズ音楽にも同様の効果があるとされており、そのリズムや音色が脳波に影響を与え、リラックス効果を引き出すことができます。クリック音については、一定間隔で鳴る音が脳波にリズミカルな刺激を与え、集中力を高めるとされています。ただし、個人差があるため、どの音楽が自分にとって効果的かは、実際に聞いてみることが必要です。
また、個人的な好みによっても、リラックス効果をもたらす音楽は異なるため、自分に合った音楽を探すことが大切です。
読書のテーマと合わせて音楽を選択するのもあり
読書をより深く楽しむためには、読書のテーマに合わせて音楽を選択することも有効かもしれません。例えば、小説の舞台が西部開拓時代のアメリカであれば、カントリー音楽やフォークソングがテーマに合った音楽となるでしょう。歴史小説の場合、時代に合わせた古楽やバロック音楽がテーマに合った音楽となります。また、冒険小説やアクション小説の場合は、エネルギッシュでダイナミックな音楽が合うかもしれません。
ただし、あまりにもテーマに合わせすぎた音楽を聴くと、読書に集中できなくなることもあるため、自分に合ったバランスを見つけることが重要です。たとえば、集中力を高めたい場合は、静かで落ち着いた音楽を選ぶこともできます。また、読書の場所や時間帯によっても、適した音楽は異なるため、状況に合わせた適切な音楽を選ぶことが大切です。
読書中に音楽を聴くことでマイナス効果が起こる場合もある
読書中に音楽を聴くことでマイナス効果が起こる場合もあります。
これは、音楽が読書の内容と合わない場合、あるいは音楽が過剰刺激になってしまう場合に起こります。たとえば、読書中に軽快なポップスやロックを聴いていると、歌詞に注意が向いたり、リズムに合わせて体が動いたりして、読書に集中できなくなってしまうことがあります。また、過度に静かな音楽を聴くと、逆に読書に集中できず、眠気を誘発することがあります。
また、個人差もあります。音楽を聴くことで刺激を受けやすい人や、音楽と読書の両方に慣れ親しんでいる人は、集中力が高まる場合もありますが、逆に音楽に集中してしまい、読書に集中できない場合もあります。
したがって、読書中に音楽を聴く場合は、自分に合った音楽を選ぶことが大切です。自分が好きなジャンルやアーティスト、または読書のテーマに合わせた音楽を選ぶことで、プラス効果を得ることができます。さらに、音量や音質も調整することで、快適な読書環境を作ることができます。
音楽聴きながら読書できないジャンル
読書中に聴くとマイナス効果になるジャンルは、人によって異なる場合がありますが、以下のようなジャンルが挙げられます。
1)ボーカル入りの歌
歌詞に意識が向き、集中力が散漫になる可能性があります。
2)ジャズやフリージャズ
複雑な音楽構成やリズムが、注意力を逸らしてしまうことがあります。
3)テンポの速い音楽
アップテンポの音楽は、聴いているだけで興奮状態になり、集中力が散漫になる可能性があります。
4)自分が好きな曲
好きな曲を聴くと、曲に思い入れや感情が絡んでしまい、読書に没頭できなくなることがあります。
これらのジャンルは、読書中に聴くとマイナス効果になると感じる人もいれば、全く問題なく聴ける人もいます。自分に合った音楽を選ぶことが重要です。
集中力が散漫になる音楽
集中力が散漫になる音楽は、個人差がありますが、以下のような特徴を持つ音楽が挙げられます。
1)歌詞がある音楽
歌詞を聴いていると、脳が言葉を処理するために、読書に集中することができなくなります。
2)ジャンルによっては、リズムやメロディが複雑な音楽
複雑な音楽は脳に刺激を与え、注意を引きつけるため、読書に集中することが難しくなります。
3)一貫した音楽ではなく、突然音量が変わる音楽
突然の音量の変化は、注意をそらすため、読書に集中することが難しくなります。
4)騒がしい音楽
騒がしい音楽は、ストレスを与え、読書に集中することが難しくなります。

まとめ
モーツァルトやヒーリングミュージック、あるいは、ゆったりとしたジャズピアノなど、アルファ波が出やすくなる音楽はたくさんあります。
好きな音楽を聴く姿勢と、読書に最適な音楽・読書に集中しやすい音楽は、別物であることをご理解ください。
リラックスして記憶力が高い状態にあり、アルファ波が出ている状態は、音楽を楽しんでいる状態とは違います。しかし、読書を効果的に、読書タイムを有益なものにしたいとお考えでしたら、アルファ波が出やすい状態になるジャンルをおすすめします。
関連記事一覧
- 読む書く
- 読書
- 読書のやり方に関する注意のまとめ
- 読書の姿勢を理想的にすれば集中力アップし疲れは低下する
- 寝ながら読書の姿勢では集中が続かないし眠くなる
- 目が悪くなる原因は読書ではなく姿勢と環境
- 読書は時間の有効活用|時間を作る方法
- 読書に音楽はプラス効果かマイナスか*当記事
- 読書習慣を身につけよう!誰でも始められる読書習慣化のコツ
- 読書には場所が必要|読書場所問題は発想を変えれば解決
- 社会人に読書が必要な理由|本読んでないと出世する人にならない
- 読書の方法が正しければ人生が変わり始めていきます
- 頭に入る読書の仕方はノートしだい
- 読書率の低下|地域(県)別・年代別・世界との比較
- 読書家の世界|有名人の読書事例から個性的な楽しみ方まで
- 読書家あるあるエピソード|いくつ共感できる?
- 東京で読書会を探している人におすすめの記事
- 読書会オンラインの魅力と成功のポイント
- 読書会のやり方:社内および大学での効果的な実施方法と成功の秘訣
- 読書初心者におすすめのジャンルと選び方|自己啓発〜ミステリー
- 読書の仕方完全ガイド:基本から応用まで