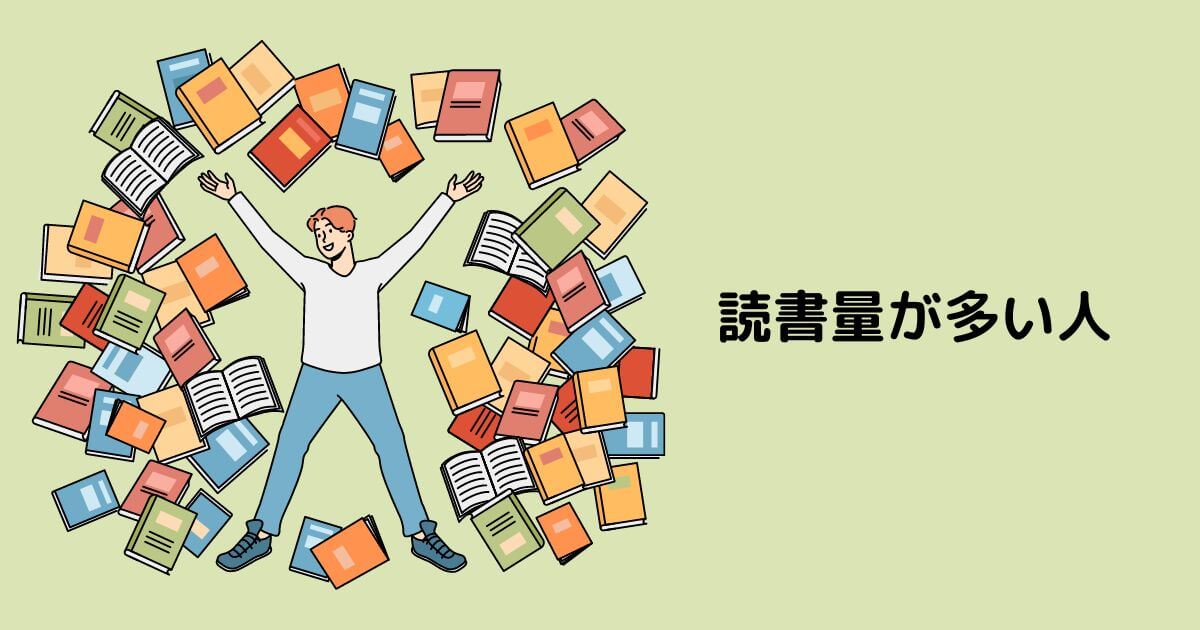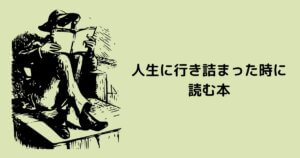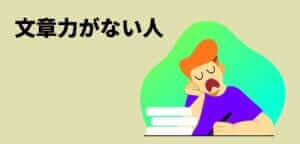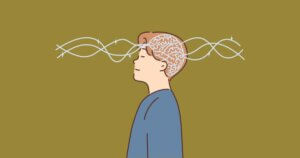実は日本人の読書量は世界から見ると多くありません。読書をしないという人の割合は、半分近いという調査結果もあります。日本人の読書量が少ないことと、平均賃金が低いことには何らかの関係性があるのかもしれません。
一般的に、成功者と言われる人には読書量が多い人が多いと言われます。なぜ読書量が多い人の方が成功するのでしょうか。
あくまでも一般論としてではありますが、以下のような理由があると考えられています。
・読書によって、知らなかった知識や情報を知ることができる。
・読書をすることで、新しい単語や言葉を学び語彙力が向上する。正確で豊かな表現ができる。
・論理的思考力が向上し、正確な判断や意見を形成することができるようになる。
・創造性が刺激され、より多様なアイディアを生み出すことができる。
・ストレスを解消できている。
以上の要因から読書量が多い人の方が、自分自身を磨くことができ、より多くのチャンスを掴むことができるとされているのです。いわゆる成功者に限らず、学生であっても社会人であっても、読書量が多い人の方が良い結果が得られるようになるのです。
当記事では、読書量が多い人が共通して持っている特徴や習慣に注目し、成功のヒントとなることを目指しています。
読書量が多い人に共通する特徴
読書量が多い人には以下のような共通する特徴があると言われています。
1.好奇心が旺盛:読書量が多い人は、好奇心が旺盛で、常に新しい知識や情報を得ようとする傾向があります。
2.継続力がある:読書は時間と労力を要するため、継続力が必要です。読書量が多い人は、自己管理能力が高く、毎日の習慣として読書を続けています。
3.集中力が高い:長時間の読書には、集中力が必要です。読書量が多い人は、集中力が高く、長時間集中して読書に没頭できる傾向があります。
4.目標意識が強い:読書量が多い人は、自分自身に読書の目標を設定し、それを達成するために努力する意識があります。
5.時間を有効に使う:読書は、交通機関の移動時間や待ち時間など、ちょっとした空き時間にもできるため、時間を有効に使えることが重要です。読書量が多い人は、時間を無駄にしないように工夫し、読書に割り当てる時間を確保しています。
読書量が多い人が共通に持っている読書に関する特徴
読書量が多いと言われる人には、読書に関して共通する以下のような特徴もあるのです。
読書量が多い人は読書のための時間を作っている
読書量が多い人は、読書に時間を割いています。例えば、毎日の通勤時間や寝る前など、ちょっとした空き時間を読書に充てることで、1日あたりの読書量を増やしています。
読書量が多い人は幅広いジャンルに興味がある
読書量が多い人は、幅広いジャンルに興味があり、様々な種類の本を読んでいます。小説やエッセイだけでなく、専門書やビジネス書など、さまざまな分野の本を読むことで、新しい知識や視野を広げることができます。
読書量が多い人は本を選ぶ基準が明確
読書量が多い人は、読む本を選ぶときに基準が高く、明確な基準を持って本を選ぶ傾向があります。自分の興味や目的に合った本を選ぶことで、有益な情報を得ることができます。
読書量が多い人は読書に没頭できる環境を作る
読書量が多い人は、読書に没頭できる環境を整えることができます。例えば、静かな場所で読書をする、集中できる音楽を聴くなど、読書に集中するための環境を整えることで、より効果的な読書ができます。
読書量が多い人は効果を最大限に引き出している
読書量が多い人は、読書の成果を活かすことができます。読んだ本から得た知識や情報を実践に役立てることで、自己啓発やキャリアアップに繋げることができます。
読書量が多い人は読書スピードが速い
読書量が多い人は、一般的に読書スピードも速い傾向があります。これは、読書に慣れているために読書スピードが上がり、また、高い集中力を持っているために効率的に本を読むことができるからです。
読書量が多い人が持っている習慣
読書量が多い人が持っている習慣に注目することは、自分自身の読書量を増やすことにプラスに影響する可能性があります。真似ができることから実践してみることをお勧めします。
読書量が多い人は朝読書の習慣がある|読書スケジュールを習慣に
朝読書の習慣を持つことは、読書量が多い人の中には見られます。朝は、脳がリフレッシュされた状態で、集中力や記憶力が高まるため、効率的な読書ができるとされています。また、朝に読書をすることで、自分自身のための時間を確保し、一日を良い気持ちでスタートできるというメリットもあります。
ただし、朝の時間帯に読書が合わない人や、朝忙しい人は、他の時間帯に読書の習慣を持つことでも十分効果があるかもしれません。重要なのは、自分に合った読書習慣を見つけ、継続することです。
読書量が多い人は常に本を持ち歩く習慣がある|読書時間を確保する習慣
読書量が多い人の中には、常に本を持ち歩く習慣がある人が多くいます。これは、自分の好きな本や読みたい本を手軽に読むことができるため、空いた時間を有効活用できるというメリットがあります。例えば、通勤時間や待ち時間などのスキマ時間に、本を読むことで、読書時間を確保することができます。
また、常に本を持ち歩くことで、読書に対する意識が高まり、自然と読書の習慣が身につくことも期待できます。本を持ち歩くことができるかどうかは、個人の生活スタイルや環境によって異なります。電子書籍をスマホやタブレットで読むという方法をとっている方も多くいます。
読書量が多い人は読書メモの習慣がある
読書量が多い人の中には、読書メモの習慣を持っている人が多いです。読書メモとは、読んだ本や記事の内容や感想を書き留めることです。
読書メモをすることで、以下のようなメリットがあります。
- 読んだ本の内容をしっかりと覚えておくことができる。
- 自分自身の考えを整理することができる。
- 読書の傾向や興味を把握し、今後の読書選択の参考にすることができる。
また、読書メモは、自分自身の成長や学びにもつながります。過去に書いたメモを振り返ることで、自分がどれだけ成長したかを実感できるため、モチベーションの維持にもつながります。

読書量が多い人は読書会への参加や読書仲間を持つ習慣がある
読書量が多い人の中には、読書会への参加や読書仲間を持つ習慣を持っている人が多いです。読書会は、同じ本を読んで集まり、その本について議論をする場です。読書仲間は、お互いに読んでいる本の内容や感想を共有し、モチベーションの維持や新たな読書の発見につながります。
読書会や読書仲間を持つことで、以下のようなメリットがあります。
- 読書に対する意欲が高まり、新たな本に挑戦するモチベーションが生まれる。
- 他人の意見を聞くことで、自分の考えを深めることができる。
- 読書を通じて、新しい人間関係を築くことができる。
読書量が多い人は読書の中で得た知識やアイデアを実践することを習慣にしている
読書量が多い人は、読書で得た知識やアイデアを実践することを習慣にしている人が多いです。読書を通じて、新たな知識やアイデアを得ることができますが、それらを実際の行動に移さなければ、意味がありません。実際に行動を起こすことで、自分自身の成長や目標の達成につながります。
読書で得た知識やアイデアを実践するためには、以下のようなことが重要です。
- 読書で得たことを整理し、具体的な行動計画を立てる。
- 継続的な行動を起こすために、定期的な振り返りを行う。
- 失敗しても、諦めずに再度挑戦すること。
また、自己啓発書やビジネス書を読んでいる人は、その内容を実践するために、日々の業務に活かすことが多いです。
読書量が多い人はネットやスマートフォンの使用を制限する習慣がある
一般的に、読書量が多い人はネットやスマートフォンの使用を制限する習慣があると言われています。これは、スマートフォンやインターネットが注意散漫になりがちで、読書に没頭することができなくなってしまうからです。
読書に集中するために、スマートフォンの通知をオフにしたり、一定時間だけネットから離れる時間を作るなどの方法があります。
成功者の読書量と習慣
成功者と言われる著名人や経営者の中には、読書量が多い人は少なくありません。本記事では代表的な成功者の読書量と習慣について紹介いたします。
ビル・ゲイツの読書量と習慣
ビル・ゲイツは年間に50冊以上の本を読んでいることで知られています。彼のブログ「Gates Notes」では、彼自身が読んだ本についてのレビューや感想を公開しており、その数は膨大なものになっています。
ビル・ゲイツは、毎日1時間以上の読書時間を確保していると言われています。また、彼は読書に関する情報を整理するために、自分でノートを取っています。これらのノートには、本の要約や重要なポイント、興味深い引用などが記載されています。
また、ビル・ゲイツは、自分の興味や好奇心に合わせて、様々な分野の本を読んでいます。彼は、科学、テクノロジー、ビジネス、歴史、哲学などの幅広い分野に興味を持っており、それらの本を読むことで自分の知識や視野を広げることができると考えています。
彼の読書習慣について、Netflixのドキュメンタリー『Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates』(邦題: 『天才の頭の中: ビル・ゲイツを解読する』)でも取り上げられています。このドキュメンタリーでは、彼の読書習慣からアイデアを実現するまでの仕事ぶりが垣間見られます。
ウォーレン・バフェットの読書量と習慣
投資家のウォーレン・バフェットは多くのビジネス関係者にとって、読書家としても有名です。彼は常に多くの時間(1日の80%)を読書に費やしているといいます。彼は読書をすることで得た知識やアイデアを投資に活かしています。
バフェットが好んで読むのは、ビジネスや投資、経済に関する書籍です。彼が特に愛読する著者として知られるのは、ベンジャミン・グレアムやフィリップ・フィッシャーなどです。また、彼はビジネス書だけでなく、自伝や伝記、歴史書、新聞なども広く読んでいます。
マーク・ザッカーバーグの読書量と習慣
Facebookのマーク・ザッカーバーグも読書かとして知られていますが、具体的な読書量については諸説あるようです。
マーク・ザッカーバーグは多くのビジネス書や哲学書を愛読することで知られています。彼は自身のFacebookページで年間の読書リストを公開することでも有名です。一例として、2015年にはAeneid、The Structure of Scientific Revolutions、Creativity, Inc.、Gang Leader for a Day、The Player of Gamesなど、約23冊の本を読んだと報告しています。
また、ザッカーバーグは自身のFacebookにおいて、「A Year of Books」というプロジェクトをスタートさせ、年間で12冊の本を選び、Facebookグループでの議論を通じて読書体験を共有するという試みを行っています。このプロジェクトは非常に人気があり、多くの読者が参加しました。ザッカーバーグはまた、読書が彼にとってどのように役立っているかについて、自身のFacebookに投稿したビデオで語っています。
イーロン・マスクの読書量と習慣
イーロン・マスクは、過去に毎日2冊ずつ読書していたことがあるとして、「読書の鬼」と呼ばれることもあるようです。
イーロン・マスクはビジネス書や科学書など、幅広いジャンルの本を読むことで知られています。彼は自身のビジネス哲学に深く影響を与えたとされる『ハイパーローカル化時代の起業戦略』や、マルチプラネット時代を迎えるにあたっての想像力を刺激する『火星移住計画』など、未来志向の書籍を好んで読んでいるようです。
孫正義の読書量と習慣
ソフトバンクの孫正義氏は、起業した当時に3年間で4000冊の本を読んだという話が伝わっています。最近では、1日に3時間から5時間の読書時間を持っているようです。読み終わった本はリサイクルショップで処分し、次の本を購入するという習慣があるようです。
また自身のブログや講演で、読書が自身のビジネスに大きな影響を与えていることを明言しており、ビジネスに取り組む上での重要性を訴えています。
柳井正の読書量と習慣
ユニクロの創業者である柳井正氏もまた読書家と知られる著名人です。経営の準備と勉強に重要なのは「読書」と明言しています。公開しているブログによると、彼は1年間で約100冊の本を読んでいるといいます。また、彼は常に手帳を持ち歩き、読書中に気になったことやアイデアをメモすることを習慣にしているようです。さらに、柳井氏は読書会に参加することもあり、他の読書好きの人々と意見交換をすることで、自身の視野を広げることもしています。
星野佳路の読書量と習慣
星野リゾートの創業者の星野佳路もまた大の読書家として知られています。星野氏は、ビジネス書や経済書、歴史書、小説など、幅広いジャンルの本を読むことで知られています。また、読書時間を確保するために、自社のリゾート地である「星のや」などでの宿泊中には、部屋に本を常備しているというエピソードもあります。
ビジネス上の問題解決のヒントを読書から得ていることも公開しています。
カズレーザーの読書量
とても博識なお笑い芸人として知られるカズレーザーさんも読書家の一人です。読書量は最近の数年間でさらに増加しているようです。2016年当時の資料では、年間に200冊は読むようにしているというコメントがあります。しかし2022年のコメントでは、「年間500冊の本を購入する」としています。
購入することは、そのまま読書量とは言えませんが、テレビ番組内で繰り広げられる知識量からすれば、ある程度は積読をしているとしても500冊のうちのかなりの読書量があるものと思われます。
拾い読みや速読などのテクニックを使って読んでいるのかもしれませんが、知識に残る読み方をしているようです。
又吉の読書量
お笑い芸人からプロの作家への転身(?)を成功させた又吉さんもまた読書家として知られる一人です。2016年当時のコメントに「読破した本の数は2000冊以上」と述べています。
忙しい中でも読書を続ける秘訣は、「5〜10分でも時間があれば、細切れになっても読み進めること」としています。私たちが読書量を増やす方法にも真似できる方法です。
2022年のコメントから察すると、最近の読書量は1ヶ月で10冊以上のようです。文化庁の調査結果に照らし合わせると、上位3%未満(7冊以上読んでる人が3%)ということになります。
読書量の目安はどのくらいに
一般的な読書量に関する調査結果を知り、さらに著名人の読書量を知った上で、自分自身はどのくらい読書量を読めばいいのか、と考える方もいるかもしれません。
読書量は単純に多ければいいというものではありません。たくさん本を読んでも自分の知識情報として残せないという人もいます。またエビングハウスの忘却曲線という理論もあり、人は本を1度しか読まない程度では忘れてしまうこともわかっています。同じ本を繰り返し読書したり、同じテーマの本を複数読んだりすることで、復習効果などにより知識は忘れにくくなっていきます。
ですので、読書量は何冊読めばいいという目安を決めることは難しいのです。本の読み方や、復習の仕方やメモの取り方など複雑に関連するからです。読書量にこだわるよりも、読書の頻度にこだわる方が成果が大きいかもしれません。つまり何冊という読書量ではなく、毎日1時間などというように読書頻度にこだわるということです。
中学生の読書量の目安
中学生の読書量の状況を知るには、前述の全国学校図書館協議会のデータや、学研の調査結果(中学生白書Web版)が役に立ちます。全国学校図書館協議会のデータよりも学研の調査結果の方が、より細かく調査されています。
1ヶ月に10冊以上読んでいる人が5%いる反面、全体の読書量の平均は2冊をやや下回っている状況です。小学生の時には、月に5〜10冊読んでいた方でも、中学生の学年が進むにつれて読書量が減少してしまいます。
中学生の読書量の目安としても、やはり1週間に一冊、つまり1ヶ月に4冊ほどを読書量の目安とすると良いのかもしれません。
まとめ
読書量が多い人の特徴と著名人の読書量についてなどを紹介してまいりました。
必ずしも読書量が多い人の方が頭がいいとか、人生や仕事の成功者になれるなどと言い切れるものではありません。しかし知識と情報源をたくさん持っている人の方が、チャンスを多く持てることは事実です。
関連記事一覧