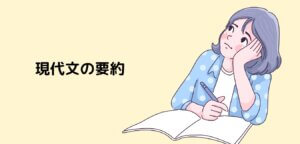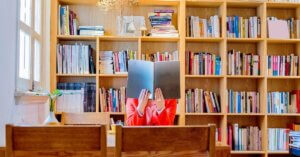斜め読みや拾い読み・飛ばし読みという言葉を聞いたことがあると思います。
きちんと読んでいないという印象があるかもしれません。しかし目的を持って読むことで、飛ばし読みは合理的な読み方となります。但し、飛ばし読みは、読み飛ばしとは違いますので注意も必要です。
速読セミナー等で教わる正当な技術(本来の速読テクニック)ではありませんが、読書スピードは結果的に速くなります。
飛ばし読みを効率良くするコツとリスク
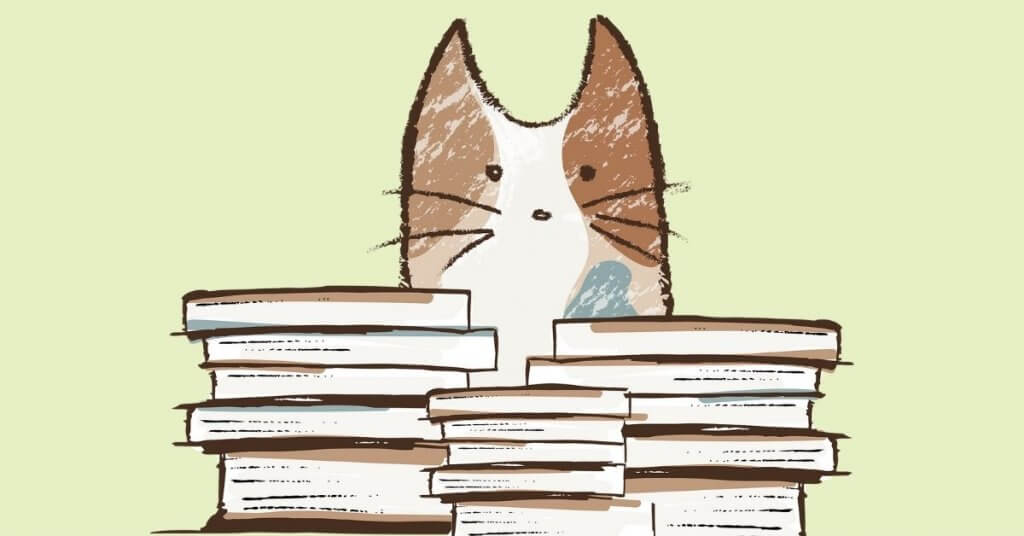
飛ばし読みをすることで、読書スピードは格段に上がります。ただし間違えた方法で実行すると、飛ばし読みではなく読み飛ばしになってしまいます。読み飛ばしになってしまうと、本の内容が頭に残らないというリスクがあります。飛ばし読みは正しく行いましょう。

飛ばし読みとは
「飛ばし読み」とは、文章やテキストを一部省略して読むことを指します。主に時間を節約するためや、大量の情報を処理する際に使われる読み方です。初心者の方にもわかりやすく説明しますね。
文章を飛ばし読みする際、以下のポイントに気を付けると良いです。
1. 見出しとサブ見出しのチェック: 記事や文書の見出しやサブ見出しを読むことで、内容の概要をつかむことができます。これにより、全体の流れや重要なトピックを理解しやすくなります。
2. 段落の冒頭と結論の読み: 各段落の最初と最後を読むことで、その段落の主要なアイデアやまとめが分かります。これにより、詳細な内容をすべて読むことなく、大まかな内容を掴むことができます。
3. 強調されたテキストに注目: 文章内で太字や斜体、強調されたテキストがある場合、それに注目すると重要な情報を見逃しにくくなります。これらのテキストは著者が特に重要だと考えているポイントを示すことが多いです。
4. 箇条書きや表をチェック: 文章内に箇条書きや表がある場合、それらを読むことで、要点を簡潔につかむことができます。情報を整理して提示しているため、重要な部分が分かりやすくなります。
読書は飛ばし読みでもすることで大差になる
読書は、内容を理解し情報を得るための重要な活動です。一方で、その読み方にはいくつかのアプローチがあります。飛ばし読みもそのひとつです。しかし、飛ばし読みと徹底的な読書とでは、その効果には大きな差が生じることがあります。
飛ばし読みは、時間を節約しながら主要なポイントをつかむ方法です。テキストの見出しやサブ見出し、段落の冒頭と結論を読むことで、大まかな内容やアイデアをつかむことができます。しかし、飛ばし読みだけでは詳細な情報や深い理解は得にくいです。
一方、徹底的な読書は、時間をかけて文章全体を理解し、細部まで踏み込む方法です。全文を読むことで、文脈や背景、著者の意図などを正確に把握できます。これにより、より深い知識や洞察を得ることができます。
この違いから、両者の効果には大差が生じます。飛ばし読みは短時間で大まかな情報を手に入れるのに有効ですが、詳細な理解や深い知識は得にくいです。一方で、徹底的な読書は時間がかかりますが、より豊かな知識や理解を獲得できると言えます。
最終的に、目的や状況に応じて適切な読み方を選ぶことが大切です。情報を手早く仕入れたい場合は飛ばし読みが有用ですが、深い知識や理解を求める場合には徹底的な読書が必要です。バランスを保ちながら、適切な読み方を選んで学習することが肝要です。
飛ばし読みを効率良くするコツ
飛ばし読みは正しく利用すれば、読書スピードはとても速くなります。正しく飛ばし読みを行うためにはポイントがあります。次のポイントに沿って実行して下さい。
1)本を読む前に、この読書から何を学ぶのかの目的を意識する
2)目的に沿って、目次から読むべき部分とそうではない部分を確認し飛ばし読みをする
3)特にビジネス書では既に知っている知識情報に関して記載されていることがあるので、その部分は飛ばして読む
4)引用は著者の主張を根拠づけるための部分なので飛ばし読みする
読書を始める前に何を学ぶのか目的を意識する
ビジネス書の多くは200ページから300ページで書かれています。そもそも、著者が強く主張している主旨は1ページしかない場合もあります。主旨や結論と考えても数ページしかないのです。
今回の読書の目的をどう考えるのかによって、読むべきページ数はほんのわずかになる可能性があります。それ以外のページは、無駄ということではなく、今回の読書には読むべきページとは言えないということです。
別の機会に、学びたい目的が変わってきたときに、読むべきページに変わる可能性があります。
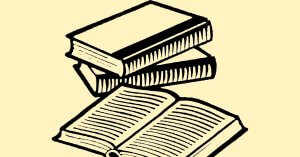
目的に沿って、目次から今回読むべきページかそうではないページかを分ける
人は得たいと考えているときに、関連する物事は脳に定着しやすいものです。目次から今回の目的に沿うページとそうではないページを分けましょう。そうではないページは、別の機会に違う目的で読むときに、必要なページになる可能性があります。
仮に今回の目的から外れているページを読んだとしても、今回の読書の目的と外れている場合、役立つ知識情報として脳に定着しない可能性が高いです。一旦記憶されたとしても役立てる機会が明確ではないために、知識情報は薄らいでしまうからです。
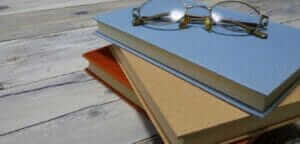
既に知っている物事に関する記述あるページは飛ばし読みをする
もちろんです。既に知っている物事に関する記述があるページを飛ばし読みするのは、効率的な読書の方法です。以下にそのポイントを説明いたします。
既に知っている情報やトピックについての記述があるページを読む際には、次の手順を考慮して飛ばし読みを行うことができます。
- 見出しやサブ見出しの確認: ページ内の見出しやサブ見出しをチェックすることで、そのページの主要なトピックや内容を把握できます。これにより、ページ全体の要点をつかむことができます。
- 初めと終わりの読み: ページの冒頭と結論を読むことで、そのページの主要なアイデアやまとめを理解できます。これにより、詳細な内容を全て読まなくても大まかな情報を得ることができます。
- 重要なフレーズや強調された部分に注目: ページ内で特に重要なフレーズや強調された部分に目を向けることで、そのページのキーポイントを素早く把握できます。これらの部分は著者が特に重要だと考えている箇所です。
この方法により、既に知っている情報に関するページを効率的に読むことができます。ただし、全く新しい情報やトピックに関するページに対しては、詳細な理解を得るために徹底的な読書が必要です。目的に応じて飛ばし読みを上手に活用することで、時間を節約しながらも必要な情報を手に入れることができます。
引用部分は読み飛ばします
引用部分は、主張の根拠づけや具体例として示されているものです。引用自体には、著者の主張はありません。
先の既に知っている情報と同様に、読み飛ばしましょう。この時点で、本書の読書の目的からすると、読むべきページがあまりない書籍であるという結論が成り立つ場合もあります。

小説の飛ばし読みはおすすめできない
もちろんです。「小説の飛ばし読みはおすすめできない」というテーマについて、専門用語を避けてわかりやすく説明いたします。
小説は物語やキャラクター、情景が織り交ぜられた楽しい読書体験です。しかし、その魅力や深みを十分に味わうために、飛ばし読みはおすすめできません。以下にその理由を説明します。
1. 物語の流れと魅力を損なう可能性がある: 小説はキャラクターの感情や関係性、物語の流れが重要な要素です。飛ばし読みだけでは、登場人物の成長や関係性の変化、意外な展開などが見逃されてしまう可能性があります。
2. 深い感情やテーマの理解が難しい: 小説はしばしば深い感情やテーマを描いています。全文を読まないと、登場人物の内面やメッセージが適切に理解できない場合があります。
3. 著者のスタイルや言葉選びを楽しめない: 小説は著者の独特なスタイルや言葉選びが楽しめる作品も多いです。飛ばし読みではその魅力を感じることが難しくなります。
4. 作品の全体的な価値を損なう可能性がある: 小説は全体が織り成す作品であり、部分的な理解だけでは作品の全体的な価値を享受することが難しいです。全文を読むことで作品全体の魅力を最大限に味わえます。
したがって、小説を最大限に楽しむためには、できるだけ全文を読むことがおすすめです。登場人物の成長や変化、物語の展開、深い感情やテーマを正しく理解し、著者の独自の世界を楽しむためには、時間をかけてじっくり読むことが大切です。
速読と飛ばし読みの違い
もちろんです。「速読と飛ばし読みの違い」について説明いたします。
速読と飛ばし読みは、いずれも効率的な読書方法を指す言葉ですが、異なるアプローチを持っています。
速読:
速読は、文章を素早く読むことで、一定の理解を保ちながらも読書のスピードを向上させる技術です。速読の目的は、より多くの情報を短時間で処理することですが、一方で高い理解度を維持することも重要です。速読の主な特徴は以下です。
- 文脈を重視: 速読では文章の文脈を把握しつつ、主要なアイデアやポイントを迅速に理解します。文章全体の意味や流れを捉えることが目指されます。
- 目の動きの最適化: 速読の技術には、目の動きを最適化する方法が含まれます。特定のテキストを一度に見る範囲を広げることで、複数の単語やフレーズを同時に捉えることを助けます。
- 理解度の保持: 速読では、スピードを上げながらも、文章の内容を十分に理解することが重要です。高い理解度を維持することで、効率的かつ有益な読書が可能となります。
飛ばし読み:
飛ばし読みは、文章をざっと流し読みして主要なポイントやアイデアをつかむ方法です。飛ばし読みの主な目的は、短時間で大まかな内容を理解することで、詳細な理解よりも情報の収集に焦点を当てます。飛ばし読みの主な特徴は以下です。
- 主要な情報の把握: 飛ばし読みでは、見出しやサブ見出し、段落の冒頭と結論などを読むことで、主要なアイデアやポイントを素早く把握します。
- 詳細な理解より速度重視: 飛ばし読みはスピードを重視し、詳細な理解よりも大まかな内容を早く把握することを目指します。一部の情報を省略しても、全体の理解が成り立つようにします。
- 深い洞察は不足: 飛ばし読みでは、詳細な情報や深い洞察は得にくいです。一方で、広範なテキストを効率的に処理できる利点があります。
要するに、速読は高い理解度を保ちつつスピードを向上させる技術であり、飛ばし読みは大まかな内容を素早く把握する方法です。目的や状況に応じて適切な読書方法を選ぶことが大切です。
飛ばし読みと読み飛ばしの違いとリスク|飛ばし読みの癖
飛ばし読みと読み飛ばしは、似て非なるものです。飛ばし読みは、上記の解説の通り、読む前に決めた目的に沿って、読む部分と読まない部分を決めて、読まない部分を飛ばして読む方法です。
読み飛ばしは、単に速く読むことの方が目的となり、内容をよく吟味せずに飛ばしてしまっている状態です。ですので、本の内容が頭に残ることも少ないし、肝心な部分も読み込めていないリスクが高くなります。
本を速く読むことを意識しすぎると、飛ばし読みが癖になってしまうリスクもあります。飛ばし読みは前述したようなコツを使って、必要な部分を読み進める方法です。特に同じテーマの本を読む場合には、既知の知識情報が記載されている可能性も考えられます。飛ばし読みが効果的になるケースです。
しかし飛ばし読みが癖になってしまうと、読み込みが浅いテーマに関しても、飛ばし読みをしてしまうリスクがあります。そういうケースで飛ばし読みをすると、読了後に頭の中に残る知識情報は浅くて狭い範囲でしかなくなるリスクがあります。
飛ばし読みは発達障害に原因がある場合もあるが
「飛ばし読みは発達障害?」という質問について説明いたします。
飛ばし読み自体は、特定の読書方法の一つであり、一般的な読書活動において情報を効率的に処理するための手段として使われます。飛ばし読みを行うこと自体は、発達障害とは直接的に関係ありません。発達障害は、神経発達の際の異常や障害に関連する状態を指す概念です。
ただし、発達障害を持つ人々にとって、読書や情報処理において飛ばし読みが好まれることがあるかもしれません。例えば、注意欠陥多動性障害(ADHD)を持つ人々は、集中力や情報処理において課題を抱えることがあり、飛ばし読みがより適切な読書アプローチとして感じられることがあります。
ただし、発達障害の症状や特性は個人によって異なるため、一概に「飛ばし読みは発達障害と関連する」とは言えません。発達障害を持つ人々も、一般の人々と同様に様々な読書方法を選ぶ可能性があります。
最終的に、飛ばし読みが発達障害と直接的な関連があるわけではなく、読書方法は個人の好みやニーズに合わせて選ばれるべきです。必要に応じて、効果的な読書アプローチを見つけることが大切です。
まとめ
飛ばし読みは、速読の中の一つの方法として紹介する事があります。当サイトの速読関連の記事でも紹介しています。
しかし、実際には速読というよりも読むべき部分を絞り込んで、効率よく読む方法です。結果的に、本を読むスピードは速くなります。

しかし、読み込み速度自体は変わっていません。読む部分を絞り込んで読まない部分を削っているだけの読み方です。ただ本をたくさん読むという人には、飛ばし読みをする人は多いです。
関連記事一覧
飛ばし読みを効率良くするコツとリスク*当記事