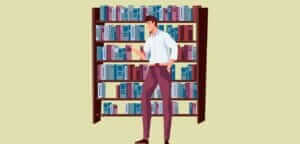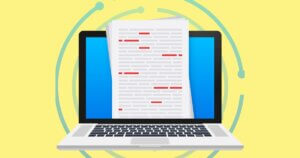文章力とはその名の通り文章を書く力ですが、相手がわかりやすいと感じることが必要条件です。相手が分かりにくいと感じてしまえば、どれほど良いことが書かれていても、文章力の高い良い文章とは言えないものです。
何を意識すれば文章力が高くなるのか、文章力がないと何が困るのかについて紹介しています。
文章力とは何か|相手に伝わる文章を書く力
文章力とは、情報やアイデアをクリアで効果的に相手に伝える能力を指します。優れた文章力を持つことは、書かれた文書が読み手に理解され、共感されることを保証します。
文章力は、適切な語彙、文法、構造の使用によって構築され、コンテキストに合った表現力を持つことも含まれます。ビジネス文書、レポート、メール、ブログ記事など、あらゆるコミュニケーション形式において重要であり、プロフェッショナルとしての成功に不可欠です。文章力を向上させるには、日常的な練習とフィードバックを受けることが肝要で、これにより情報伝達能力が向上し、職場や個人のコミュニケーションにおいて優れた成果を生み出します。
文章力とは、こちらが伝えたいことが相手に分かりやすく伝わる文章を書く力です。
文章力とは言い換えると
文章力とは、言い換えると「言葉で思考やアイデアを他人に伝える能力」です。これは、情報をクリアで理解しやすい形で文章化し、他の人に伝えるスキルを指します。
文章力を持つことは、ビジネスコミュニケーション、アカデミックライティング、クリエイティブな表現など、様々なコンテキストで重要です。良い文章は、読む人にとって魅力的で理解しやすく、感情や情報を効果的に伝えることができます。
文章力を高めるには、語彙力の向上、文法の正確さ、論理的な構成、読み手のニーズに合った表現力などが必要です。文章力はプロフェッショナルな成功や個人的な表現力向上に寄与するため、継続的なトレーニングと実践が不可欠です。
文章力がない原因は
文章力がない原因はいくつかの要因に起因します。主な原因を以下に示します。
- 経験不足: 文章を書くことは経験の積み重ねが重要です。文章を書く機会が少なかったり、あまり書かない環境で育った場合、文章力が不足することがあります。
- 語彙力の不足: 豊かな語彙力は良い文章を書くために不可欠です。語彙が限られていると、表現の幅が狭まり、文章が単調になりがちです。
- 文法の知識不足: 文法のルールを理解していないと、文章に誤字脱字や文法の誤りが多く含まれる可能性があります。これは文章の質を低下させます。
- 表現力の不足: アイデアや感情を効果的に表現できない場合、読者に伝わりにくい文章を書いてしまうことがあります。表現力の向上が必要です。
- 練習の不足: 文章力は練習によって向上します。定期的に文章を書く機会を持たない場合、スキルが停滞することがあります。
- 自己自信の欠如: 自信がないと、良いアイデアや意見を文章に起こすことが難しくなります。自己表現への不安が文章力の低下につながることがあります。
- 文書構造の理解不足: 文章の構造や論理的な展開を理解していないと、文章が混乱しやすくなります。読み手にとって整理された内容を提供できないかもしれません。
これらの原因は個人によって異なりますが、文章力を向上させるためには定期的な練習、学習、フィードバックの受け入れが重要です。文章力を高めるためには、努力と継続的な学習が必要です。

文章力の基本
文章力の基本について、初心者の方にも分かりやすく説明しますね。
文章力とは、上手に文章を書く能力のことを指します。良い文章を書くためには、以下の基本的な要素が重要です。
- 明確な目的意識: 文章を書く前に、何を伝えたいのか、読み手にどんな印象を与えたいのかを明確にしましょう。目的意識があると、文章の内容がぐっとまとまります。
- 読み手を意識した表現: 読み手の立場に立って文章を書くことが大切です。相手が専門的な知識を持っている場合でも、難しい言葉や専門用語を使いすぎないように心掛けましょう。分かりやすく説明することが大切です。
- 適切な構成: 文章は、はじめから終わりまでスムーズに読み進められるように構成されると良いですね。まずはじめに主題を示し、中身は段落ごとに1つのアイディアを明確にし、最後にまとめをつけると分かりやすくなります。
- 具体的な例や事例: 読み手が抽象的な概念を理解しやすくするためには、具体的な例や事例を挙げると良いです。実際の経験や具体的なイメージを伝えることで、文章がより生き生きとします。
- 適切な語彙: 豊かな語彙を持つことは文章力の鍵です。同じ言葉を繰り返さず、バリエーション豊かに表現することで、文章がより魅力的になります。
- 文法と文構造: 文章は正確な文法と適切な文構造で成り立っています。主語と動詞の一致や文のつながりに気を配ることで、読みやすく分かりやすい文章になります。
- 修正と校正: 最初に書いた文章は完璧ではないことがよくあります。書き上げた後は、何度か文章を読み直し、修正や校正を行いましょう。文章を洗練させることができます。
これらの基本を意識しながら、自分の思いをしっかりと伝えられるように文章を磨いていきましょう。文章力は練習と経験によって向上しますので、積極的に挑戦してくださいね。
文章力を磨く方法は
文章力を磨く方法はいくつかありますので、具体的な方法をご紹介しますね。
- 多読・多書き: 読むことで他の人の文章の構成や表現を学び、書くことで自分の文章力を向上させることができます。さまざまなジャンルやスタイルの本や記事を読んで、異なる視点や表現を吸収しましょう。
- 定期的な練習: 文章を書く習慣を身につけるために、定期的にライティングの練習を行うと良いです。日記やブログ、エッセイなど、毎日少しずつでも文章を書くことで上達します。
- フィードバックを求める: 自分の文章を他人に見てもらい、フィードバックをもらうことで成長できます。信頼できる友人や先輩に読んでもらい、アドバイスを受けることで改善点が見つかるでしょう。
- 文章の構成を意識する: 文章は明確な構成が大切です。主題をはじめに示し、段落ごとにまとまった内容を持たせ、最後にまとめを入れるなど、読み手が迷わずに読み進められるように工夫しましょう。
- 文法と表現の勉強: 文法の基本を理解することで、正確な文章を書くことができます。また、多彩な表現を学ぶことで文章が豊かになります。
- 読み手の視点に立つ: 読み手の立場になって文章を書くことが重要です。相手がどんな背景や知識を持っているのかを考慮し、わかりやすく伝えることが大切です。
- 編集と修正: 書いた文章は一度で完成することは少ないです。何度も読み直して、不要な言葉を省き、表現を洗練させることで、より良い文章に仕上げることができます。
これらの方法を意識して文章を書く習慣を身につけると、自然な日本語の文章が書けるようになります。地道な努力が必要ですが、継続することで確実に文章力は向上します。是非、挑戦してみてくださいね。
文章力は複数の力で出来ている
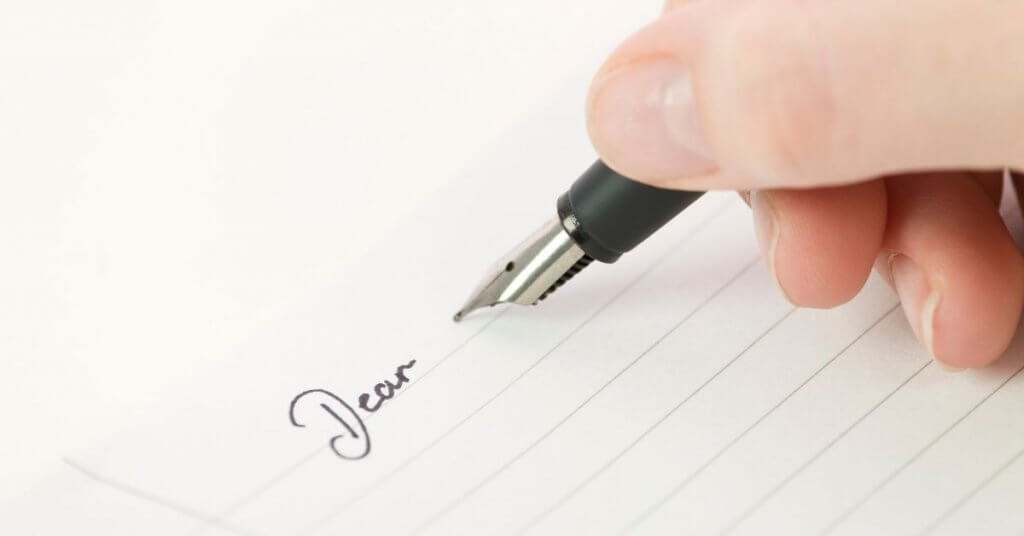
相手にわかりやすく伝わるための文章力には、いくつか注意する点があります。それぞれが〇〇力と呼ばれるものです。実際には、一口に「文章力」と言っている文章を書く力は、「相手にわかりやすく伝わる」ことを前提とすると、文章力を構成している複数の〇〇力を集結させる必要があるのです。
文章力を構成している力には以下のようなものがあります。漠然と文章力のトレーニングをしようと考えるよりも、それぞれの力を高めていくことで、文章力が高まると考える良いです。
1)文章構成力
2)語彙力
3)敬語
4)相手へ対する想像力
5)発想力
6)要約力
7)注意力
文章力には論理的な構成設計
相手にわかりやすい文章とは、言葉の使い方と構成によって生まれます。特に構成については、人が理解しやすい物事の順番が決まっていますので、分かりやすい構成を覚えておくと良いです。
分かりにくい文章とはどういう状態かを抑えておきましょう。例えば旅行で行き先がわからずに乗り物に乗っていると不安になります。分かりにくい文章とはゴールがわからない文章です。
論理的に話す場合、結論から先にいうという方法がありますが、文章も同じです。結論を先に示すことで、文章が底に向かっていることがわかり、相手にはわかり易い文章になります。
論理的で理解しやすい文章の構成を設計することが、文章を書くとき最初に取り掛かることです。大枠の構成で一般的なものでは、以下のようなものがあります。
・結論ー理由(根拠)ー事例ー結論
・問題提起ー反論・疑問ー解決提案ー選択提案ーまとめ
・概要(序文)ー詳細(本文)ーまとめ
・事実ー説明と意見ー提案ー提案についての結果
文書の目的によって、どの構造が最適なのか判断します。
文章力には語彙力が必要
語彙力は、文章をより魅力的にし、効果的に伝えるために欠かせない要素です。語彙力とは、言葉の知識と使い方の幅を指します。適切な言葉を選び、ニュアンスを伝えることで、文章の表現力が向上します。
また、正確な単語を使うことで情報を正確に伝え、読み手との共感を生むことができます。語彙力が高ければ、読み手に親しみを持たせる言葉やメタファーを使い、文章に彩りを与えることも可能です。
語彙力を向上させるためには、多読や単語帳の活用、対話を通じて新しい言葉を覚えることが重要です。日々の練習と学習を通じて語彙力を養い、魅力的で伝わりやすい文章を書けるようにしましょう。
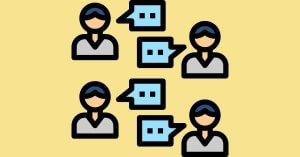
文章力には敬語
ビジネス文書であっても、単純に言葉や単語を並べればいいわけではなく、組み合わせることによって、状態や状況を最適に表現する必要があります。
相手が社外であれば、なおさらです。せっかく敬語を使っているのに、間違えた表現をしてしまい相手からの信頼を無くする可能性もあります。
例えば、敬語には相手に対して使う尊敬語と、自分を下げて表現する謙譲語、そして全般に使う丁寧語があります。自分に使うべき謙譲語を相手の行動に対して使う失敗はありがちな表現の間違いです。
語彙力とも関連する表現力もあります。言葉自体を知っていること、言葉の使い方を知っていること、言葉の使い所を知っていることが必要です。

文章力には想像力で相手視点から考える
文章の分かりやすさが最適かどうかを考えるには、相手視点で考えるという想像力が必要です。
よくある間違いは、「自分は相手のことを思って考えた」というものです。まさによくある失敗です。相手のことを想像しているようでいて、実は自分の価値観で考えている可能性があるからです。
想像力を使って考えるということは、思いやりを持って考えることでもあります。「相手の身になったつもりで、相手視点で考える」ことをすると、出てくる答えが違うことがあります。
例えば成績の悪い営業マンは、「顧客が求めているのは安いことだ。値引きを希望しているに違いない。」と考えてしまいます。しかし顧客は、「値段以前に、まず安心できる商品・サービスなのか」「買った後で失敗したと思いたくない」を心配しています。
また商品サービスや関連用語への理解度は、相手によって違います。相手の理解度を想像して文章を書く必要があります。一般ユーザーなのか、関連取引先なのか、社内の部下なのか上司なのか、によって理解度はそれぞれ違います。一般的には、一般ユーザーに専門用語はNGですし、取引先に対しては専門用語でなければおかしいでしょう。
ですので、分かりやすい文章を書くには、想像力を働かせる必要があるのです。
文章力には発想力が必要
特に一般客へ向けた文章を作る場合や、社内でのプレゼンをする場合など、毎回同じ文章や資料では良くないケースがあります。発想力とは思いつき力と置き換えても良いかもしれません。
どういう文章を作っていけば、伝わりやすいか、分かりやすいかを考えるときに、論理性はもちろん大事ですが、思いつきのように、発想して追加した文章が相手の心に刺さることもたくさんあります。
文章力には要約力で情報を詰め込みすぎない
文章作成では、要約力も必要です。多くの情報を使って、分かりやすくしたいと考えてしまいますが、情報を詰め込みすぎることが分かりにくくしてしまうこともあります。
そんなときには、次回のチャンスに詳細情報を伝えることとして、今回は多くの情報のエッセンスだけを要約して伝えることも必要です。
もちろん、文章で伝えられる次のチャンスがないこともあり得ます。全部の情報を詰め込むのではなく、要点をまとめるように要約して、短い文章にまとめることも必要です。

文章力には注意力を持って全体俯瞰
7つ目の注意力を使って全体俯瞰をするのは、文章を一通り書き終えた後に行うことです。構成を設計した書いたはずですが、完成した文章を全体俯瞰してみて、分かりにくくなっていないか、誤字脱字や表現力など全てのチェックも含めて、注意力を使って確認する必要があります。
社内の文書であれば、ミスがあっても自分の評価を下げる(もちろん大問題)ことで済むかもしれませんが、社外となれば、そうはいきません。
よくありがちなのは、ミスをしたのは自分の責任と考える人がいることです。社外文書の場合は、そう簡単ではありません。特に単純な誤字脱字ミスではなく、表現や敬語や言葉遣いなどが問題となり、取引先と今後の取引中止となることは十分にあり得ます。
ですから、文章を作成し、社外に発信する場合は、必ず責任者のチェックを受けることです。自分の一存で発信してはいけません。それが可能なのは、社長だけです。

まとめ
社会人に必要な文章力は、単純に文章を書けるということではないことをご理解いただけたと思います。
良い文章とは相手が求めることが書かれている文章です。そして、文章力が高いということは、相手に伝えたいことがわかりやすく伝わる文章を書けているということです。

相手にわかりやすく読み取れるためには、上記の7つの能力が必要です。もし何か不足しているような気づきがありましたら、意識して練習をすることです。
練習しない限り、年齢と共に自動的に、良くなって行くものではないからです。
関連記事一覧
文章力とは何か?文章力は複数の力で出来ている*当記事
文章力の基本|メールからビジネスまで、77のテクニックで学ぶ